聖書物語 ノーマン・メイラー著
2011年5月8日 読書 コメント (3)
子供の頃通っていた保育園はカソリック系だった。
教室の前にイチジクの樹があって、その向こう側に
小さな礼拝堂がちゃんとあった。
週に一度聖書の時間があって神様のお話を聞いたはずだが、
退屈だった思い出しかない。
小学生になって旧約聖書を読んだらとても面白かったのだが、
新約聖書は相変わらず意味不明で、
数ページも読まずに挫折したのだった。
イエスという人もその考え方も全くあやふやでとっかかりが掴めなかったんだと思う。
そんな私ですが、この本は一気に読めてしまいました。
面白かったです。
ここで描かれたイェシュア(イエス)は、間違いなく神の子であり、
数々の奇跡を行い、時には<神の声>を聞いて(<声>よりは<直感>に近い)、
貧しき人々に愛と希望の光を見出そうとする聖人であります。
そして同時に質素な大工出身で、喉も渇けば腹も減り
時には美しい娼婦(マグダラのマリア)に心動かされ、
「神は答えてくれない・・・。」と失望し、
弟子と信者たちがいつまでたっても無知無能で、本質的なことを理解しないと
一人で苛立つ30代の青年でもある。
これら二つの姿の見事な対比によって、薄っぺらな紙のようだった彼が、
血肉を供えた人物として目の前に鮮やかに立ち現れてくる。
エキサイティングな体験でした。
おそらくこのイエス像は著者であるノーマン・メイラー独自の解釈によるものでしょう。
後書きにもあるように、著者の意図は聖書の解釈でなく、神がかり的才能を持った青年の
光と影を描ききることだったようです。
もうひとつこの本の視点の面白いところは、神とイェシュアとの関係性です。
ここでは神は、全知全能の存在としては描かれていません。
物語の中でイエスは何度も「わが父」と呼びかけるのですが、
息子の切羽詰った心の叫びに<常に>応えるわけでもない。
そのたびイェシュアは自分の無力さを痛感し、言葉と奇跡によって人々を救おうという信念がゆらぐのを感じます。
最終的にゴルゴダの丘の上で磔にされ、苦痛の中で命の炎が消えゆくのを実感しながら、
神は万能ではない。
悪魔との戦いに明け暮れる神は、世界の瑣末まで関っていられないのだと悟る瞬間は
とても暗示的でした。
---------------------------------------------------------------
本を読みながらふとICWRのワン・シーンを思いだしました。
毛布にくるまったShitaoが一人涙を流すところ。
「神(=父)の声が聞こえない。」
もしかしたらそんな絶望感に満ちたシーンだったのかも。
教室の前にイチジクの樹があって、その向こう側に
小さな礼拝堂がちゃんとあった。
週に一度聖書の時間があって神様のお話を聞いたはずだが、
退屈だった思い出しかない。
小学生になって旧約聖書を読んだらとても面白かったのだが、
新約聖書は相変わらず意味不明で、
数ページも読まずに挫折したのだった。
イエスという人もその考え方も全くあやふやでとっかかりが掴めなかったんだと思う。
そんな私ですが、この本は一気に読めてしまいました。
面白かったです。
ここで描かれたイェシュア(イエス)は、間違いなく神の子であり、
数々の奇跡を行い、時には<神の声>を聞いて(<声>よりは<直感>に近い)、
貧しき人々に愛と希望の光を見出そうとする聖人であります。
そして同時に質素な大工出身で、喉も渇けば腹も減り
時には美しい娼婦(マグダラのマリア)に心動かされ、
「神は答えてくれない・・・。」と失望し、
弟子と信者たちがいつまでたっても無知無能で、本質的なことを理解しないと
一人で苛立つ30代の青年でもある。
これら二つの姿の見事な対比によって、薄っぺらな紙のようだった彼が、
血肉を供えた人物として目の前に鮮やかに立ち現れてくる。
エキサイティングな体験でした。
おそらくこのイエス像は著者であるノーマン・メイラー独自の解釈によるものでしょう。
後書きにもあるように、著者の意図は聖書の解釈でなく、神がかり的才能を持った青年の
光と影を描ききることだったようです。
もうひとつこの本の視点の面白いところは、神とイェシュアとの関係性です。
ここでは神は、全知全能の存在としては描かれていません。
物語の中でイエスは何度も「わが父」と呼びかけるのですが、
息子の切羽詰った心の叫びに<常に>応えるわけでもない。
そのたびイェシュアは自分の無力さを痛感し、言葉と奇跡によって人々を救おうという信念がゆらぐのを感じます。
最終的にゴルゴダの丘の上で磔にされ、苦痛の中で命の炎が消えゆくのを実感しながら、
神は万能ではない。
悪魔との戦いに明け暮れる神は、世界の瑣末まで関っていられないのだと悟る瞬間は
とても暗示的でした。
---------------------------------------------------------------
本を読みながらふとICWRのワン・シーンを思いだしました。
毛布にくるまったShitaoが一人涙を流すところ。
「神(=父)の声が聞こえない。」
もしかしたらそんな絶望感に満ちたシーンだったのかも。
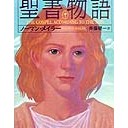

コメント
>「神(=父)の声が聞こえない。」
そうだ、と思えます。
「傷ついた人を救っても救っても救いきれない。」という悲しみなのかと思ってたけど。
マザーテレサが死の数年前に「神の声が聞こえない」とつぶやいていた、
という話も思い出しました。
それもアリだと思います。
私もこの本を読むまでは
「この苦痛がいつまで続くんだろう?」(どんな傷も僕を殺せないとするならば)
・・・という恐怖と絶望の涙かなと考えてました。
まぁ、あの作品、特にShitaoに関してはどんな解釈・どんな妄想も成立するわけですから(笑)
それだけに、いつまでも私の心を捉えて離さない人物でもあり。
マザー・テレサのその言葉は・・・とても痛々しいですよね。
誰よりも献身的に働いてきた彼女が、最後に辿りついた認識がそれというのは・・・。
キリスト教的な神と人間の間柄は、<悟り>を最終目的地とする仏教とは異質なものな気がします。
キリスト教的な神様は内面世界を旅することより、行動せよ、と命じているような気がしました。
それゆえ、最終目的地を、人は死ぬ瞬間でも見出すことができないのかもしれない。
・・・意外と残酷な結末ですよ、この「聖書物語」にしても・・・。
「神はこたえない」という絶望…
それは、苛酷な現実を最期まで見つめたことの証明なのかもしれませんが。
「天は自ら助くる者を助く」という言葉でさえ、きついなと思ったことがあります。
仏教的な諦観をよしせず、死=涅槃、とは見なされない世界では、
行動停止や、苦しみから逃れようとすることは敗北を意味するのか?
だから逆に、無条件の許しや救いが、甘美な輝きを放つのかなぁ。