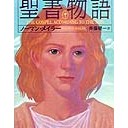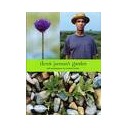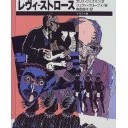TAKUYA KIMURA×MEN’S NON-NO ENDLESS
2011年9月30日 読書
まずENDLESSから見てます。
あまりにもいろんな感覚を刺激され感情がこみ上げてきた。
なんかわけわかんない状態に(笑)
とりあえず考えを纏めるために、ざっと見た感想。
1.時間軸に沿って並べるやり方がとてもよかった。
2.やはり役に入ってるときの彼の写真は、とてもいい。
3.そしてなぜか、後になるほどどんどんよくなる。
4.野口強コーディネイト撮り下ろし。不良オヤジと青年の絶妙なバランス。
このまんま映画が一本できそう。
5.祐真さんのコーディネイトの美青年(アラフォーだがw)魅力的過ぎるだろう。
リラックスムードでちょっと素が垣間見える感じでいい。
このお二人に対する彼の評が抜群に冴えている。
最後のロング・インタビュー。
見えてたこと・見えてなかったこと。
複雑で深くて大きな感情的経験を重ねてきたんだろうな。
ファッション誌にこれだけたくさん登場し続けた一人のタレントの、多彩な表情と
その時々のトレンドを楽しんでもいい。
また、ある男性の人生の一部分を、ファッション写真という手段で切り取って
時間軸に沿って編集した記録と見ることもできる。
そして、「100Questions 100Answers」のQ51への答え。
どうしてこういう言葉がサラッと出てくるんだか(笑)
だから好きだよ。
*しっかし・・・なんで見本の映像がアレなの?不自然すぎ。
面白いから載せます。
あまりにもいろんな感覚を刺激され感情がこみ上げてきた。
なんかわけわかんない状態に(笑)
とりあえず考えを纏めるために、ざっと見た感想。
1.時間軸に沿って並べるやり方がとてもよかった。
2.やはり役に入ってるときの彼の写真は、とてもいい。
3.そしてなぜか、後になるほどどんどんよくなる。
4.野口強コーディネイト撮り下ろし。不良オヤジと青年の絶妙なバランス。
このまんま映画が一本できそう。
5.祐真さんのコーディネイトの美青年(アラフォーだがw)魅力的過ぎるだろう。
リラックスムードでちょっと素が垣間見える感じでいい。
このお二人に対する彼の評が抜群に冴えている。
最後のロング・インタビュー。
見えてたこと・見えてなかったこと。
複雑で深くて大きな感情的経験を重ねてきたんだろうな。
ファッション誌にこれだけたくさん登場し続けた一人のタレントの、多彩な表情と
その時々のトレンドを楽しんでもいい。
また、ある男性の人生の一部分を、ファッション写真という手段で切り取って
時間軸に沿って編集した記録と見ることもできる。
そして、「100Questions 100Answers」のQ51への答え。
どうしてこういう言葉がサラッと出てくるんだか(笑)
だから好きだよ。
*しっかし・・・なんで見本の映像がアレなの?不自然すぎ。
面白いから載せます。
むき出しの茶色い地面に降り立つのか?
それともまさに飛び立とうとしているのか?
ドイツ製の白地にオレンジのラインの鮮やかなヘリ。
青い空をバックに佇む、サビの浮き出た白い防波堤の表面。
晩秋の、エクリュの空に黒い神経線維のように張りついて見える
梢と散りそこねた枯葉。
王冠型の白いサーカス?のテントを、真っ黒な作業着に身を包んだ、とても小さく見える男が
塗装している遠景。
(表紙の写真です)
・・・どんなに文章で表現しても、その一枚のインパクトにかすりもしないと思い知る。
野口里佳の写真の被写体は、美しい人物あるいは風景ではなく。
ある決定的瞬間でもない。
技巧を凝らした『アーティスティックな』一枚というのでもない。
しかし、その日常的で同時に非日常的にも思える、目を奪うようなある瞬間が、
まさにそうあるべき姿で、色合いで、質感で、焼き付けられたんだな、と思う。
ページをめくるごとにその<一瞬>へと目線が入り込んでしまう。
言葉で表現しようのない、<見ること>の快感をたっぷり味わえるのです。
横浜トリエンナーレの『鳥と人』のシリーズを見て虜になって、ネットで探しました。
amazonでは品切れになってますが、こちらから直接購入できます。
↓
http://www.mdn.co.jp/di/book/44191/
野口里佳特別編集、とでもいうような構成になっていてとてもいい本でした。
インタビューも読み応え充分。
それともまさに飛び立とうとしているのか?
ドイツ製の白地にオレンジのラインの鮮やかなヘリ。
青い空をバックに佇む、サビの浮き出た白い防波堤の表面。
晩秋の、エクリュの空に黒い神経線維のように張りついて見える
梢と散りそこねた枯葉。
王冠型の白いサーカス?のテントを、真っ黒な作業着に身を包んだ、とても小さく見える男が
塗装している遠景。
(表紙の写真です)
・・・どんなに文章で表現しても、その一枚のインパクトにかすりもしないと思い知る。
野口里佳の写真の被写体は、美しい人物あるいは風景ではなく。
ある決定的瞬間でもない。
技巧を凝らした『アーティスティックな』一枚というのでもない。
しかし、その日常的で同時に非日常的にも思える、目を奪うようなある瞬間が、
まさにそうあるべき姿で、色合いで、質感で、焼き付けられたんだな、と思う。
ページをめくるごとにその<一瞬>へと目線が入り込んでしまう。
言葉で表現しようのない、<見ること>の快感をたっぷり味わえるのです。
横浜トリエンナーレの『鳥と人』のシリーズを見て虜になって、ネットで探しました。
amazonでは品切れになってますが、こちらから直接購入できます。
↓
http://www.mdn.co.jp/di/book/44191/
野口里佳特別編集、とでもいうような構成になっていてとてもいい本でした。
インタビューも読み応え充分。
久々に赤を着たくなった。
2011年8月22日 読書
GINZA。
ソニア パークPRESENTS 蒼井優が着るミニマルな「赤」
「JAPAN RED」と題して「赤」をテーマにコーディネイトしています。
この「赤」がとても綺麗なんですよね~・・・。
久々に<赤い色の服>が着たくなりました。
昔働いてた会社の色見本に、国別の伝統色で分類してるのがあって。
<日本の色><中国の色><フランスの色>・・・みたく。
例えば一口に「赤」といっても、青みがかったものからまっ赤、黄みがかったもの、
薄いもの、濃いもの、白っぽいもの、黒っぽいもの・・・明度と彩度の変化で
実に豊富。
しかも国によって色彩のパレットのニュアンスが違うのです。
その色をどうやって作り出すのか、材料や比率の違いと、もうひとつはその国の自然の中に
どんな色が多いのか、で色彩のセンスが違ってくるのかもしれません。
日本の色彩は比較的彩度の低いものが多い気がします。
絵の具のチューブから絞りだしたまんまの色でなく、少しずつ混ぜたような曖昧な色彩は
あまり強い印象を与えない代わりに微妙な陰影に富む。
日本人的美意識なのかも。
でも、赤は別格。
ここでいうJAPAN REDは、所謂「朱赤」にちかい鮮やかな赤。
やや黄色のニュアンスを帯びつつも、どこか凛とした透明度のある赤。
うっすら黄みがかった日本人の肌に、よく馴染む色。
そうそう、茜色という優雅な響きの名前がしっくりきます。
個人的には成人式の着物の色です(笑)
赤い紅型(沖縄の伝統の文様)の振袖だったんです。
そんな「赤」を、蒼井優さんが着る。
時にはイヴニングドレスだったり、少し懐かしいクラシックな丸襟のカーディガンだったり。
彼女の長い黒髪によく映えて、とても印象的です。
撮影は上田義彦氏。
去年の春、ゲツコイ直前のキムラを、静謐にエロティックに、
一方で、ソフィスティケートされた都会のオトコっぽく。
もう一方で、人慣れしない野性の生き物のように切り取った方。
被写体の個性はまったく違うのに、なんといいますか・・・。
凛として静かな、ただよう空気感が似ています。
ソニア パークPRESENTS 蒼井優が着るミニマルな「赤」
「JAPAN RED」と題して「赤」をテーマにコーディネイトしています。
この「赤」がとても綺麗なんですよね~・・・。
久々に<赤い色の服>が着たくなりました。
昔働いてた会社の色見本に、国別の伝統色で分類してるのがあって。
<日本の色><中国の色><フランスの色>・・・みたく。
例えば一口に「赤」といっても、青みがかったものからまっ赤、黄みがかったもの、
薄いもの、濃いもの、白っぽいもの、黒っぽいもの・・・明度と彩度の変化で
実に豊富。
しかも国によって色彩のパレットのニュアンスが違うのです。
その色をどうやって作り出すのか、材料や比率の違いと、もうひとつはその国の自然の中に
どんな色が多いのか、で色彩のセンスが違ってくるのかもしれません。
日本の色彩は比較的彩度の低いものが多い気がします。
絵の具のチューブから絞りだしたまんまの色でなく、少しずつ混ぜたような曖昧な色彩は
あまり強い印象を与えない代わりに微妙な陰影に富む。
日本人的美意識なのかも。
でも、赤は別格。
ここでいうJAPAN REDは、所謂「朱赤」にちかい鮮やかな赤。
やや黄色のニュアンスを帯びつつも、どこか凛とした透明度のある赤。
うっすら黄みがかった日本人の肌に、よく馴染む色。
そうそう、茜色という優雅な響きの名前がしっくりきます。
個人的には成人式の着物の色です(笑)
赤い紅型(沖縄の伝統の文様)の振袖だったんです。
そんな「赤」を、蒼井優さんが着る。
時にはイヴニングドレスだったり、少し懐かしいクラシックな丸襟のカーディガンだったり。
彼女の長い黒髪によく映えて、とても印象的です。
撮影は上田義彦氏。
去年の春、ゲツコイ直前のキムラを、静謐にエロティックに、
一方で、ソフィスティケートされた都会のオトコっぽく。
もう一方で、人慣れしない野性の生き物のように切り取った方。
被写体の個性はまったく違うのに、なんといいますか・・・。
凛として静かな、ただよう空気感が似ています。
アートディレクターが平林奈緒美さんに交代してから
ついつい毎号立読みしてます(笑)
で、今回は購入しました。
正直、これに掲載されてる服もバッグも靴も、
私が到底日常に身につけようと思うお値段ではありません。
ゼロが一桁(場合によっては二桁!)多かったりします。
でもレイアウトやグラフィック、つまり見せ方の面白さ、
カッコよさに惹かれてしまいました。
表紙でも充分伝わると思うのですが、写真はシンプルに。文字は効果的に。
ダイナミックでインパクトがありながら、見やすい。
すばらしい。
中身の構成も当然こんな感じであります。
もう一つ「上手いな!」と思わず唸ったのが、テーマの提示のしかた。
フツーに【秋冬注目のシューズ&バッグ、ぜんぶ見せます!】などという直球勝負なコピーも
もちろんアリですけど、
【フェティッシュ コケティッシュ】ですよ。
オシャレな女性にとって、靴とバッグは場合によっては服そのものより情熱の対象になります。
つまり、それらは【フェティッシュ】な存在であり、
秋冬のテーマの一つであるらしい【コケティッシュ】を語呂合わせ的に併記した上手さ。
ついつい中身をじっくり見たくなるではありませんか(←それは私だw)
肝心な中身のほうも、靴とバッグをただカタログ的に漫然と並べるのではなく、
例えば靴を「誘惑」「ダンス」「音楽」の切り口で分類したり、
バッグを「旅のシーン」別に相応しいシチュエーションを演出して見せたり、
とっても興味深い。
カタログと化したファッション雑誌とは根本的に発想が違うんですね。
まずコンセプトありきといいますか。
この面白さは文章で書いても伝わりにくいなぁ~・・・。
ヒマがあったら書店で見てくださいね。
一方にオマケで読者を釣って成功しているファッション誌の作り方があり、
また掲載品数で勝負のカタログと化したファッション誌もあり、
でも中にはこういう、遊び心満載の、作り手が楽しんで・情熱を持ってモノヅクリしてるのが
アツく伝わってくるファッション誌があってもいい。
so-enとともに新刊が毎回楽しみです。
あ、そうそう。
「読む」=コラムも良いです。
川上未映子さん×辛酸なめ子さんの「フェティッシュ、コケティッシュ」トークと、
あの「大奥」の作者(元BL漫画家w)よしながふみさんと語る「ベルばら手帖」
は、切り口が新鮮でとても面白かったデス。
特によしながさんの「アンドレが大好き!だってすごくバカでしょう?」
という観点は目からウロコであります(笑)
ついつい毎号立読みしてます(笑)
で、今回は購入しました。
正直、これに掲載されてる服もバッグも靴も、
私が到底日常に身につけようと思うお値段ではありません。
ゼロが一桁(場合によっては二桁!)多かったりします。
でもレイアウトやグラフィック、つまり見せ方の面白さ、
カッコよさに惹かれてしまいました。
表紙でも充分伝わると思うのですが、写真はシンプルに。文字は効果的に。
ダイナミックでインパクトがありながら、見やすい。
すばらしい。
中身の構成も当然こんな感じであります。
もう一つ「上手いな!」と思わず唸ったのが、テーマの提示のしかた。
フツーに【秋冬注目のシューズ&バッグ、ぜんぶ見せます!】などという直球勝負なコピーも
もちろんアリですけど、
【フェティッシュ コケティッシュ】ですよ。
オシャレな女性にとって、靴とバッグは場合によっては服そのものより情熱の対象になります。
つまり、それらは【フェティッシュ】な存在であり、
秋冬のテーマの一つであるらしい【コケティッシュ】を語呂合わせ的に併記した上手さ。
ついつい中身をじっくり見たくなるではありませんか(←それは私だw)
肝心な中身のほうも、靴とバッグをただカタログ的に漫然と並べるのではなく、
例えば靴を「誘惑」「ダンス」「音楽」の切り口で分類したり、
バッグを「旅のシーン」別に相応しいシチュエーションを演出して見せたり、
とっても興味深い。
カタログと化したファッション雑誌とは根本的に発想が違うんですね。
まずコンセプトありきといいますか。
この面白さは文章で書いても伝わりにくいなぁ~・・・。
ヒマがあったら書店で見てくださいね。
一方にオマケで読者を釣って成功しているファッション誌の作り方があり、
また掲載品数で勝負のカタログと化したファッション誌もあり、
でも中にはこういう、遊び心満載の、作り手が楽しんで・情熱を持ってモノヅクリしてるのが
アツく伝わってくるファッション誌があってもいい。
so-enとともに新刊が毎回楽しみです。
あ、そうそう。
「読む」=コラムも良いです。
川上未映子さん×辛酸なめ子さんの「フェティッシュ、コケティッシュ」トークと、
あの「大奥」の作者(元BL漫画家w)よしながふみさんと語る「ベルばら手帖」
は、切り口が新鮮でとても面白かったデス。
特によしながさんの「アンドレが大好き!だってすごくバカでしょう?」
という観点は目からウロコであります(笑)
雑誌にしては高い。1800円ですよ。
でも価格に見合うボリュームと視点の面白さ。
「フランス」とか「パリ」という文字に過剰に反応してしまうのは
自分の年代の特徴かも。
ファッション、映画、音楽、写真。自分のヲタク趣味の対象である香水。
大きな<アート>の括りでこの国は常に憧れの対象でありました
(←過去形かよw)
で、コレを読んで久々にその憧れが再燃しそうです。
所謂「オシャレなパリ/フレンチ案内」ではありません。
あそこに行けばこんなものが見れて、食べられて、買い物できて・・・という
マニュアル的な雑誌ではなく、
さまざまな顔をもつこの国を、個人的視点から掘り下げたレポートの集積といいますか。
もちろんフランス=恋愛大国という定番的視点もきっちり押さえつつ、
文化、風俗、歴史から斬り込んで、<フランス人>という人々の横顔のアウトラインを
浮かび上がらせる構成となっています。
・・・それにしてもフランス人てやっぱ大人やな~。←憧れ再燃。
写真もいいです。
上質紙なので微妙な色彩が生きていて、オマケにレイアウトもよい。
たくさん文字がありすぎて、蒸暑いのにいちいち読んでられんわ!!!!
と思って写真だけ見てても楽しいです。
「原発大国フランス」というもう一つの素顔にもきっちり言及していて、
フランス人と原発とのつきあい方の徹底ぶりのさわりを知るだけでも、
わが国の原発政策には何が足りないのか考えてみるきっかけになる。
先日風のように来日したジェーン・バーキンについてもちゃんと言及してくれてるし。
A Scent of Franceというタイトルの美しいフォトエッセイ。
かつてはフランス占領下にあったベトナム、サイゴン(現ホーチミン市)。
曽祖父が実はフランス人だったと知った21歳のベトナム人女性:リンの視線から描かれた、
<アジアに漂うフランスの残り香>の架空の物語。
今のサイゴン市のエキゾティックな写真とあいまってひと時暑さをわすれました。
でも価格に見合うボリュームと視点の面白さ。
「フランス」とか「パリ」という文字に過剰に反応してしまうのは
自分の年代の特徴かも。
ファッション、映画、音楽、写真。自分のヲタク趣味の対象である香水。
大きな<アート>の括りでこの国は常に憧れの対象でありました
(←過去形かよw)
で、コレを読んで久々にその憧れが再燃しそうです。
所謂「オシャレなパリ/フレンチ案内」ではありません。
あそこに行けばこんなものが見れて、食べられて、買い物できて・・・という
マニュアル的な雑誌ではなく、
さまざまな顔をもつこの国を、個人的視点から掘り下げたレポートの集積といいますか。
もちろんフランス=恋愛大国という定番的視点もきっちり押さえつつ、
文化、風俗、歴史から斬り込んで、<フランス人>という人々の横顔のアウトラインを
浮かび上がらせる構成となっています。
・・・それにしてもフランス人てやっぱ大人やな~。←憧れ再燃。
写真もいいです。
上質紙なので微妙な色彩が生きていて、オマケにレイアウトもよい。
たくさん文字がありすぎて、蒸暑いのにいちいち読んでられんわ!!!!
と思って写真だけ見てても楽しいです。
「原発大国フランス」というもう一つの素顔にもきっちり言及していて、
フランス人と原発とのつきあい方の徹底ぶりのさわりを知るだけでも、
わが国の原発政策には何が足りないのか考えてみるきっかけになる。
先日風のように来日したジェーン・バーキンについてもちゃんと言及してくれてるし。
A Scent of Franceというタイトルの美しいフォトエッセイ。
かつてはフランス占領下にあったベトナム、サイゴン(現ホーチミン市)。
曽祖父が実はフランス人だったと知った21歳のベトナム人女性:リンの視線から描かれた、
<アジアに漂うフランスの残り香>の架空の物語。
今のサイゴン市のエキゾティックな写真とあいまってひと時暑さをわすれました。
ずーっと読みたくて発売日の昨日、会社帰りに買いました。
『拡張するファッション』
序章からして興奮。
アートと時代性とシンクロしながら、
<拡張していく>生命体のような<ファッション>。
ガーリー全盛の’90年代から、ネットでパリコレのランウェイを
堪能できる現在まで。
ファッションの役割りも意味も変わっていく時代の流れの中で、
誰が・いつ・何を・どう表現してきたか?
キム・ゴードン、ソフィア・コッポラ、HIROMIX、長島有里枝、エレン・フライス。
時代のアイコンともいえる人たちのインタビューで構成された、
興味深く読み応えのある本です。
著者の林 央子(ハヤシ ナカコ)さんは、リニューアル後の『暮しの手帖』で
アート・ファッション関係のページを受け持ってらっしゃる方。
それでお名前を知ったのです。
林さんの視点の新鮮さと、フッションをキーワードに縦横無尽に広がっていく自由な好奇心、
コアの部分へ一気に辿りつく直観力の鋭さ。
それぞれのインタビューに思わず赤線を引きたくなるような箇所がたくさんあるんです。
(いえ、引きませんけど)
・・・や~。こういう本が読みたかったんですよ。
じっくり読んで、また感想をupしたいと思います。
さて。
何か映画を見たいな~と思いながら今週いけなかったのでDVDを借りてきました。
『スイミング・プール』と『ロミオ+ジュリエット』
とりあえず「ロミオ」の方から。
昔VHSで見ようとして途中挫折した苦い経験が(´д`;)
さー。今ならどうかしら~?
と思って見はじめたんですけど・・・やっぱり途中挫折・・・。
映像はそれなりに凝ってるんだよね。
シェークスピアの悲劇をまんま現代劇に移行させた設定で、
登場人物はアロハ着てたり、ギャングみたいだったり、キャデラック乗り回してる(笑)
なんとなくD.ジャーマンの『ジュビリー』辺りを意識したと思われる。
ディカプリオはきれ~ですよ~。ほんとに美少年で☆
しかし致命的に面白くない。
そもそもロミオとジュリエットという物語に何の興味もないから仕方ないかもですが、
映像が凝ってるわりにグっとこないのは何故なんだろう。
う~む。
そうだなぁ・・・一番の要因は台詞かもしれない。
皆シェイクスピア劇通りの台詞を喋るんだけど、発声が現代風で、
響きがあまり美しくない。←シェイクスピア劇よく知らないけどw
さらにやたら声がデカく、ちょうど映画で舞台のお芝居を見ている感じ。
見てて疲れました。
その違和感を上手くコントロールできてたら唯一無二の面白さに繋がったかな?
・・・と思うんですけどね。
どんな声で何をどう発するか。
とっても大事だわ・・・。
『拡張するファッション』
序章からして興奮。
アートと時代性とシンクロしながら、
<拡張していく>生命体のような<ファッション>。
ガーリー全盛の’90年代から、ネットでパリコレのランウェイを
堪能できる現在まで。
ファッションの役割りも意味も変わっていく時代の流れの中で、
誰が・いつ・何を・どう表現してきたか?
キム・ゴードン、ソフィア・コッポラ、HIROMIX、長島有里枝、エレン・フライス。
時代のアイコンともいえる人たちのインタビューで構成された、
興味深く読み応えのある本です。
著者の林 央子(ハヤシ ナカコ)さんは、リニューアル後の『暮しの手帖』で
アート・ファッション関係のページを受け持ってらっしゃる方。
それでお名前を知ったのです。
林さんの視点の新鮮さと、フッションをキーワードに縦横無尽に広がっていく自由な好奇心、
コアの部分へ一気に辿りつく直観力の鋭さ。
それぞれのインタビューに思わず赤線を引きたくなるような箇所がたくさんあるんです。
(いえ、引きませんけど)
・・・や~。こういう本が読みたかったんですよ。
じっくり読んで、また感想をupしたいと思います。
さて。
何か映画を見たいな~と思いながら今週いけなかったのでDVDを借りてきました。
『スイミング・プール』と『ロミオ+ジュリエット』
とりあえず「ロミオ」の方から。
昔VHSで見ようとして途中挫折した苦い経験が(´д`;)
さー。今ならどうかしら~?
と思って見はじめたんですけど・・・やっぱり途中挫折・・・。
映像はそれなりに凝ってるんだよね。
シェークスピアの悲劇をまんま現代劇に移行させた設定で、
登場人物はアロハ着てたり、ギャングみたいだったり、キャデラック乗り回してる(笑)
なんとなくD.ジャーマンの『ジュビリー』辺りを意識したと思われる。
ディカプリオはきれ~ですよ~。ほんとに美少年で☆
しかし致命的に面白くない。
そもそもロミオとジュリエットという物語に何の興味もないから仕方ないかもですが、
映像が凝ってるわりにグっとこないのは何故なんだろう。
う~む。
そうだなぁ・・・一番の要因は台詞かもしれない。
皆シェイクスピア劇通りの台詞を喋るんだけど、発声が現代風で、
響きがあまり美しくない。←シェイクスピア劇よく知らないけどw
さらにやたら声がデカく、ちょうど映画で舞台のお芝居を見ている感じ。
見てて疲れました。
その違和感を上手くコントロールできてたら唯一無二の面白さに繋がったかな?
・・・と思うんですけどね。
どんな声で何をどう発するか。
とっても大事だわ・・・。
ku:nel (クウネル) 2009年 05月号 [雑誌]
2011年5月14日 読書 コメント (2)
陶器には全く詳しくないけど、ご飯のお茶碗は粉引きが一番好きです。
布でいうと晒した木綿のような手触りでなんとなく温かみがあって、
あの質感と口をつけたときの感触が
炊きたてご飯のぴかぴかしたお米の色や甘い香り、
味わいにぴったりくるからです。
古い染付けの青も好きだなぁ。
藍染めの布と同じ薄い青から黒に近い群青まで、
人の手の温もりを感じます。
このku:nelにもそんな素敵な器がたくさん。
ソニア・パークさんや伊藤まさこさんの器も紹介されていて、
ああ、人となりがわかるなぁ、と。
しかし。
実は一番大事なページはそこではないのであった。
最後の方にひっそりと掲載されている、ルーシー・リーさんの陶器のボタン。
ルーシー・リーさんの陶器は有名だと思いますが、
一時期彼女が<生活のために>作っていた
様々な色合い・形のボタンがぎっしり。
丸いの・四角いの・リボンを結んだ形、お皿みたいな平べったいのや豆みたいな形や・・・
ずらっと並んだボタンたちは、同じようなデザインでも焼き具合によって
ほんの少しずつ微妙に違っていたりする。
もともと小さくてきれいなものがずらっと並んだのを見るのが好きなので、
眺めてるだけで幸せになります。
特に私が心引かれたのはターコイズのような鮮やかなブルー。
丸めた粘土をぺたっと平べったくしたような少し歪な楕円に、
南国の空のような青が乗っかっている。
表面が溶けてガラス化したかのような質感は、七宝焼きっぽくもあります。
じーっと見ていると吸い込まれそうな色。
見飽きません。
それより後ろのページにある、真っ白なボタンのシリーズもとても美しい。
これは、三宅一生氏のコレクションの為に制作されたそうです。
整った円形の、平べったいお皿の形。
端の所に絶妙のバランスで開けられた小さな穴。
無駄を削ぎおとしたミニマルな表現。
モダン・アートのようなデザイン。
前者のボタンと後者のボタンの制作まで、数十年の月日が流れていたそうです。
ルーシー・リーさんが晩年に辿りついた、美しいものの形を象徴しているような気がしました。
布でいうと晒した木綿のような手触りでなんとなく温かみがあって、
あの質感と口をつけたときの感触が
炊きたてご飯のぴかぴかしたお米の色や甘い香り、
味わいにぴったりくるからです。
古い染付けの青も好きだなぁ。
藍染めの布と同じ薄い青から黒に近い群青まで、
人の手の温もりを感じます。
このku:nelにもそんな素敵な器がたくさん。
ソニア・パークさんや伊藤まさこさんの器も紹介されていて、
ああ、人となりがわかるなぁ、と。
しかし。
実は一番大事なページはそこではないのであった。
最後の方にひっそりと掲載されている、ルーシー・リーさんの陶器のボタン。
ルーシー・リーさんの陶器は有名だと思いますが、
一時期彼女が<生活のために>作っていた
様々な色合い・形のボタンがぎっしり。
丸いの・四角いの・リボンを結んだ形、お皿みたいな平べったいのや豆みたいな形や・・・
ずらっと並んだボタンたちは、同じようなデザインでも焼き具合によって
ほんの少しずつ微妙に違っていたりする。
もともと小さくてきれいなものがずらっと並んだのを見るのが好きなので、
眺めてるだけで幸せになります。
特に私が心引かれたのはターコイズのような鮮やかなブルー。
丸めた粘土をぺたっと平べったくしたような少し歪な楕円に、
南国の空のような青が乗っかっている。
表面が溶けてガラス化したかのような質感は、七宝焼きっぽくもあります。
じーっと見ていると吸い込まれそうな色。
見飽きません。
それより後ろのページにある、真っ白なボタンのシリーズもとても美しい。
これは、三宅一生氏のコレクションの為に制作されたそうです。
整った円形の、平べったいお皿の形。
端の所に絶妙のバランスで開けられた小さな穴。
無駄を削ぎおとしたミニマルな表現。
モダン・アートのようなデザイン。
前者のボタンと後者のボタンの制作まで、数十年の月日が流れていたそうです。
ルーシー・リーさんが晩年に辿りついた、美しいものの形を象徴しているような気がしました。
聖書物語 ノーマン・メイラー著
2011年5月8日 読書 コメント (3)
子供の頃通っていた保育園はカソリック系だった。
教室の前にイチジクの樹があって、その向こう側に
小さな礼拝堂がちゃんとあった。
週に一度聖書の時間があって神様のお話を聞いたはずだが、
退屈だった思い出しかない。
小学生になって旧約聖書を読んだらとても面白かったのだが、
新約聖書は相変わらず意味不明で、
数ページも読まずに挫折したのだった。
イエスという人もその考え方も全くあやふやでとっかかりが掴めなかったんだと思う。
そんな私ですが、この本は一気に読めてしまいました。
面白かったです。
ここで描かれたイェシュア(イエス)は、間違いなく神の子であり、
数々の奇跡を行い、時には<神の声>を聞いて(<声>よりは<直感>に近い)、
貧しき人々に愛と希望の光を見出そうとする聖人であります。
そして同時に質素な大工出身で、喉も渇けば腹も減り
時には美しい娼婦(マグダラのマリア)に心動かされ、
「神は答えてくれない・・・。」と失望し、
弟子と信者たちがいつまでたっても無知無能で、本質的なことを理解しないと
一人で苛立つ30代の青年でもある。
これら二つの姿の見事な対比によって、薄っぺらな紙のようだった彼が、
血肉を供えた人物として目の前に鮮やかに立ち現れてくる。
エキサイティングな体験でした。
おそらくこのイエス像は著者であるノーマン・メイラー独自の解釈によるものでしょう。
後書きにもあるように、著者の意図は聖書の解釈でなく、神がかり的才能を持った青年の
光と影を描ききることだったようです。
もうひとつこの本の視点の面白いところは、神とイェシュアとの関係性です。
ここでは神は、全知全能の存在としては描かれていません。
物語の中でイエスは何度も「わが父」と呼びかけるのですが、
息子の切羽詰った心の叫びに<常に>応えるわけでもない。
そのたびイェシュアは自分の無力さを痛感し、言葉と奇跡によって人々を救おうという信念がゆらぐのを感じます。
最終的にゴルゴダの丘の上で磔にされ、苦痛の中で命の炎が消えゆくのを実感しながら、
神は万能ではない。
悪魔との戦いに明け暮れる神は、世界の瑣末まで関っていられないのだと悟る瞬間は
とても暗示的でした。
---------------------------------------------------------------
本を読みながらふとICWRのワン・シーンを思いだしました。
毛布にくるまったShitaoが一人涙を流すところ。
「神(=父)の声が聞こえない。」
もしかしたらそんな絶望感に満ちたシーンだったのかも。
教室の前にイチジクの樹があって、その向こう側に
小さな礼拝堂がちゃんとあった。
週に一度聖書の時間があって神様のお話を聞いたはずだが、
退屈だった思い出しかない。
小学生になって旧約聖書を読んだらとても面白かったのだが、
新約聖書は相変わらず意味不明で、
数ページも読まずに挫折したのだった。
イエスという人もその考え方も全くあやふやでとっかかりが掴めなかったんだと思う。
そんな私ですが、この本は一気に読めてしまいました。
面白かったです。
ここで描かれたイェシュア(イエス)は、間違いなく神の子であり、
数々の奇跡を行い、時には<神の声>を聞いて(<声>よりは<直感>に近い)、
貧しき人々に愛と希望の光を見出そうとする聖人であります。
そして同時に質素な大工出身で、喉も渇けば腹も減り
時には美しい娼婦(マグダラのマリア)に心動かされ、
「神は答えてくれない・・・。」と失望し、
弟子と信者たちがいつまでたっても無知無能で、本質的なことを理解しないと
一人で苛立つ30代の青年でもある。
これら二つの姿の見事な対比によって、薄っぺらな紙のようだった彼が、
血肉を供えた人物として目の前に鮮やかに立ち現れてくる。
エキサイティングな体験でした。
おそらくこのイエス像は著者であるノーマン・メイラー独自の解釈によるものでしょう。
後書きにもあるように、著者の意図は聖書の解釈でなく、神がかり的才能を持った青年の
光と影を描ききることだったようです。
もうひとつこの本の視点の面白いところは、神とイェシュアとの関係性です。
ここでは神は、全知全能の存在としては描かれていません。
物語の中でイエスは何度も「わが父」と呼びかけるのですが、
息子の切羽詰った心の叫びに<常に>応えるわけでもない。
そのたびイェシュアは自分の無力さを痛感し、言葉と奇跡によって人々を救おうという信念がゆらぐのを感じます。
最終的にゴルゴダの丘の上で磔にされ、苦痛の中で命の炎が消えゆくのを実感しながら、
神は万能ではない。
悪魔との戦いに明け暮れる神は、世界の瑣末まで関っていられないのだと悟る瞬間は
とても暗示的でした。
---------------------------------------------------------------
本を読みながらふとICWRのワン・シーンを思いだしました。
毛布にくるまったShitaoが一人涙を流すところ。
「神(=父)の声が聞こえない。」
もしかしたらそんな絶望感に満ちたシーンだったのかも。
信長―あるいは戴冠せるアンドロギュヌス (新潮文庫)
2011年2月7日 読書
斬新な信長像といえばコレが極めつけな気がします。
歴史小説ではなく、ファンタジー小説なんですけどね。
古代ローマのヘリオガバルスから戦国時代へ、そしてナチス台頭のベルリンへ。
まるでレイダース(一作目)と国盗り物語と帝都物語をミックスしたような
発想の飛躍ですが、それぞれの時代が錯綜しつつも緻密に描かれているので、
最後まで一気に読んでしまいました。
タイトルからわかるように、ここでは信長はアンドロギュヌス(両性具有者)として
描かれています。
少女の美貌と少年の体つきに小さな乳房、生殖器も二つあります。
しかし、面白いことにその異様な描写と今まで数々描かれてきた信長像が、
読み進めるうちに必ずしも乖離してないというか、
これはこれでアリだな、と思ってしまうのです。
(肖像画のイメージも色白で線の細いどっちかというと女性的な容貌ですよね。)
それは置いといて、信長ってある種異邦人といいますか、鬼ッ子といいますか、
周囲から浮きまくっていたことは確かなようです。
慣習を無視し、物事を合理的に考え、古いものをどんどん壊して新たなルールを生み出していく容赦ない革命家でありカリスマ性を備えた、謎めいた存在。
だからこそ、こういう荒唐無稽な設定も可能なのかもしれません。
歴史小説ではなく、ファンタジー小説なんですけどね。
古代ローマのヘリオガバルスから戦国時代へ、そしてナチス台頭のベルリンへ。
まるでレイダース(一作目)と国盗り物語と帝都物語をミックスしたような
発想の飛躍ですが、それぞれの時代が錯綜しつつも緻密に描かれているので、
最後まで一気に読んでしまいました。
タイトルからわかるように、ここでは信長はアンドロギュヌス(両性具有者)として
描かれています。
少女の美貌と少年の体つきに小さな乳房、生殖器も二つあります。
しかし、面白いことにその異様な描写と今まで数々描かれてきた信長像が、
読み進めるうちに必ずしも乖離してないというか、
これはこれでアリだな、と思ってしまうのです。
(肖像画のイメージも色白で線の細いどっちかというと女性的な容貌ですよね。)
それは置いといて、信長ってある種異邦人といいますか、鬼ッ子といいますか、
周囲から浮きまくっていたことは確かなようです。
慣習を無視し、物事を合理的に考え、古いものをどんどん壊して新たなルールを生み出していく容赦ない革命家でありカリスマ性を備えた、謎めいた存在。
だからこそ、こういう荒唐無稽な設定も可能なのかもしれません。
ku:nel (クウネル) 2011年 03月号
2011年2月5日 読書
今回表紙がかっこいいなぁ~・・・と思ったら
平林奈緒美さんのコレクションのひとつ
1930年代の軍用包帯のパッケージだそうで(笑)
『いとしいものは、形をかえて。』
要はリサイクルとかリメイクとかそういう類のことですが、
さすがに切り口が面白い。
そのテのジャンルのキーワードはカワイイになりがちだと思うのですけど
ku:nelのそれは敢てキーワードを探すならアート系←w
何がどうしてアート系なの?とお思いでしょうが・・・それは見てくださいとしか>え?
さて。
表紙の包帯をコレクションしてらっしゃる平林奈緒美さん。
この方は資生堂のアートディレクターとして活躍なさってらっしゃいましたし、
最近ではArts&scienceやJournal Standardのアートワークを手がけてらっしゃるそうで
(ソニア・パークのショッピングマニュアルも平林さんのデザインです)
ご本人もインタビューで語ってらっしゃるように、BAUHAUSやロシア・アバンギャルドが
お好きだったとか
↓
クリエーターズファイル/平林奈緒美
http://biz.toppan.co.jp/gainfo/cf/hirabayashi/p1.html
ku:nelではご自宅のコダワリの内装から小物に至るまで多くの写真が掲載されてまして、その隅々まで美意識の行き届いた世界に思わずため息が漏れたのですが。
中でも目がクギヅケになったのは、アメリカの業者さんに問い合わせて、
そこから輸入できないとわかると、わざわざスリランカの製造元から取寄せたという、
真っ白なタイルのバスルーム。
タイルの白さ、キッチリと並んだ長方形の規則正しいピッチ、備え付けられた真鍮のシャワーや水栓まで、完璧としか言いようがありません。
美学。としか表現しようのないものがそこにある。
以前平林さんはku:nelのおしゃれ特集にも登場されてました。
白いシャツ+(本物の)軍パン、そして黒ブチメガネにこだわりがあって、
気に入ったのを見つけると、なくなる不安から複数購入してしまうとか(笑)
う~ん・・・カッコイイ。
香りにしろ音楽にしろ映画にしろ、いろんなものが好きでちょっと気になると
ついつい手を出してしまう自分は心からの尊敬の念を抱いてしまうのでした。
そうだ。
ku:nelは毎回映画紹介のページもマニアックで面白いんですよ。
(といってもマニアックすぎてこれを参考に見ることはあまりない・笑)
というか、毎回文章を書いてる方の顔ぶれがユニークで読んでるだけで楽しいのですが、
今回はアッバス・キアロスタミ監督のお当番でした。
この方の作品はみたことがないのですが、「オリーブの林を抜けて」は
映画好きの知人が絶賛していたので、一度見てみようかと。
「甘い生活」も大学時代、深夜の映画館で見たけど途中で寝ちゃったので;
これまたほとんど覚えていない・・・。
キアロスタミ監督の紹介がとっても良かったので、見てみようかと思ってます。
平林奈緒美さんのコレクションのひとつ
1930年代の軍用包帯のパッケージだそうで(笑)
『いとしいものは、形をかえて。』
要はリサイクルとかリメイクとかそういう類のことですが、
さすがに切り口が面白い。
そのテのジャンルのキーワードはカワイイになりがちだと思うのですけど
ku:nelのそれは敢てキーワードを探すならアート系←w
何がどうしてアート系なの?とお思いでしょうが・・・それは見てくださいとしか>え?
さて。
表紙の包帯をコレクションしてらっしゃる平林奈緒美さん。
この方は資生堂のアートディレクターとして活躍なさってらっしゃいましたし、
最近ではArts&scienceやJournal Standardのアートワークを手がけてらっしゃるそうで
(ソニア・パークのショッピングマニュアルも平林さんのデザインです)
ご本人もインタビューで語ってらっしゃるように、BAUHAUSやロシア・アバンギャルドが
お好きだったとか
↓
クリエーターズファイル/平林奈緒美
http://biz.toppan.co.jp/gainfo/cf/hirabayashi/p1.html
ku:nelではご自宅のコダワリの内装から小物に至るまで多くの写真が掲載されてまして、その隅々まで美意識の行き届いた世界に思わずため息が漏れたのですが。
中でも目がクギヅケになったのは、アメリカの業者さんに問い合わせて、
そこから輸入できないとわかると、わざわざスリランカの製造元から取寄せたという、
真っ白なタイルのバスルーム。
タイルの白さ、キッチリと並んだ長方形の規則正しいピッチ、備え付けられた真鍮のシャワーや水栓まで、完璧としか言いようがありません。
美学。としか表現しようのないものがそこにある。
以前平林さんはku:nelのおしゃれ特集にも登場されてました。
白いシャツ+(本物の)軍パン、そして黒ブチメガネにこだわりがあって、
気に入ったのを見つけると、なくなる不安から複数購入してしまうとか(笑)
う~ん・・・カッコイイ。
香りにしろ音楽にしろ映画にしろ、いろんなものが好きでちょっと気になると
ついつい手を出してしまう自分は心からの尊敬の念を抱いてしまうのでした。
そうだ。
ku:nelは毎回映画紹介のページもマニアックで面白いんですよ。
(といってもマニアックすぎてこれを参考に見ることはあまりない・笑)
というか、毎回文章を書いてる方の顔ぶれがユニークで読んでるだけで楽しいのですが、
今回はアッバス・キアロスタミ監督のお当番でした。
この方の作品はみたことがないのですが、「オリーブの林を抜けて」は
映画好きの知人が絶賛していたので、一度見てみようかと。
「甘い生活」も大学時代、深夜の映画館で見たけど途中で寝ちゃったので;
これまたほとんど覚えていない・・・。
キアロスタミ監督の紹介がとっても良かったので、見てみようかと思ってます。
ロベール・クートラス作品集『僕の夜 Mes Nuits』(編集・追記しました)
2011年1月15日 読書
リブロ吉祥寺にありました。
小さな本です。
一枚一枚のCARTEも小さなサイズなので
きっとこの大きさがぴったりなのでしょう。
謎めいた筆致、記号のようにも見える文様、暗示的な人物。
聖書の挿絵のようにも、タロットカードのようにも、古代人の壁画のようにも見えます。
言葉にならないメッセージ。
じーっと見ていると、自分の中の洞窟に隠れている何かが見えてくる気がします。
出版社:ecritのHPです。
この日記で興味を持つ方がいらっしゃるかどうかは別としまして(笑)再度掲載。
とても小さな会社のようです。
↓
http://www.e-ecrit.com/press/coutelas/
がんばって頂きたいなぁ。
こういう本が売れる時代じゃないのかもしれないけれど。
こういうものこそネットじゃなく印刷物でゆっくり眺めたいですもん。
小さな本です。
一枚一枚のCARTEも小さなサイズなので
きっとこの大きさがぴったりなのでしょう。
謎めいた筆致、記号のようにも見える文様、暗示的な人物。
聖書の挿絵のようにも、タロットカードのようにも、古代人の壁画のようにも見えます。
言葉にならないメッセージ。
じーっと見ていると、自分の中の洞窟に隠れている何かが見えてくる気がします。
出版社:ecritのHPです。
この日記で興味を持つ方がいらっしゃるかどうかは別としまして(笑)再度掲載。
とても小さな会社のようです。
↓
http://www.e-ecrit.com/press/coutelas/
がんばって頂きたいなぁ。
こういう本が売れる時代じゃないのかもしれないけれど。
こういうものこそネットじゃなく印刷物でゆっくり眺めたいですもん。
暮しの手帖 2010年 10月号 [雑誌]
2011年1月14日 読書 コメント (2)
年末の風邪がやっぱり治らなくて病院へ・・・。
風邪引きだらけで11:30予約したのに診察終了が12:30過ぎ!
疲れました。
が。
待合室で手に取った「暮らしの手帖」と運命の出会いが。←
これ、書店で立読みして買おうかどうか迷ってるうちに
無くなってたんですよ。
1985年に急逝した画家、ロベール・クートラスの特集。
この方は毎夜毎夜小さく切ったダンボールに謎めいた詩的な絵を描き、時には虫食い様の小さな穴をあけアイロンを当て、アンティークのような加工を施し、
気に入ったものだけにニスを塗って作品に仕上げていたそうです。
これらの作品は「CARTE(=カルト)」と呼ばれ、画商にもっと売れる作品を!と依頼されながら彼は全てを断ってカルト作りにのめりこんでいった、と。
それらカルトは、購入した方々の絶妙なセンスで、あるものはチョコレートの箱に納まって小さな宝物のように抽斗に入れられ、あるものはモダンなリビングの壁に端正に飾られ、あるものはテーブルの上にカードのように並べられ、
そのコーディネイトの的確さはそれだけでひとつの作品に見えます。
持ち主と作品とが深く・近しい関係にあるからこそでしょう。
(もちろん暮らしの手帖なので写真の出来も素晴しいのです)
彼の作品は何か・・・キリストのイコン画のような神秘的な雰囲気と、感情の深い部分に訴えかけるような、不思議なインパクトがあります。
それでいてこっち側に自己主張する感じでもなく、いわば画家の自己完結した小さな世界を、こっそり覗き見するような後ろめたいほの暗さも備えていました。
「これは買うしかない!!!!」
帰宅して早速PCを開き密林のページに飛んだ私を待っていたのは
『品切れ』
の無情な文字でありました・・・・・・・・・・。
誰か、持ってたら譲ってください。「暮らしの手帖 48号」←
実はロベール・クートラスの作品集が昨年秋に発売されていたらしく。
『僕の夜 Mes Nuit』
http://www.e-ecrit.com/press/coutelas/
早速購入じゃ!!!
と思ったらコッチも品切れ(つД`)・゜・←遅い!!
でも再版するそうです・・・。
予約しよっと。
風邪引きだらけで11:30予約したのに診察終了が12:30過ぎ!
疲れました。
が。
待合室で手に取った「暮らしの手帖」と運命の出会いが。←
これ、書店で立読みして買おうかどうか迷ってるうちに
無くなってたんですよ。
1985年に急逝した画家、ロベール・クートラスの特集。
この方は毎夜毎夜小さく切ったダンボールに謎めいた詩的な絵を描き、時には虫食い様の小さな穴をあけアイロンを当て、アンティークのような加工を施し、
気に入ったものだけにニスを塗って作品に仕上げていたそうです。
これらの作品は「CARTE(=カルト)」と呼ばれ、画商にもっと売れる作品を!と依頼されながら彼は全てを断ってカルト作りにのめりこんでいった、と。
それらカルトは、購入した方々の絶妙なセンスで、あるものはチョコレートの箱に納まって小さな宝物のように抽斗に入れられ、あるものはモダンなリビングの壁に端正に飾られ、あるものはテーブルの上にカードのように並べられ、
そのコーディネイトの的確さはそれだけでひとつの作品に見えます。
持ち主と作品とが深く・近しい関係にあるからこそでしょう。
(もちろん暮らしの手帖なので写真の出来も素晴しいのです)
彼の作品は何か・・・キリストのイコン画のような神秘的な雰囲気と、感情の深い部分に訴えかけるような、不思議なインパクトがあります。
それでいてこっち側に自己主張する感じでもなく、いわば画家の自己完結した小さな世界を、こっそり覗き見するような後ろめたいほの暗さも備えていました。
「これは買うしかない!!!!」
帰宅して早速PCを開き密林のページに飛んだ私を待っていたのは
『品切れ』
の無情な文字でありました・・・・・・・・・・。
誰か、持ってたら譲ってください。「暮らしの手帖 48号」←
実はロベール・クートラスの作品集が昨年秋に発売されていたらしく。
『僕の夜 Mes Nuit』
http://www.e-ecrit.com/press/coutelas/
早速購入じゃ!!!
と思ったらコッチも品切れ(つД`)・゜・←遅い!!
でも再版するそうです・・・。
予約しよっと。
河童の三平 (ちくま文庫)
2011年1月10日 読書
人間の生きてる意味ってなんだろう?
なぁんてことをちょっとだけ考えてしまった20代に改めて読んで、
もの凄い衝撃を受けた作品です。
小学生に上がる頃既に何度も読んでいたんですけどね。
本作は昭和20~30年代と思しき日本の、超ド田舎に住む三平少年が、
ふとしたはずみから自分に瓜二つの<河童の>三平に出会うところから始まります。
河童の世界に引きずり込まれたり、セコい死神(ねずみ男にそっくりw)に
ストーカーされたり、小人を飼育したり、猫仙人の世界へつれていかれたり。
三平の相棒兼悪友はすれっからし(笑)の子ダヌキ。
田舎の子供ののんびりのどかな日常に、何の違和感もなく侵入してくる
『この世ならぬ世界の住人たち』。
三平と、異形の隣人達のあまりにも日常的なやり取りが面白く、
やがてしんみりした寂しさを運んでくる。
水木しげるは超尊敬する作家さんの一人であります。
これと『悪魔くん千年王国』は今読んでも読後にある種の虚脱感を覚える傑作です。
水木さんのすごさはたくさんあるのですが、そのひとつは『死生観』だと思います。
彼の作品の中で、人はいきなり死ぬ。ころっと死ぬ。
「あっ!?」というまの唐突な死がそこにある。
(『河童の三平』に至っては主人公が途中で死んでしまうのであります)
それを受け止める周囲の人々の反応も、悲しんではいるのですが、
死を死として受け止め『死んでしまったこと』をいつまでも悔やんだりはしない。
こう書くとずいぶん冷酷な感じがしますが、水木作品の中では死者の行くところ
(=死後の世界)は生者の住まいのすぐ隣にある。
次元の裂け目をくぐり抜けるように『あっち側』に行ってしまい、会うことはできない。
それだけ。
この達観した死生観はおそらく、ラバウルで危く戦死しかけた経歴と
切り離して考えることはできないでしょう。
さっきまで親しく家族や故郷の話をしていた人が、目の前で一瞬にして命を落としてゆく。
自らも敵の奇襲で左腕を失い、生死の境を彷徨う。
いわば地獄の釜が開いたその中を、図らずも覗き込む羽目になった人だからこその、
冷徹でそして限りなく優しい生命への目線がある。
とても印象的なシーンがふたつあります。
体の弱い母に代わり三平を育ててくれたお爺さんが死神に連れて行かれた夜。
畳の上で一人淋しくうたたねする三平。
そして次のシーンではいきなり、どこからか上がりこんできた悪戯ものの子ダヌキが
よりそうようにグーグー寝ている。
子ダヌキに腹を立てながらも三平は、完全な孤独からは救われる。
そしてラストシーン。
苦労の多かった三平のお母さんの気持ちを慮って、死んだ三平になりすまし
小学校を卒業した河童の三平。
「せめて、小学校の間だけは(人間の)三平のふりをしていたのです。」と告白する河童に、
「私はずっと前から気付いていました。でも、あなたたちの気持ちが嬉しくて、気付かないふりをしていたの。」
とやさしく語りかける母。
義務を終えた河童は静かに母に手を振り、河童の世界へと帰って行く。
彼を見送るたった一人残された母と、傍らに寄り添うように立つ子ダヌキ。
いつものように山の向こう側へと沈んでいく夕日。
この最後のコマを見終わった時いつも、なんともいえない虚脱感と、
何があっても生きていけそうな不思議な力が湧いてくるのです。
なぁんてことをちょっとだけ考えてしまった20代に改めて読んで、
もの凄い衝撃を受けた作品です。
小学生に上がる頃既に何度も読んでいたんですけどね。
本作は昭和20~30年代と思しき日本の、超ド田舎に住む三平少年が、
ふとしたはずみから自分に瓜二つの<河童の>三平に出会うところから始まります。
河童の世界に引きずり込まれたり、セコい死神(ねずみ男にそっくりw)に
ストーカーされたり、小人を飼育したり、猫仙人の世界へつれていかれたり。
三平の相棒兼悪友はすれっからし(笑)の子ダヌキ。
田舎の子供ののんびりのどかな日常に、何の違和感もなく侵入してくる
『この世ならぬ世界の住人たち』。
三平と、異形の隣人達のあまりにも日常的なやり取りが面白く、
やがてしんみりした寂しさを運んでくる。
水木しげるは超尊敬する作家さんの一人であります。
これと『悪魔くん千年王国』は今読んでも読後にある種の虚脱感を覚える傑作です。
水木さんのすごさはたくさんあるのですが、そのひとつは『死生観』だと思います。
彼の作品の中で、人はいきなり死ぬ。ころっと死ぬ。
「あっ!?」というまの唐突な死がそこにある。
(『河童の三平』に至っては主人公が途中で死んでしまうのであります)
それを受け止める周囲の人々の反応も、悲しんではいるのですが、
死を死として受け止め『死んでしまったこと』をいつまでも悔やんだりはしない。
こう書くとずいぶん冷酷な感じがしますが、水木作品の中では死者の行くところ
(=死後の世界)は生者の住まいのすぐ隣にある。
次元の裂け目をくぐり抜けるように『あっち側』に行ってしまい、会うことはできない。
それだけ。
この達観した死生観はおそらく、ラバウルで危く戦死しかけた経歴と
切り離して考えることはできないでしょう。
さっきまで親しく家族や故郷の話をしていた人が、目の前で一瞬にして命を落としてゆく。
自らも敵の奇襲で左腕を失い、生死の境を彷徨う。
いわば地獄の釜が開いたその中を、図らずも覗き込む羽目になった人だからこその、
冷徹でそして限りなく優しい生命への目線がある。
とても印象的なシーンがふたつあります。
体の弱い母に代わり三平を育ててくれたお爺さんが死神に連れて行かれた夜。
畳の上で一人淋しくうたたねする三平。
そして次のシーンではいきなり、どこからか上がりこんできた悪戯ものの子ダヌキが
よりそうようにグーグー寝ている。
子ダヌキに腹を立てながらも三平は、完全な孤独からは救われる。
そしてラストシーン。
苦労の多かった三平のお母さんの気持ちを慮って、死んだ三平になりすまし
小学校を卒業した河童の三平。
「せめて、小学校の間だけは(人間の)三平のふりをしていたのです。」と告白する河童に、
「私はずっと前から気付いていました。でも、あなたたちの気持ちが嬉しくて、気付かないふりをしていたの。」
とやさしく語りかける母。
義務を終えた河童は静かに母に手を振り、河童の世界へと帰って行く。
彼を見送るたった一人残された母と、傍らに寄り添うように立つ子ダヌキ。
いつものように山の向こう側へと沈んでいく夕日。
この最後のコマを見終わった時いつも、なんともいえない虚脱感と、
何があっても生きていけそうな不思議な力が湧いてくるのです。
derek jarman’s garden(編集・追記しました)
2011年1月8日 読書 コメント (4)
美しいものとは何か。
例えば自然の美しさ。
何の作為もなくただそこにあるだけで美しい。
しかしヒトがある作為を持って作り出した風景に
心を奪われることもあります。
Derek Jarmanは1994年にAIDSで亡くなった映像作家です。
作品は同性愛者である彼のパーソナリティと深く関わっており、
切り離して語ることはできません。
一方で晩年、イングランドのダンジェネスという海岸沿いの荒れ地に
少しずつ手を加え、庭(=Garden)を作り上げたことでも有名です。
イギリス人の園芸熱は有名ですが、彼の庭は一風変わった作りです。
基本、植物は地のもの(海岸沿いの荒地で生育できる植物は限られていました)
庭作りのセオリーとは異なる独自の美意識で選び抜かれたオブジェの数々。
遠いどこからか波に乗って・あるいは何らかの理由で打ち捨てられた木、
漁師の道具、農具。
小屋はProspect Cottage(展望の小屋)と名づけられ、黒く塗られ、それらと野性の草花を
映像作家らしいセンスで配し、根気強く手を加え、見事に個性的な庭が完成しました。
この本には庭のディテール写真が数多く収められ、アザミやケシなどの野性の草花たちの
素朴な美しさ・・・ひっそりとはびこる苔の緑・・・赤さびた金属のオブジェ、
波と風に削られ丸くなった骨のような小石、
それら全ての織り成す力強さに圧倒されます。
また、ページごとに彼の短い文章が添えられており、
その繊細で鋭い観察眼や独特のユーモアは読む者の感受性を刺激します。
AIDSに刻一刻と肉体を蝕まれながら、彼を強く支えていたもののひとつが
この庭作りへの情熱であったこと。
だからこそ、彼のGardenは見るものの目を釘付けにし、そのむき出しの美しさは
心に漣を立てずにはいられません。
写真3枚目の遠景に映る不気味な施設。
ダンジェネスの原子力発電所。
彼は敢てこの場所を選んだそうです。
自然のあるがままの素朴な生命力と反骨精神旺盛な映像作家の作為。
正反対に見える二つが奇跡のように出会った、荒涼たる風景の中の天国の美。
いつかは訪れてみたい場所です・・・。
例えば自然の美しさ。
何の作為もなくただそこにあるだけで美しい。
しかしヒトがある作為を持って作り出した風景に
心を奪われることもあります。
Derek Jarmanは1994年にAIDSで亡くなった映像作家です。
作品は同性愛者である彼のパーソナリティと深く関わっており、
切り離して語ることはできません。
一方で晩年、イングランドのダンジェネスという海岸沿いの荒れ地に
少しずつ手を加え、庭(=Garden)を作り上げたことでも有名です。
イギリス人の園芸熱は有名ですが、彼の庭は一風変わった作りです。
基本、植物は地のもの(海岸沿いの荒地で生育できる植物は限られていました)
庭作りのセオリーとは異なる独自の美意識で選び抜かれたオブジェの数々。
遠いどこからか波に乗って・あるいは何らかの理由で打ち捨てられた木、
漁師の道具、農具。
小屋はProspect Cottage(展望の小屋)と名づけられ、黒く塗られ、それらと野性の草花を
映像作家らしいセンスで配し、根気強く手を加え、見事に個性的な庭が完成しました。
この本には庭のディテール写真が数多く収められ、アザミやケシなどの野性の草花たちの
素朴な美しさ・・・ひっそりとはびこる苔の緑・・・赤さびた金属のオブジェ、
波と風に削られ丸くなった骨のような小石、
それら全ての織り成す力強さに圧倒されます。
また、ページごとに彼の短い文章が添えられており、
その繊細で鋭い観察眼や独特のユーモアは読む者の感受性を刺激します。
AIDSに刻一刻と肉体を蝕まれながら、彼を強く支えていたもののひとつが
この庭作りへの情熱であったこと。
だからこそ、彼のGardenは見るものの目を釘付けにし、そのむき出しの美しさは
心に漣を立てずにはいられません。
写真3枚目の遠景に映る不気味な施設。
ダンジェネスの原子力発電所。
彼は敢てこの場所を選んだそうです。
自然のあるがままの素朴な生命力と反骨精神旺盛な映像作家の作為。
正反対に見える二つが奇跡のように出会った、荒涼たる風景の中の天国の美。
いつかは訪れてみたい場所です・・・。
暮しの手帖 2010年 12月号 [雑誌]
2010年12月14日 読書 コメント (2)
写真が毎回端正で美しい。
紙の質感や柔かい白さも好き。
今回は「おそうざいふう外国料理」「ワンボウルケーキ」。
洗いざらしの真っ白なクロスの上に置かれた料理のお皿は
うっとりするほど美味しそう。
とりわけP.18の豚肉のカツレツ。
もの凄くキメ細かい衣を着けてサックリと程よく揚がったカツレツに
グリーンのレタスとクレソン、黄色い櫛切りのレモン。
こんな美形なカツレツ、作れるわけないのですが、見てるだけで幸せ。
中表紙の松浦弥太郎氏撮影のクリスマスっぽい赤いアレンジメントも素敵です。
美味しいものと美しいものは心と体を幸せにする。
・・・と思いませんか?
紙の質感や柔かい白さも好き。
今回は「おそうざいふう外国料理」「ワンボウルケーキ」。
洗いざらしの真っ白なクロスの上に置かれた料理のお皿は
うっとりするほど美味しそう。
とりわけP.18の豚肉のカツレツ。
もの凄くキメ細かい衣を着けてサックリと程よく揚がったカツレツに
グリーンのレタスとクレソン、黄色い櫛切りのレモン。
こんな美形なカツレツ、作れるわけないのですが、見てるだけで幸せ。
中表紙の松浦弥太郎氏撮影のクリスマスっぽい赤いアレンジメントも素敵です。
美味しいものと美しいものは心と体を幸せにする。
・・・と思いませんか?
きのう何食べた?(4) (モーニングKC)
2010年11月20日 読書
毎回友だちに借りて読んでます・・・スミマセン。
美容師と弁護士の中年ゲイカップル。
楽天的で素直でほんわかした美容師さん(ヒゲ系w)と
いい男で生まじめで趣味が倹約と料理のやり手弁護士さん。
ふたりのナニゲな~い日常のやり取りと
ふたりをとりまく人たちとの日々の出来事を淡々と描いている。
弁護士の彼が作るごく日常的だけどツボを押さえた節約料理の数々。
料理の解説がやや饒舌に感じるときもありますが、や、イイオトコが料理してる姿が
いかに魅力的であるかは、よーーーーくわかってるつもりですけど(笑)
マンガで見てもいいもんですね~w
・・・たとえ彼がゲイであっても。
今日私はふと明日の朝のトーストに塗るジャムもはちみつも切れてることに気付いた。
「あ~・・・めんどくさ。買いに行くか~(´д`;)」
と、重い腰をあげようとしたその時。
昨夜読んだこれに出てきた「りんごのキャラメル煮」を思い出した。
冷蔵庫にはちゃんとりんごがある。そしてお砂糖。
さっそく作ってみました。
単純に焦がしたお砂糖のカラメルの中に、くし形に切ったりんごを皮ごと入れて
煮詰めるだけなんですけど(笑)
ウマイ!簡単っ!
さっそく明日の朝はバタートーストにりんごのキャラメル煮をのっけて、
ストックしてあるバニラアイスと一緒に食べるんだ♪
美味しい、は人を少し幸せにしますね。
美容師と弁護士の中年ゲイカップル。
楽天的で素直でほんわかした美容師さん(ヒゲ系w)と
いい男で生まじめで趣味が倹約と料理のやり手弁護士さん。
ふたりのナニゲな~い日常のやり取りと
ふたりをとりまく人たちとの日々の出来事を淡々と描いている。
弁護士の彼が作るごく日常的だけどツボを押さえた節約料理の数々。
料理の解説がやや饒舌に感じるときもありますが、や、イイオトコが料理してる姿が
いかに魅力的であるかは、よーーーーくわかってるつもりですけど(笑)
マンガで見てもいいもんですね~w
・・・たとえ彼がゲイであっても。
今日私はふと明日の朝のトーストに塗るジャムもはちみつも切れてることに気付いた。
「あ~・・・めんどくさ。買いに行くか~(´д`;)」
と、重い腰をあげようとしたその時。
昨夜読んだこれに出てきた「りんごのキャラメル煮」を思い出した。
冷蔵庫にはちゃんとりんごがある。そしてお砂糖。
さっそく作ってみました。
単純に焦がしたお砂糖のカラメルの中に、くし形に切ったりんごを皮ごと入れて
煮詰めるだけなんですけど(笑)
ウマイ!簡単っ!
さっそく明日の朝はバタートーストにりんごのキャラメル煮をのっけて、
ストックしてあるバニラアイスと一緒に食べるんだ♪
美味しい、は人を少し幸せにしますね。
ごく幼少の頃<アラジンと魔法のランプ>が大好きだった。
自分で本を読むようになっても人魚姫や白雪姫より
アラビアの王様やお姫さま、
ジンニー(魔神)やジンニーア(女魔神)の出てくる物語のほうが
ずっと楽しいと思っていた。
中学生になって絵本ではない「千一夜物語」を図書館で読んで
完全にぶっ飛んだ。
・・・なんてエロティックで自由な世界のお話なんだろう。
アンデルセンもイソップも面白いけど、なんとなく暗くて読後感が良くなかったりする。
その点、千一夜物語はどこまでも官能的で享楽的でファンタジックで、
そして大らかなのである。
話の発端からしてすごい。
美人のお妃に裏切られて女性不信になった王様が、
毎晩美しい処女を召しだして一晩を共にし、
朝には処刑するという無茶苦茶なことをやっていた。
当然、若くてきれいな女の子がどんどん減っていく。国家存亡の危機だ。
事態を憂慮した大臣の娘・シェへラザード(この本ではシャハラザード)は一計を案じ、
王様が続きを聞かずには居られないような面白い物語を毎晩語って聞かせ、
王様は続きが知りたいばかりに彼女を処刑せず、翌晩の寝物語の続きを心待ちにする。
・・・ここから始まる物語なのだから、色っぽくて当然である。
イスラム世界の話なのでアッラーの名が随所に出てくる。
しかしイスラム世界に対して私たちが抱きがちであるだろうイメージ・・・
厳格な戒律でコントロールされた男尊女卑や禁欲的なイメージは、
ここでは見事に裏切られる。
(<排他的なイスラム教徒>の姿は’80年代以降急速に広まったイスラム原理主義的教えに乗っ取ったものである)
恋に色事に自由奔放で、女は控えめに見えて賢く逞しく、
男はいつも女のはかりごとにうまいこと丸め込まれてしまう。
美男美女がやたらに出てくる。
しかもその美貌の描写の大げさなこと、少女漫画以上である。
ところどころに挿入されるアッラーとその作りたまいし世界を讃える詩は、
刹那的で耽美的でさえある。
何より、金銀宝石と薔薇と麝香と竜涎香(=アンバー)と、
その他夥しい香料の香り漂う世界は想像するだけでうっとりしてしまう。
・・・たぶん訳本が優れているからだと思いますが。
というわけで、最近の私は苦痛以外のなにものでもない通勤時間を、
目も眩むような美男美女と目くるめく魔法と財宝、
そして浮世の諸々を忘却の彼方へ運び去る、
エキゾティックな香料の幻覚とともにやり過ごしているのです。
(全13巻)
自分で本を読むようになっても人魚姫や白雪姫より
アラビアの王様やお姫さま、
ジンニー(魔神)やジンニーア(女魔神)の出てくる物語のほうが
ずっと楽しいと思っていた。
中学生になって絵本ではない「千一夜物語」を図書館で読んで
完全にぶっ飛んだ。
・・・なんてエロティックで自由な世界のお話なんだろう。
アンデルセンもイソップも面白いけど、なんとなく暗くて読後感が良くなかったりする。
その点、千一夜物語はどこまでも官能的で享楽的でファンタジックで、
そして大らかなのである。
話の発端からしてすごい。
美人のお妃に裏切られて女性不信になった王様が、
毎晩美しい処女を召しだして一晩を共にし、
朝には処刑するという無茶苦茶なことをやっていた。
当然、若くてきれいな女の子がどんどん減っていく。国家存亡の危機だ。
事態を憂慮した大臣の娘・シェへラザード(この本ではシャハラザード)は一計を案じ、
王様が続きを聞かずには居られないような面白い物語を毎晩語って聞かせ、
王様は続きが知りたいばかりに彼女を処刑せず、翌晩の寝物語の続きを心待ちにする。
・・・ここから始まる物語なのだから、色っぽくて当然である。
イスラム世界の話なのでアッラーの名が随所に出てくる。
しかしイスラム世界に対して私たちが抱きがちであるだろうイメージ・・・
厳格な戒律でコントロールされた男尊女卑や禁欲的なイメージは、
ここでは見事に裏切られる。
(<排他的なイスラム教徒>の姿は’80年代以降急速に広まったイスラム原理主義的教えに乗っ取ったものである)
恋に色事に自由奔放で、女は控えめに見えて賢く逞しく、
男はいつも女のはかりごとにうまいこと丸め込まれてしまう。
美男美女がやたらに出てくる。
しかもその美貌の描写の大げさなこと、少女漫画以上である。
ところどころに挿入されるアッラーとその作りたまいし世界を讃える詩は、
刹那的で耽美的でさえある。
何より、金銀宝石と薔薇と麝香と竜涎香(=アンバー)と、
その他夥しい香料の香り漂う世界は想像するだけでうっとりしてしまう。
・・・たぶん訳本が優れているからだと思いますが。
というわけで、最近の私は苦痛以外のなにものでもない通勤時間を、
目も眩むような美男美女と目くるめく魔法と財宝、
そして浮世の諸々を忘却の彼方へ運び去る、
エキゾティックな香料の幻覚とともにやり過ごしているのです。
(全13巻)
ku:nel (クウネル) 2010年 11月号 [雑誌]
2010年9月18日 読書 コメント (4)
表紙を見た瞬間「買い!」だと思いました(笑)
ボタン好きなんですよ。アンティークのやつとか特に好き。
昔、代官山や青山の古着屋さんでもボタン売ってたんですよね。
宝探しみたいに漁って、イヤリングやリングを作ってました。
パリでお約束の如くwフレアマーケットに行って、
薄いグリーンのソーダ水みたいなすりガラスのボタンを
一そろい買いました。
一目ぼれして買ったんですが、あまりにも繊細で綺麗すぎて
使いみちがなく箪笥の肥やしです・・・。
他にも古道具屋さんで見つけた目の覚めるようなブルーと吸い込まれそうな藍色の、
表面に細かい細工のある小さなボタンを4つ、大事にしまってあります。
お店のご主人が「たぶん人形の目か何かに使ったんじゃないでしょうか。」
と仰ってました。
さて。
さすがKU:NEL。中身も裏切りません。
おしゃれといっても所謂トレンドのカタログではないのです。
ディテールに拘りのあるおしゃれさん(笑)が続々と。
カシミアの肌触りの虜になった人、古い服だけがもつ味わいに中毒してる人、
もう様々な・・・いわばおしゃれ=ヲタクな方々ばかりで。
読み応えがありました。
中でも刺繍作家さんのお話・・・母から娘、孫娘へと脈々と受け継がれる布と服への愛着。
たかがおしゃれ。されどおしゃれ。
そこには人間の歴史が確かに存在しているのだなぁ、と。
昨日のわっつでも思ったのですが、どうやら私は拘りのある人々の
お話を聞くのが好きらしい。
ものをめぐるストーリーが、それを愛する人々によって、血の通った存在になったと、
そう感じるとき、なんともいえず幸せなのです。
(や、単純にモエてるだけかもw)
映画監督さんが語る岸田今日子さんのお話も凄い。
砂の女は、いつか必ず見てみようと思ったのでした。
オススメの一冊です!
拘りのおしゃれ好き(笑)なら、買って損はなし。
ボタン好きなんですよ。アンティークのやつとか特に好き。
昔、代官山や青山の古着屋さんでもボタン売ってたんですよね。
宝探しみたいに漁って、イヤリングやリングを作ってました。
パリでお約束の如くwフレアマーケットに行って、
薄いグリーンのソーダ水みたいなすりガラスのボタンを
一そろい買いました。
一目ぼれして買ったんですが、あまりにも繊細で綺麗すぎて
使いみちがなく箪笥の肥やしです・・・。
他にも古道具屋さんで見つけた目の覚めるようなブルーと吸い込まれそうな藍色の、
表面に細かい細工のある小さなボタンを4つ、大事にしまってあります。
お店のご主人が「たぶん人形の目か何かに使ったんじゃないでしょうか。」
と仰ってました。
さて。
さすがKU:NEL。中身も裏切りません。
おしゃれといっても所謂トレンドのカタログではないのです。
ディテールに拘りのあるおしゃれさん(笑)が続々と。
カシミアの肌触りの虜になった人、古い服だけがもつ味わいに中毒してる人、
もう様々な・・・いわばおしゃれ=ヲタクな方々ばかりで。
読み応えがありました。
中でも刺繍作家さんのお話・・・母から娘、孫娘へと脈々と受け継がれる布と服への愛着。
たかがおしゃれ。されどおしゃれ。
そこには人間の歴史が確かに存在しているのだなぁ、と。
昨日のわっつでも思ったのですが、どうやら私は拘りのある人々の
お話を聞くのが好きらしい。
ものをめぐるストーリーが、それを愛する人々によって、血の通った存在になったと、
そう感じるとき、なんともいえず幸せなのです。
(や、単純にモエてるだけかもw)
映画監督さんが語る岸田今日子さんのお話も凄い。
砂の女は、いつか必ず見てみようと思ったのでした。
オススメの一冊です!
拘りのおしゃれ好き(笑)なら、買って損はなし。
MORSE―モールス (ハヤカワ文庫NV)
2010年8月14日 読書
「ぼくのエリ 200歳の少女」の原作です。
先に映画を見てから、これは絶対原作も読まねば!といそいそと購入。
面白いですよ、これ。
永遠に年を取らず、人の生き血を飲まずにはいられない。
太陽に照らされると燃え尽きて灰になる。
ヴァンパイア小説の定番の設定を生かしつつ、
望まぬまま異形の者と化してしまった悲しみと
思春期にさしかかったコドモのゆれ動く内面を繊細に汲み取りシンクロさせ、
疎外された子供たちの惨めな救いようのなさ、無関心で身勝手な大人たちへの絶望感を
静かに降り積もりながら凍りつく北欧の長い冬の閉塞感でつつみこんだ上手さ。
その部分は映画も小説もぴったり同じでした。
ただ小説のほうはよりホラー的色合いが濃くて、描写の過剰な残酷・悲惨さは、
どっちかっていうとB級ホラー作品風味(笑)
忠実に映像化するなら、たぶんハリウッドのほうが得意そう。
(ただし性的タブーに触れる描写もあるので、そこんとこはスルーだろうな)
・・・実際ハリウッドが映画化して、今秋に全米公開されるそうです。
ニューメキシコでロケしたとか。
映画的には全くテイストの違う作品に仕上がってるかもしれないですね。
映像でどんな空気を表現するのか。
小説と同じ設定、同じエピソードを遣いながら、全体の流れをどう組み立てていくか。
小説の物語的骨格がしっかりしているからこその大胆な改編ともいえますし、
映像と文章という媒体の決定的違いも大きいでしょう。
ただあくまで個人的な感想ですが、映画ではオスカルとエリの繊細さやナイーブさが、
御伽話の妖精譚のような味わいを添え、作品を陳腐化からずっと遠ざけていたと思う。
映像作品としての出来の素晴しさを再確認した感もあり。
*************************************
先日コメント頂いたモザイク描写とタイトルの欺瞞性について。
原作を読んで思ったこと。
・・・そこのところはたぶん、「小さな恋のメロディ」的に売り出したかったんだろうな、
日本の配給元は。
先に映画を見てから、これは絶対原作も読まねば!といそいそと購入。
面白いですよ、これ。
永遠に年を取らず、人の生き血を飲まずにはいられない。
太陽に照らされると燃え尽きて灰になる。
ヴァンパイア小説の定番の設定を生かしつつ、
望まぬまま異形の者と化してしまった悲しみと
思春期にさしかかったコドモのゆれ動く内面を繊細に汲み取りシンクロさせ、
疎外された子供たちの惨めな救いようのなさ、無関心で身勝手な大人たちへの絶望感を
静かに降り積もりながら凍りつく北欧の長い冬の閉塞感でつつみこんだ上手さ。
その部分は映画も小説もぴったり同じでした。
ただ小説のほうはよりホラー的色合いが濃くて、描写の過剰な残酷・悲惨さは、
どっちかっていうとB級ホラー作品風味(笑)
忠実に映像化するなら、たぶんハリウッドのほうが得意そう。
(ただし性的タブーに触れる描写もあるので、そこんとこはスルーだろうな)
・・・実際ハリウッドが映画化して、今秋に全米公開されるそうです。
ニューメキシコでロケしたとか。
映画的には全くテイストの違う作品に仕上がってるかもしれないですね。
映像でどんな空気を表現するのか。
小説と同じ設定、同じエピソードを遣いながら、全体の流れをどう組み立てていくか。
小説の物語的骨格がしっかりしているからこその大胆な改編ともいえますし、
映像と文章という媒体の決定的違いも大きいでしょう。
ただあくまで個人的な感想ですが、映画ではオスカルとエリの繊細さやナイーブさが、
御伽話の妖精譚のような味わいを添え、作品を陳腐化からずっと遠ざけていたと思う。
映像作品としての出来の素晴しさを再確認した感もあり。
*************************************
先日コメント頂いたモザイク描写とタイトルの欺瞞性について。
原作を読んで思ったこと。
・・・そこのところはたぶん、「小さな恋のメロディ」的に売り出したかったんだろうな、
日本の配給元は。
実家のPCがネットに接続できない!
ワイヤレス接続なので、ケーブルもないし・・・
原因を突き止めるのに一苦労・・・。
ワイヤレスLAN接続が切断されていたのでした。
ようやく復活して日記をUP。
ケータイから日記UPすれば?ってコトですが。
Dairy NoteはWILLCOMではユーザー登録できないんです;
WILLCOM使いに冷たい・・・。
*************************************
最近ケルト民話や江戸時代の怪談にハマってまして、
図書館でそのテの書架を物色してるときふと目にとまったこの本。
レヴィ-ストロースはフランスの社会人類学者・思想家です。
名前は知ってますし、なんとなく興味はあったのですが、
でもこういう分野ってなんか手を出しにくいですよね(笑)
この方の思想・研究は複雑かつ多岐にわたっていて、きちんと理解するには
相当な時間と理解力が必要なようですので、一番印象に残った部分をかいつまんで。
レヴィ-ストロースは新大陸の先住民の風俗・習慣、民話(=神話)を収集し、
互いに比較・関連つけることで、それらを構成する核の部分に共通項がある点に注目し、
未開人と呼ばれる人々に共通の思考方法があると結論付け、「野生の思考」と命名しました。
私たちは教育を受けることで抽象的な概念から<知ること><理解すること>を始めますが、
未開人と呼ばれる人々は人間・動物・あらゆる自然現象など
具体的に見た・感じたものを分類し再構築することによって
世界を<知り><理解する>のだそうです。
レヴィ-ストロースの思考はそこから更に発展して、芸術や音楽とは何か?言葉とは?
・・・という分野にまで広がっていき、同時代の思想家や心理学者など
さまざまな分野の人々に影響を与え続けているそうです。
現代人である私たちは主に抽象化された世界に生きているといえるのではないかと。
自然のダイナミズムや生々しい人間の生の営みを実感することって確実に減っている。
それ故<体験から直感的に世界を知ること>の価値(=意味)を忘れがちですが、
『野生の思考』は、芸術家と呼ばれる人々の創作にかかわる部分、感覚と直感によって
世界の姿を明らかにしていこうとする方法論に生き続けており、
決して現代人の思考方法と全くの無縁ではない、という考え方はとても刺激的でした。
(そして思わず彼のことを連想してしまう自分は相当なビョーキですネ;)
まぁこうして日記wなんか書いてる理由は、日常の出来事を整理し、
自分なりに意味づけしたいという欲求があるからに他ならないわけで。
この本は「物事をどう見るか・どう理解するか」についてのヒントを
提示しているような気がしました。
<思想>の本なんて日頃読まないし、とっつきにくいじゃないですか?
この本は文章だけでなく豊富なイラスト付きなので、私でも概要がつかみやすく、
ゆっくり時間をかけ、理解しながら読み進めることができました。
ワイヤレス接続なので、ケーブルもないし・・・
原因を突き止めるのに一苦労・・・。
ワイヤレスLAN接続が切断されていたのでした。
ようやく復活して日記をUP。
ケータイから日記UPすれば?ってコトですが。
Dairy NoteはWILLCOMではユーザー登録できないんです;
WILLCOM使いに冷たい・・・。
*************************************
最近ケルト民話や江戸時代の怪談にハマってまして、
図書館でそのテの書架を物色してるときふと目にとまったこの本。
レヴィ-ストロースはフランスの社会人類学者・思想家です。
名前は知ってますし、なんとなく興味はあったのですが、
でもこういう分野ってなんか手を出しにくいですよね(笑)
この方の思想・研究は複雑かつ多岐にわたっていて、きちんと理解するには
相当な時間と理解力が必要なようですので、一番印象に残った部分をかいつまんで。
レヴィ-ストロースは新大陸の先住民の風俗・習慣、民話(=神話)を収集し、
互いに比較・関連つけることで、それらを構成する核の部分に共通項がある点に注目し、
未開人と呼ばれる人々に共通の思考方法があると結論付け、「野生の思考」と命名しました。
私たちは教育を受けることで抽象的な概念から<知ること><理解すること>を始めますが、
未開人と呼ばれる人々は人間・動物・あらゆる自然現象など
具体的に見た・感じたものを分類し再構築することによって
世界を<知り><理解する>のだそうです。
レヴィ-ストロースの思考はそこから更に発展して、芸術や音楽とは何か?言葉とは?
・・・という分野にまで広がっていき、同時代の思想家や心理学者など
さまざまな分野の人々に影響を与え続けているそうです。
現代人である私たちは主に抽象化された世界に生きているといえるのではないかと。
自然のダイナミズムや生々しい人間の生の営みを実感することって確実に減っている。
それ故<体験から直感的に世界を知ること>の価値(=意味)を忘れがちですが、
『野生の思考』は、芸術家と呼ばれる人々の創作にかかわる部分、感覚と直感によって
世界の姿を明らかにしていこうとする方法論に生き続けており、
決して現代人の思考方法と全くの無縁ではない、という考え方はとても刺激的でした。
(そして思わず彼のことを連想してしまう自分は相当なビョーキですネ;)
まぁこうして日記wなんか書いてる理由は、日常の出来事を整理し、
自分なりに意味づけしたいという欲求があるからに他ならないわけで。
この本は「物事をどう見るか・どう理解するか」についてのヒントを
提示しているような気がしました。
<思想>の本なんて日頃読まないし、とっつきにくいじゃないですか?
この本は文章だけでなく豊富なイラスト付きなので、私でも概要がつかみやすく、
ゆっくり時間をかけ、理解しながら読み進めることができました。