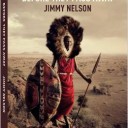中国の空は広い。
大地は遥かかなた、一直線に空との境目へと続く。
埃っぽい赤茶色の大地に背の低い草原がどこまでも広がり、
立ち尽くし眺めていると軽く目眩を覚える。
ふと目を凝らすと遠く米粒大に動くものがある。
だんだん近づいてくるとそれは人と羊と馬。
モンゴルの遊牧民、陽に焼けたなめし革のような肌、
人懐こい笑顔。
広い大地を縦断する列車へ乗り込む。
薄暗い車内。
ポツポツと埋まった席で物思いに耽る人、低い話声、時々笑い声が混じる。
質素な藍染のブラウスを着た老婦人が新聞に目を凝らしている。
所在無げに煙草を吸う男。
手編みの毛糸の帽子を被った赤ちゃんを抱っこした若い母親。
ところどころ錆びた手洗い場。
デッキには麻袋に詰め込まれ観念したような鶏たち。
列車は単調なリズムを休みなく刻み、揚子江を超え、灰色の空の下に張り付くように
ひっそりと家々が点在する風景を抜けていく。
スモッグの中に唐突に未来的な高層建築のシルエットが浮かび上がってくる。
北京。
天安門で記念写真。
紫禁城のすぐそばをゆったりと川が流れ、対岸は煤けた家並が続く。
公園では静かに太極拳をする年寄や麻雀に興じる男たち、幸せそうな家族。
南下して蘇州。
「蘇州夜曲」のメロディのように柔らかな緑と古き良き時代の面影の残る街並。
漆喰壁の家、食堂の裏庭まであふれる湯気、公道でのんびり髪を切る青空床屋。
次は上海の朱家角。
水路が張り巡らされた街のそこここに古い石の橋が掛かっている。
のんびりと小舟が行き交い、恋人たちが寄り添い川を眺めている。
家並みはまさに「古き良き時代の中国」の風情を醸し出し、最後の王朝の時代から
時が止まってしまったような錯覚を覚える。
写真家の上田義彦氏が1980年代後半から2011年まで度々訪れた中国。
装丁からも察せられるように、これはとてもノスタルジックで端正な本です。
父の書棚を整理していたら奥のほうに仕舞い込まれていたアルバム。
そこから見つけ出したような空気を纏っている。
うっすらブルーグレイのフィルターを通したような、記憶の靄から現れるような。
眺めているといつの間にか私の目は上田氏のそれと同化し、
私の記憶がその記憶とすり替わったような不思議な錯覚を覚える。
そしてたぶん、こんな風景はもう地上のどこにもないのかもしれないという、
根拠もないのに確信に似た直感に胸が締め付けられる。
そんな写真集です。
大地は遥かかなた、一直線に空との境目へと続く。
埃っぽい赤茶色の大地に背の低い草原がどこまでも広がり、
立ち尽くし眺めていると軽く目眩を覚える。
ふと目を凝らすと遠く米粒大に動くものがある。
だんだん近づいてくるとそれは人と羊と馬。
モンゴルの遊牧民、陽に焼けたなめし革のような肌、
人懐こい笑顔。
広い大地を縦断する列車へ乗り込む。
薄暗い車内。
ポツポツと埋まった席で物思いに耽る人、低い話声、時々笑い声が混じる。
質素な藍染のブラウスを着た老婦人が新聞に目を凝らしている。
所在無げに煙草を吸う男。
手編みの毛糸の帽子を被った赤ちゃんを抱っこした若い母親。
ところどころ錆びた手洗い場。
デッキには麻袋に詰め込まれ観念したような鶏たち。
列車は単調なリズムを休みなく刻み、揚子江を超え、灰色の空の下に張り付くように
ひっそりと家々が点在する風景を抜けていく。
スモッグの中に唐突に未来的な高層建築のシルエットが浮かび上がってくる。
北京。
天安門で記念写真。
紫禁城のすぐそばをゆったりと川が流れ、対岸は煤けた家並が続く。
公園では静かに太極拳をする年寄や麻雀に興じる男たち、幸せそうな家族。
南下して蘇州。
「蘇州夜曲」のメロディのように柔らかな緑と古き良き時代の面影の残る街並。
漆喰壁の家、食堂の裏庭まであふれる湯気、公道でのんびり髪を切る青空床屋。
次は上海の朱家角。
水路が張り巡らされた街のそこここに古い石の橋が掛かっている。
のんびりと小舟が行き交い、恋人たちが寄り添い川を眺めている。
家並みはまさに「古き良き時代の中国」の風情を醸し出し、最後の王朝の時代から
時が止まってしまったような錯覚を覚える。
写真家の上田義彦氏が1980年代後半から2011年まで度々訪れた中国。
装丁からも察せられるように、これはとてもノスタルジックで端正な本です。
父の書棚を整理していたら奥のほうに仕舞い込まれていたアルバム。
そこから見つけ出したような空気を纏っている。
うっすらブルーグレイのフィルターを通したような、記憶の靄から現れるような。
眺めているといつの間にか私の目は上田氏のそれと同化し、
私の記憶がその記憶とすり替わったような不思議な錯覚を覚える。
そしてたぶん、こんな風景はもう地上のどこにもないのかもしれないという、
根拠もないのに確信に似た直感に胸が締め付けられる。
そんな写真集です。
眠狂四郎無頼控 (1) (新潮文庫)
2015年6月16日 読書
円月殺法の使い手にして凄腕の剣客、眠狂四郎。
ころび伴天連(改宗させられた宣教師)と上臈との不義の子。
つまり、ハーフ。
長身痩躯に日本人離れした彫りの深い顔、白い肌、茶色い髪。
虚無感を纏い、自らの身を顧みない。
気に入った女は容赦なく抱く。
彼をひたすら愛する美しく薄幸の女、美保代。
薄暗い世界で微かに灯るか細い炎のような。
父の書棚で発見して中学生の頃ドキドキしながら読みました。
エロスの香りが濃厚に漂う、ハードボイルド時代小説。
いつかこの狂四郎をキムラに演じて欲しいなぁとずっと思ってます。
ほら、外見なんてピッタリじゃないですか?彫が深いし髪も茶色いし。
そして…日本人離れした白い肌。
日焼け厳禁ですから、眠狂四郎は(笑)
昔、片岡孝夫版を見た覚えがありますが…田村正和もやってたんですね。
(wikiで確認)
テレビだとエロス薄めになっちゃうので、是非映画で。
美保代役、誰がいいだろう…とぴたっとハマる女優さん、見つかりました。
上戸彩。
彼女以外、あり得ません。
ころび伴天連(改宗させられた宣教師)と上臈との不義の子。
つまり、ハーフ。
長身痩躯に日本人離れした彫りの深い顔、白い肌、茶色い髪。
虚無感を纏い、自らの身を顧みない。
気に入った女は容赦なく抱く。
彼をひたすら愛する美しく薄幸の女、美保代。
薄暗い世界で微かに灯るか細い炎のような。
父の書棚で発見して中学生の頃ドキドキしながら読みました。
エロスの香りが濃厚に漂う、ハードボイルド時代小説。
いつかこの狂四郎をキムラに演じて欲しいなぁとずっと思ってます。
ほら、外見なんてピッタリじゃないですか?彫が深いし髪も茶色いし。
そして…日本人離れした白い肌。
日焼け厳禁ですから、眠狂四郎は(笑)
昔、片岡孝夫版を見た覚えがありますが…田村正和もやってたんですね。
(wikiで確認)
テレビだとエロス薄めになっちゃうので、是非映画で。
美保代役、誰がいいだろう…とぴたっとハマる女優さん、見つかりました。
上戸彩。
彼女以外、あり得ません。
Fish Work the Bering Sea / Corey Arnold
2015年1月14日 読書Twitterでまたもや心惹かれる写真家さんを見つけてしまった。
Corey Arnold氏はポーランドを中心に活動している漁師兼フォトグラファーだそうです。
この意外すぎる組み合わせ。
その作品は当然、漁師としての日常の厳しさと喜びに彩られていて…。
自然の見せる素顔。
それが意図されたものでないぶん美しく、時には恐ろしく、宗教的な神々しさすら
感じる色彩と造形に満ちている。
人間はなんとちっぽけで、また健気で素晴らしい生き物だろうか。
釣り上げたデカい鮭の返り血を浴びながら、大らかに笑う漁師。
それは、ヒトが<笑い>を覚えたばかりの原始的な喜びを連想させる、剥き出しの
エネルギーに満ちている。
http://tabi-labo.com/75033/corey-arnold-photo/?utm_content=bufferac61c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
早速Amazonで検索。
『Fish Work the Bering Sea / Corey Arnold』
やっぱ高い←
でも欲しい。
最近つくづく思う。
自分はホンキが好きなんだと。
人も、作品も。
Corey Arnold氏はポーランドを中心に活動している漁師兼フォトグラファーだそうです。
この意外すぎる組み合わせ。
その作品は当然、漁師としての日常の厳しさと喜びに彩られていて…。
自然の見せる素顔。
それが意図されたものでないぶん美しく、時には恐ろしく、宗教的な神々しさすら
感じる色彩と造形に満ちている。
人間はなんとちっぽけで、また健気で素晴らしい生き物だろうか。
釣り上げたデカい鮭の返り血を浴びながら、大らかに笑う漁師。
それは、ヒトが<笑い>を覚えたばかりの原始的な喜びを連想させる、剥き出しの
エネルギーに満ちている。
http://tabi-labo.com/75033/corey-arnold-photo/?utm_content=bufferac61c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
早速Amazonで検索。
『Fish Work the Bering Sea / Corey Arnold』
やっぱ高い←
でも欲しい。
最近つくづく思う。
自分はホンキが好きなんだと。
人も、作品も。
BIRD7号 きらめきのシルクロードへ (講談社 Mook(J))
2014年12月18日 読書
十代の頃、世界の国々の写真集を持っていた。
確か全部で12冊くらいあって異国の町並みや暮らしや
そこに住む人の風俗を眺めながら、あれこれ想像に浸っていた。
北の国、南の島、熱帯のジャングル、そして砂漠。
中でも一番強く惹かれた写真は、驚く程精密な文様の
タイルで彩られたイスラム寺院の内部だった。
明るいターコイズブルーと深い藍染めのようなネイビーブルー。
強烈な太陽を連想するレモンイエロー。オアシスの樹木のようなグリーン。
鮮やかで艶やかに描かれた複雑なアラベスク模様が、蒼穹の空から垂下がる不思議な蜂の巣のように重なり合い、じっと眺めているといつのまにか吸い込まれて、まるで
自分がその場で天上を見上げているような錯覚に陥ったものだ。
『イラクのイスファハーンにあるモスクの一部』だと解説がついていた。
…いつかここに行ってみたい! 子供心に強く思った。
しかし悲しいことに間もなくイランイラク戦争が始まってしまい、ニュースで激しい市街戦の様子を見た私は、もしかしたらあの美しいモスクは失われてしまったんじゃないかと思っていた。
雑誌『Bird』は前もアイスランド特集の感想を書いたけど、旅好きで人とは違う体験をしてみたい女子向けの雑誌らしく、内容も割とディープで視点が面白い。
何より写真がスタイリッシュで、紙質がよいので質感や色が気持ちいい。
で、シルクロードである。
買わなくてどうする(笑)
さて。
書店でぱらぱらとページをめくった私の目にいきなり飛び込んできた一枚。
それはまさに、あのイスファハーンのモスクだった。
昔の記憶どおりに。寸分たがわず。色褪せないまま。
激しい戦火に焼かれず、破壊されることなく、ずうっとそこにあったのだ。
なんだか胸がジーンと熱くなった。
よかった、戦争が終わって。
もしかしたら近い将来、ここに行くことができるかもしれないじゃないか。
それにしてもタイルって色褪せないんだなぁ。
あのまんま、記憶の中のままだなんて。
イスファハーンのモスクの他にも優美で荘厳なイスラム建築や、過酷な自然の中で
シンプルに力強く暮らす遊牧民、カラフルでおしゃれな衣装の女性たち、伝統的な
キリム絨毯、そして神秘的なトルコのパムッカレの自然など、非常に魅力的で充実した内容であります。
そしてとにかく ブルーが印象に残る。
キルギスの真っ白な砂漠にぽっかりと浮かぶ青い湖、そして壮大な砂漠の湖に映る
月の光のワン・ショットの素晴らしさ。
透き通るような深い紺碧に染上げられた空と大地に、月が放つ白銀の光が反射して
この世のものとは思えない。
ああ、生きてるうちに行ってみたい場所がまた増えてしまった…。
確か全部で12冊くらいあって異国の町並みや暮らしや
そこに住む人の風俗を眺めながら、あれこれ想像に浸っていた。
北の国、南の島、熱帯のジャングル、そして砂漠。
中でも一番強く惹かれた写真は、驚く程精密な文様の
タイルで彩られたイスラム寺院の内部だった。
明るいターコイズブルーと深い藍染めのようなネイビーブルー。
強烈な太陽を連想するレモンイエロー。オアシスの樹木のようなグリーン。
鮮やかで艶やかに描かれた複雑なアラベスク模様が、蒼穹の空から垂下がる不思議な蜂の巣のように重なり合い、じっと眺めているといつのまにか吸い込まれて、まるで
自分がその場で天上を見上げているような錯覚に陥ったものだ。
『イラクのイスファハーンにあるモスクの一部』だと解説がついていた。
…いつかここに行ってみたい! 子供心に強く思った。
しかし悲しいことに間もなくイランイラク戦争が始まってしまい、ニュースで激しい市街戦の様子を見た私は、もしかしたらあの美しいモスクは失われてしまったんじゃないかと思っていた。
雑誌『Bird』は前もアイスランド特集の感想を書いたけど、旅好きで人とは違う体験をしてみたい女子向けの雑誌らしく、内容も割とディープで視点が面白い。
何より写真がスタイリッシュで、紙質がよいので質感や色が気持ちいい。
で、シルクロードである。
買わなくてどうする(笑)
さて。
書店でぱらぱらとページをめくった私の目にいきなり飛び込んできた一枚。
それはまさに、あのイスファハーンのモスクだった。
昔の記憶どおりに。寸分たがわず。色褪せないまま。
激しい戦火に焼かれず、破壊されることなく、ずうっとそこにあったのだ。
なんだか胸がジーンと熱くなった。
よかった、戦争が終わって。
もしかしたら近い将来、ここに行くことができるかもしれないじゃないか。
それにしてもタイルって色褪せないんだなぁ。
あのまんま、記憶の中のままだなんて。
イスファハーンのモスクの他にも優美で荘厳なイスラム建築や、過酷な自然の中で
シンプルに力強く暮らす遊牧民、カラフルでおしゃれな衣装の女性たち、伝統的な
キリム絨毯、そして神秘的なトルコのパムッカレの自然など、非常に魅力的で充実した内容であります。
そしてとにかく ブルーが印象に残る。
キルギスの真っ白な砂漠にぽっかりと浮かぶ青い湖、そして壮大な砂漠の湖に映る
月の光のワン・ショットの素晴らしさ。
透き通るような深い紺碧に染上げられた空と大地に、月が放つ白銀の光が反射して
この世のものとは思えない。
ああ、生きてるうちに行ってみたい場所がまた増えてしまった…。
BIRD (講談社 Mook(J))/ICELAND
2014年8月31日 読書
ブックオフで見つけた。
TRANSIT誌の女性向け雑誌。
旅をテーマにその国のカルチャーや日常生活を
丁寧に独自の視点で紹介している。
アイスランドはイングランドの更に北側に位置する
こじんまりと小さな島国。
寒いけど活火山がたくさんあって熱い国でもある。
アイスランドと言えば
ミュージシャンのビョークやシガー・ロスを輩出している国。
どっちも独特で幻想的で懐かしいような、別の世界から響いてくるような音と
世界観を持っている。
どうしてこんな音楽が生まれるんだろう?
昔、ビョークがインタビューで
「アイスランドでは雨が降っても傘なんてささない。風が強過ぎて役に立たないの。イングランドにやってきて皆が傘をさして歩いてるのにはびっくりしたわ。」
って話していたのが何故か強烈に印象に残っている。
写真でみたアイスランドの風景。
氷河が削り取った岩肌が剥き出しの岩壁の上から、遥か地上に向かって流れ落ちる
巨大な滝、ビロードのような背の低い草に覆われた大地、その上に広がるのは
うっすら青みがかった銀色の空。
その空が、こじんまりとした街の上にも、ふつふつと湧き上る天然の温泉の上にも、
どんより冷たい青い色をした海の上にも広がっている。
晴れてるのか、曇っているのか。
靄がかかったような曖昧な空気と妙にくっきり見える大地のりんかく。
確かにこんな世界でしかあの音やメロディは生まれなかったに違いない。
そして小さなこの国の人々は温かく寄り添うように生きている。
誰もが顔見知りでお決まりの場所には誰かしら知ってる顔がいる、というように。
時には息苦しくなるし、思い切って外の世界へ出て行く人もいるが、時々たまらなく懐かしくなって、何度でも戻ってくるのだそうだ。
何となく夢の世界のようだな、と思った。
何度も何度も繰り返し夢の中で行く場所。
あ、またここに来ちゃったな、と思うのだけど、妙に懐かしくて切ないところ。
きっとアイスランドに行ったら、そんな感じがしそうな気がする。
いつかは行ってみたい国がまた一つ増えたのでした。
アイスランドの風景が出て来るMVふたつ。
*Birthday/Sugercubesビョークのソロデビュー前、アイスランドのバンド時代。
https://www.youtube.com/watch?v=noXYiNo5TOo
*Olsen Olsen/Sigur ros
https://www.youtube.com/watch?v=Hi4ZpS3DLhw
TRANSIT誌の女性向け雑誌。
旅をテーマにその国のカルチャーや日常生活を
丁寧に独自の視点で紹介している。
アイスランドはイングランドの更に北側に位置する
こじんまりと小さな島国。
寒いけど活火山がたくさんあって熱い国でもある。
アイスランドと言えば
ミュージシャンのビョークやシガー・ロスを輩出している国。
どっちも独特で幻想的で懐かしいような、別の世界から響いてくるような音と
世界観を持っている。
どうしてこんな音楽が生まれるんだろう?
昔、ビョークがインタビューで
「アイスランドでは雨が降っても傘なんてささない。風が強過ぎて役に立たないの。イングランドにやってきて皆が傘をさして歩いてるのにはびっくりしたわ。」
って話していたのが何故か強烈に印象に残っている。
写真でみたアイスランドの風景。
氷河が削り取った岩肌が剥き出しの岩壁の上から、遥か地上に向かって流れ落ちる
巨大な滝、ビロードのような背の低い草に覆われた大地、その上に広がるのは
うっすら青みがかった銀色の空。
その空が、こじんまりとした街の上にも、ふつふつと湧き上る天然の温泉の上にも、
どんより冷たい青い色をした海の上にも広がっている。
晴れてるのか、曇っているのか。
靄がかかったような曖昧な空気と妙にくっきり見える大地のりんかく。
確かにこんな世界でしかあの音やメロディは生まれなかったに違いない。
そして小さなこの国の人々は温かく寄り添うように生きている。
誰もが顔見知りでお決まりの場所には誰かしら知ってる顔がいる、というように。
時には息苦しくなるし、思い切って外の世界へ出て行く人もいるが、時々たまらなく懐かしくなって、何度でも戻ってくるのだそうだ。
何となく夢の世界のようだな、と思った。
何度も何度も繰り返し夢の中で行く場所。
あ、またここに来ちゃったな、と思うのだけど、妙に懐かしくて切ないところ。
きっとアイスランドに行ったら、そんな感じがしそうな気がする。
いつかは行ってみたい国がまた一つ増えたのでした。
アイスランドの風景が出て来るMVふたつ。
*Birthday/Sugercubesビョークのソロデビュー前、アイスランドのバンド時代。
https://www.youtube.com/watch?v=noXYiNo5TOo
*Olsen Olsen/Sigur ros
https://www.youtube.com/watch?v=Hi4ZpS3DLhw
Before They Pass Away
2014年8月10日 読書
Twitterで流れて来た写真を見て心を奪われました。
シンプルに力強く、美しい。
http://virates.com/society/313968
『失われてゆく少数民族の姿』を写真というメディアの
タイムカプセルで保存する。
所謂学術的にも貴重な資料ではあるでしょうけれど。
圧倒的な美しさの前に言葉は無意味。
と、いうわけで15000円超え・総重量5キロのこの写真集が
欲しくてたまらない…。
シンプルに力強く、美しい。
http://virates.com/society/313968
『失われてゆく少数民族の姿』を写真というメディアの
タイムカプセルで保存する。
所謂学術的にも貴重な資料ではあるでしょうけれど。
圧倒的な美しさの前に言葉は無意味。
と、いうわけで15000円超え・総重量5キロのこの写真集が
欲しくてたまらない…。
KINFOLKって雑誌を目にしたのは去年。
色合いといいモデルの雰囲気といいとってもいいんだけど、
なんの雑誌なのかイマイチよく分からなくて
購入したことは無かった。
たまたま某リサイクル書店でピカピカの古本(新古本かも…)
を見つけて購入。
なんと特集は<老い>。
モデルさんは所謂高齢者のカテゴリーに入ってくる年齢の男女
ばかりですが、まぁ。
カッコいいのなんの。
ファッションはもちろん、その姿勢も生き方もスタイリッシュ。
職業は様々。
もちろん若くはないので、しみやしわはあるし、プロポーションもそれなり。
でも美しいんですよねー…。
皆さんあきらめてない。ファッションもお化粧も、そして自分の生き方も。
シワだらけの手のアップの写真があるのですが、素晴らしく印象に残った。
美しい高齢者の方々の他にも、スタイリッシュに撮影されたお料理やインテリア、
建築物や風景なんかの写真もあり。
たぶんライフスタイルマガジンってカテゴリーに入るんでしょうかね。
これはジャパンエディションですが、もともとアメリカのポートランドが発祥の
雑誌とのこと。
ポートランド。
ユニークでナチュラルでアーティスティックな生き方をする人々が集まる街として
ここ数年雑誌に取り上げられることも多くなってきた場所(らしいw)。
KINFORKとは、KIN=同族、同類 FOLK=人々 を組み合わせた言葉ということ。
『同じような考え方の人たちのつながり』
…みたいな意味なんでしょうかね。
年四回発行。
雑誌にしてはお高いのは広告がほとんど掲載されてないのと、全体のクォリティの
高さを見れば仕方ないのかもしれません。
(ほとんど、というのは一部、お洋服やなんかがさり気なく紹介されているので)
(carharttとかnest robeとか、成る程なんか分かる)
が、果たしてどういう層の人たちが定期的に購入するんだろうか…。
でもかなりいい感じなので、最新号もちょっと中身を確かめてみて気に入ったら買ってみてもいいかな〜…。などと考えたのでした。
色合いといいモデルの雰囲気といいとってもいいんだけど、
なんの雑誌なのかイマイチよく分からなくて
購入したことは無かった。
たまたま某リサイクル書店でピカピカの古本(新古本かも…)
を見つけて購入。
なんと特集は<老い>。
モデルさんは所謂高齢者のカテゴリーに入ってくる年齢の男女
ばかりですが、まぁ。
カッコいいのなんの。
ファッションはもちろん、その姿勢も生き方もスタイリッシュ。
職業は様々。
もちろん若くはないので、しみやしわはあるし、プロポーションもそれなり。
でも美しいんですよねー…。
皆さんあきらめてない。ファッションもお化粧も、そして自分の生き方も。
シワだらけの手のアップの写真があるのですが、素晴らしく印象に残った。
美しい高齢者の方々の他にも、スタイリッシュに撮影されたお料理やインテリア、
建築物や風景なんかの写真もあり。
たぶんライフスタイルマガジンってカテゴリーに入るんでしょうかね。
これはジャパンエディションですが、もともとアメリカのポートランドが発祥の
雑誌とのこと。
ポートランド。
ユニークでナチュラルでアーティスティックな生き方をする人々が集まる街として
ここ数年雑誌に取り上げられることも多くなってきた場所(らしいw)。
KINFORKとは、KIN=同族、同類 FOLK=人々 を組み合わせた言葉ということ。
『同じような考え方の人たちのつながり』
…みたいな意味なんでしょうかね。
年四回発行。
雑誌にしてはお高いのは広告がほとんど掲載されてないのと、全体のクォリティの
高さを見れば仕方ないのかもしれません。
(ほとんど、というのは一部、お洋服やなんかがさり気なく紹介されているので)
(carharttとかnest robeとか、成る程なんか分かる)
が、果たしてどういう層の人たちが定期的に購入するんだろうか…。
でもかなりいい感じなので、最新号もちょっと中身を確かめてみて気に入ったら買ってみてもいいかな〜…。などと考えたのでした。
読み始めたら止まらない。
『赤い追跡者』
エイズウィルスによる血液製剤汚染を知りつつ闇から闇へ事実を隠匿し、二千人もの血友病患者を感染させた黒幕は誰だ?
真実を追い求め、目的のためには手段を選ばず
<取材の悪魔>と囁かれるTVディレクター、西悟。
ストーリーもさることながら、筆者が元NHKのPとあって臨場感が違う。
そして映像的な文章。
おススメです。
これ、Twitterのフォロワーさんのおススメだったんですよ。
彼女の描いた西悟のイメージは<荒野のカメラマン>のキムラ。
うん、ぴったりだ。
Nikonのカタログ表紙でまさに西そのものの写真があるんですよ。
うっすらと無精髭、異様な眼光を放つ目、黒い革ジャン。
キムラに挑んで欲しい役がまた一つ増えてしまった…。
『赤い追跡者』
エイズウィルスによる血液製剤汚染を知りつつ闇から闇へ事実を隠匿し、二千人もの血友病患者を感染させた黒幕は誰だ?
真実を追い求め、目的のためには手段を選ばず
<取材の悪魔>と囁かれるTVディレクター、西悟。
ストーリーもさることながら、筆者が元NHKのPとあって臨場感が違う。
そして映像的な文章。
おススメです。
これ、Twitterのフォロワーさんのおススメだったんですよ。
彼女の描いた西悟のイメージは<荒野のカメラマン>のキムラ。
うん、ぴったりだ。
Nikonのカタログ表紙でまさに西そのものの写真があるんですよ。
うっすらと無精髭、異様な眼光を放つ目、黒い革ジャン。
キムラに挑んで欲しい役がまた一つ増えてしまった…。
広島に原爆を落とす日/つか こうへい著 (編集しました)
2013年12月30日 読書 コメント (2)
MAYUKO様が以前紹介されていた『広島に原爆を落とす日』。
凄い作品です。
読み始めてすぐに物語の世界に否応無く引込まれ、
時間を忘れて読み耽り、
最後は涙が止まりませんでした。
本でこんなに泣いたのは何年ぶりだろうか…。
主人公は二人の男女。
朝鮮王族の血筋でありながら、日本人に国を滅ぼされ、母・知淑と共に日本へやってきた犬子恨一郎。
差別に苦しみながらも誇りと名誉を追い求め、少佐の地位まで這い上がってきた彼は自分の愛国心は日本人以上と自負する男。
特異な名は誇り高い母が敢えて選んだもの。
王族の姓=李を捨てた自分たちは犬畜生以下だと名字を<犬子>とし、恨み忘れまじと息子に与えた名が<恨一郎(はんいちろう)>。
その恨一郎が愛した美しい女、髪百合子。
百合子もまた訳あって先祖代々呪われ蔑まれてきた賤民の一族の出身。
幼なじみの二人は自然に惹かれ合い、稀に見る美貌と芯の強さを備えた百合子に、
恨一郎は結婚を申し込むが、「朝鮮人の元へ嫁になどいけない。」と断られ、
愛の深さ故酷く傷つき、百合子への想いを断ち切るかのように、日本国を守る闘いに激しくのめり込んで行く。
時代は太平洋戦争末期。
日本の敗戦は決定的なのに、何故アメリカは敢えて原爆を投下したのか。
日本人より日本を愛した男が何故、投下ボタンを押す役目を自ら引き受けたのか。
ストーリーは二つの謎を巡って当時の日本の政界・軍、アメリカ大統領、ヒトラーとナチス・ドイツまで巻き込んで虚々実々の壮大なスケールで展開する。
もちろん史実とは全く異なる虚構の世界の架空の出来事、ある意味ファンタジー。
でも単なる夢物語を描くなら、これほど危険で挑戦的なテーマを選ばないはず。
日本、アメリカ、ドイツまで巻き込んだ複雑怪奇な物語は、人の欲望と哀しみを
壮大にまき散らしながら、最終的に恨一郎と百合子の愛の成就というただ一点に
収束していく。
そう、これは純愛の物語なのです。
人の想いが純粋で一途で清らかに光輝くほど、その向こう側には真っ黒な憎しみの
影が生まれる。
それが人間という生き物の避け難い業。
この世で一番深く重く、目も眩むような愛の証を百合子に捧げる。
その執念で生きる恨一郎が選んだのが、原爆投下のスイッチを押すことだった。
意味深に<エンジェル>と名付けられた、人類史上最悪の爆弾。
それが炸裂した瞬間、世界に死の天使が降臨する。
白い閃光と黒い雨を伴って。
現世では叶わぬ二人の恋が、熱線で無辜の数十万人を焼き払いながら成就する。
恨一郎は真っ赤なチマチョゴリを纏った百合子を遥か上空から目視し、その頭上へ
精確に爆弾を投下する。
彼の想いを、百合子は両手を大きく広げ、喜びを溢れさせながら受け止める。
夏の青い空/生い茂る樹々の濃い緑/中心に立つ真っ赤なチマチョゴリ。
上空からまっすぐ投下される黒い金属の塊。
白熱した閃光が全てを包み込み、焼尽す。
色彩のコントラストが引き起こす視覚イメージの強烈な生々しさ。
その美しさが行為の恐ろしさを圧倒し、むしろ高揚感とカタルシスを伴った感動を
引き起こした。
その時私は恨一郎と百合子の感情や感覚の一部を共有し体験していたに違いない。
この世で一番愛する人を自らの手で永久に消し去る。
その瞬間、彼女の愛は自分だけに注がれて俺の世界は至上の悦びに光輝く。
百合子は、永遠に自分のもの。
原爆投下直後、自分は腹を切るので介錯してほしいと恨一郎はB29に同乗したアメリカ人に懇願する。
「犯した罪は決して許されない。私の魂は永遠に宇宙を彷徨うだろう。」
「その長い時間の唯一の慰めが、かつて人を愛したという記憶だけ。」
恨一郎もまた、その瞬間に想いの全てを捧げる。
人類史上最初に核爆弾のスイッチを押した恐怖の名として俺は、人々の記憶に残る。
向けられる憎しみと蔑みが激しいほど、救いとしての愛の記憶は無限に強度を増す。
抱えた想いの強さだけが彼を、永遠の孤独に耐えさせる。
究極の愛の物語。
凄い作品です。
読み始めてすぐに物語の世界に否応無く引込まれ、
時間を忘れて読み耽り、
最後は涙が止まりませんでした。
本でこんなに泣いたのは何年ぶりだろうか…。
主人公は二人の男女。
朝鮮王族の血筋でありながら、日本人に国を滅ぼされ、母・知淑と共に日本へやってきた犬子恨一郎。
差別に苦しみながらも誇りと名誉を追い求め、少佐の地位まで這い上がってきた彼は自分の愛国心は日本人以上と自負する男。
特異な名は誇り高い母が敢えて選んだもの。
王族の姓=李を捨てた自分たちは犬畜生以下だと名字を<犬子>とし、恨み忘れまじと息子に与えた名が<恨一郎(はんいちろう)>。
その恨一郎が愛した美しい女、髪百合子。
百合子もまた訳あって先祖代々呪われ蔑まれてきた賤民の一族の出身。
幼なじみの二人は自然に惹かれ合い、稀に見る美貌と芯の強さを備えた百合子に、
恨一郎は結婚を申し込むが、「朝鮮人の元へ嫁になどいけない。」と断られ、
愛の深さ故酷く傷つき、百合子への想いを断ち切るかのように、日本国を守る闘いに激しくのめり込んで行く。
時代は太平洋戦争末期。
日本の敗戦は決定的なのに、何故アメリカは敢えて原爆を投下したのか。
日本人より日本を愛した男が何故、投下ボタンを押す役目を自ら引き受けたのか。
ストーリーは二つの謎を巡って当時の日本の政界・軍、アメリカ大統領、ヒトラーとナチス・ドイツまで巻き込んで虚々実々の壮大なスケールで展開する。
もちろん史実とは全く異なる虚構の世界の架空の出来事、ある意味ファンタジー。
でも単なる夢物語を描くなら、これほど危険で挑戦的なテーマを選ばないはず。
日本、アメリカ、ドイツまで巻き込んだ複雑怪奇な物語は、人の欲望と哀しみを
壮大にまき散らしながら、最終的に恨一郎と百合子の愛の成就というただ一点に
収束していく。
そう、これは純愛の物語なのです。
人の想いが純粋で一途で清らかに光輝くほど、その向こう側には真っ黒な憎しみの
影が生まれる。
それが人間という生き物の避け難い業。
この世で一番深く重く、目も眩むような愛の証を百合子に捧げる。
その執念で生きる恨一郎が選んだのが、原爆投下のスイッチを押すことだった。
意味深に<エンジェル>と名付けられた、人類史上最悪の爆弾。
それが炸裂した瞬間、世界に死の天使が降臨する。
白い閃光と黒い雨を伴って。
現世では叶わぬ二人の恋が、熱線で無辜の数十万人を焼き払いながら成就する。
恨一郎は真っ赤なチマチョゴリを纏った百合子を遥か上空から目視し、その頭上へ
精確に爆弾を投下する。
彼の想いを、百合子は両手を大きく広げ、喜びを溢れさせながら受け止める。
夏の青い空/生い茂る樹々の濃い緑/中心に立つ真っ赤なチマチョゴリ。
上空からまっすぐ投下される黒い金属の塊。
白熱した閃光が全てを包み込み、焼尽す。
色彩のコントラストが引き起こす視覚イメージの強烈な生々しさ。
その美しさが行為の恐ろしさを圧倒し、むしろ高揚感とカタルシスを伴った感動を
引き起こした。
その時私は恨一郎と百合子の感情や感覚の一部を共有し体験していたに違いない。
この世で一番愛する人を自らの手で永久に消し去る。
その瞬間、彼女の愛は自分だけに注がれて俺の世界は至上の悦びに光輝く。
百合子は、永遠に自分のもの。
原爆投下直後、自分は腹を切るので介錯してほしいと恨一郎はB29に同乗したアメリカ人に懇願する。
「犯した罪は決して許されない。私の魂は永遠に宇宙を彷徨うだろう。」
「その長い時間の唯一の慰めが、かつて人を愛したという記憶だけ。」
恨一郎もまた、その瞬間に想いの全てを捧げる。
人類史上最初に核爆弾のスイッチを押した恐怖の名として俺は、人々の記憶に残る。
向けられる憎しみと蔑みが激しいほど、救いとしての愛の記憶は無限に強度を増す。
抱えた想いの強さだけが彼を、永遠の孤独に耐えさせる。
究極の愛の物語。
ゴローズ大全vol.2
2013年7月12日 読書
書店でぱらぱらめくって、これは手元に置いて
じっくり見なきゃ駄目だと思った。
最初から順を追って目を通そうと。
もちろんキムラのインタビュー目当てで買ったけど、
そこにいきなり飛びこんではいけない気がした。
「アクセサリー以上のもの、お守りみたいなもの」
ゴローズのアクセサリーがどんな風に作られ、選ばれ、
大切に扱われているか、
最初のページから読んでみて初めて、言葉の意味が実感できた気がする。
皮革と銀。
人の手で触れ、頻繁に身につけることで味わいを増していく素材。
例えばベルトのバックルの裏のスレ。ブレスレットやリングの細かい傷や曇り。
酸化の黒ずみ。柔らかくしなやかに、こっくりした色合いに熟成された皮。
所有者に<なじんで>いく過程で、<その人らしさ>を写し取ったモノの写真からは時に持ち主の体温すら感じる。
「選ぶとき、自分も選ばれている」
「それを身につけるのにふさわしいかどうか」
高校生で手に入れたブレスレットから始まり、少しずつ数を増やして行くそれらは、キムラの成長・成熟の歴史を一緒に歩んできた。
触れて・見ることのできる成長の証であり、記録であり、縛めでもあるのだろう。
(観念より実体、言葉より行為を信じる彼にはまさにうってつけの存在だ)
彼の<お守り>は願掛けといったような他力本願な存在ではない。
「(闘いの前の)ネイティブのフェイスペインティングのようなもの」
彼の戦場は西部の荒野でなく、TVや映画やコンサートの現場ではあるけれど。
その<お守り>のパワーはどこから来るのか。
作った人(ゴローさん)、選んでくれた人、手渡してくれた人と彼との、精神的な
繋がりの結果として自分の手元にある。とキムラは言う。
手に入れる過程を含めて、関わった全ての人の気持ちが刻み込まれている<お守り>を身につけるのは、その人たちと一緒に<居る>のと同じなのかもしれない。
それらをある種の畏敬をこめて<お守り>と呼ぶ彼の、繊細で多分にロマンティックなセンスが私は大好きだ。
人が好きでいつも誰かと一緒に居たい、繋がっていたいという気持ちが透けて見えてそこは開放区でずーっとキムラが語ってきたことと重なる。
だからこれは、40歳の木村拓哉の開放区だと思った。
じっくり見なきゃ駄目だと思った。
最初から順を追って目を通そうと。
もちろんキムラのインタビュー目当てで買ったけど、
そこにいきなり飛びこんではいけない気がした。
「アクセサリー以上のもの、お守りみたいなもの」
ゴローズのアクセサリーがどんな風に作られ、選ばれ、
大切に扱われているか、
最初のページから読んでみて初めて、言葉の意味が実感できた気がする。
皮革と銀。
人の手で触れ、頻繁に身につけることで味わいを増していく素材。
例えばベルトのバックルの裏のスレ。ブレスレットやリングの細かい傷や曇り。
酸化の黒ずみ。柔らかくしなやかに、こっくりした色合いに熟成された皮。
所有者に<なじんで>いく過程で、<その人らしさ>を写し取ったモノの写真からは時に持ち主の体温すら感じる。
「選ぶとき、自分も選ばれている」
「それを身につけるのにふさわしいかどうか」
高校生で手に入れたブレスレットから始まり、少しずつ数を増やして行くそれらは、キムラの成長・成熟の歴史を一緒に歩んできた。
触れて・見ることのできる成長の証であり、記録であり、縛めでもあるのだろう。
(観念より実体、言葉より行為を信じる彼にはまさにうってつけの存在だ)
彼の<お守り>は願掛けといったような他力本願な存在ではない。
「(闘いの前の)ネイティブのフェイスペインティングのようなもの」
彼の戦場は西部の荒野でなく、TVや映画やコンサートの現場ではあるけれど。
その<お守り>のパワーはどこから来るのか。
作った人(ゴローさん)、選んでくれた人、手渡してくれた人と彼との、精神的な
繋がりの結果として自分の手元にある。とキムラは言う。
手に入れる過程を含めて、関わった全ての人の気持ちが刻み込まれている<お守り>を身につけるのは、その人たちと一緒に<居る>のと同じなのかもしれない。
それらをある種の畏敬をこめて<お守り>と呼ぶ彼の、繊細で多分にロマンティックなセンスが私は大好きだ。
人が好きでいつも誰かと一緒に居たい、繋がっていたいという気持ちが透けて見えてそこは開放区でずーっとキムラが語ってきたことと重なる。
だからこれは、40歳の木村拓哉の開放区だと思った。
クウネル 別冊 着る?2 (マガジンハウスムック ku:nel別冊)
2013年3月27日 読書
こういうムック誌にありがちなのですが
やっぱり一冊目ほどインパクトは無いです。
といっても他のナチュラル系ファッション
提案マガジン(ナリュリラとかその周辺)
とは一線を画すいい写真と味わいのあるコーディネート。
冒頭の町田康氏のエッセイというか書き下ろしというか、
すっとぼけた、いかにもな感じの文章がとっても好きです。
すっ飛ばさずに読んでみてください。
戎 康友氏の撮る、海と真っ白い服。
青と純白の眩しさに突然そそり立つ灰色の岩肌のバランスが清々しい。
コーディネートはねじったり結んだり巻いたりか、あっさりそのままを着るかで、
アシンメトリーなバランスが何となく和の発想。
大好きだったころのコムデギャルソンを思い出し懐かしくなりました。
ああいう服、最近はとんと着ないなぁ。
P75のコーディネートが、まさにあの時代のギャルソンまんまでちょっとびっくり。
全体的に大人しい写真が多い中で目を引いたのが
ソニア・パークのARTS&SCIENCEのページ。
深紅のワンピースの美しさに目がクギヅケになりました。
珊瑚でも朱色でも、暗紅色でも薔薇色でもない、本当の真っ赤。
説明を読んでビックリ。
カイガラムシの一種「ラック」の染料を使い京都で染めたものだそう。
つい最近勧められて『完璧な赤』という本を読んだばかりなので感慨もひとしお。
http://www.hayakawa-online.co.jp/product/books/112162.html
おお!!!これが16世紀のヨーロッパの人々が血眼になって探し求めた赤か!
他には本藍染めのブラウスが素敵だったなぁ。少しグリーン味を帯びた藍色。
ソニア・パークのモノ作りは一つ一つにストーリーがありますな(蘊蓄とも云うw)
撮影はホンマタカシ氏。
Ku:nel本誌を見ても思うのですが、こういう雑誌ってもちろん洋服や小物や
ライフスタイルの提案も大事ですけど、カタログ的な見せ方じゃないので、
全体のイメージ作りに写真の果たす役割はかなり大きい。
たぶんモデルやロケーション選びの段階から、フォトグラファーも企画に参加して
一緒に作り上げてるんだろうな。
あれ?
なんだかんだ言って結局結構気に入ってるような(笑)
三冊目が出たらきっと買ってしまうだろうなぁ…。
話変わりまして。
最近フランシス・ベーコンのインタビュー集を読んでいるのですが、これがとても
残念な本で。
インタビュー内容はとてもエキサイティングで興味深いんだけど、読み辛い。
たぶん翻訳がダメダメなんだろうな…。
1996年出版なんですが、どっかの大学の研究者さんで、うーむ。
この手の方々の翻訳にありがちな。
英語力は満点でも日本語力が…(ry.
読み終わったら美術手帖を読みます。
こっちはかなり面白そう。
やっぱり一冊目ほどインパクトは無いです。
といっても他のナチュラル系ファッション
提案マガジン(ナリュリラとかその周辺)
とは一線を画すいい写真と味わいのあるコーディネート。
冒頭の町田康氏のエッセイというか書き下ろしというか、
すっとぼけた、いかにもな感じの文章がとっても好きです。
すっ飛ばさずに読んでみてください。
戎 康友氏の撮る、海と真っ白い服。
青と純白の眩しさに突然そそり立つ灰色の岩肌のバランスが清々しい。
コーディネートはねじったり結んだり巻いたりか、あっさりそのままを着るかで、
アシンメトリーなバランスが何となく和の発想。
大好きだったころのコムデギャルソンを思い出し懐かしくなりました。
ああいう服、最近はとんと着ないなぁ。
P75のコーディネートが、まさにあの時代のギャルソンまんまでちょっとびっくり。
全体的に大人しい写真が多い中で目を引いたのが
ソニア・パークのARTS&SCIENCEのページ。
深紅のワンピースの美しさに目がクギヅケになりました。
珊瑚でも朱色でも、暗紅色でも薔薇色でもない、本当の真っ赤。
説明を読んでビックリ。
カイガラムシの一種「ラック」の染料を使い京都で染めたものだそう。
つい最近勧められて『完璧な赤』という本を読んだばかりなので感慨もひとしお。
http://www.hayakawa-online.co.jp/product/books/112162.html
おお!!!これが16世紀のヨーロッパの人々が血眼になって探し求めた赤か!
他には本藍染めのブラウスが素敵だったなぁ。少しグリーン味を帯びた藍色。
ソニア・パークのモノ作りは一つ一つにストーリーがありますな(蘊蓄とも云うw)
撮影はホンマタカシ氏。
Ku:nel本誌を見ても思うのですが、こういう雑誌ってもちろん洋服や小物や
ライフスタイルの提案も大事ですけど、カタログ的な見せ方じゃないので、
全体のイメージ作りに写真の果たす役割はかなり大きい。
たぶんモデルやロケーション選びの段階から、フォトグラファーも企画に参加して
一緒に作り上げてるんだろうな。
あれ?
なんだかんだ言って結局結構気に入ってるような(笑)
三冊目が出たらきっと買ってしまうだろうなぁ…。
話変わりまして。
最近フランシス・ベーコンのインタビュー集を読んでいるのですが、これがとても
残念な本で。
インタビュー内容はとてもエキサイティングで興味深いんだけど、読み辛い。
たぶん翻訳がダメダメなんだろうな…。
1996年出版なんですが、どっかの大学の研究者さんで、うーむ。
この手の方々の翻訳にありがちな。
英語力は満点でも日本語力が…(ry.
読み終わったら美術手帖を読みます。
こっちはかなり面白そう。
ku:nel (クウネル) 2013年 05月号 [雑誌]
2013年3月19日 読書
久々に雑誌をジャケ買いしました。
パッと目が合って一瞬で惹き付けられた感じ、写真に。
あーku:nelか。
しかも特集が「詩とサンドイッチ。」
<詩のすすめ いんちき篇>なんて書いてある、
このエッセイみたいな文章が頷けることしきり。
特に
「あからさまなものというのは、たいてい美しくはありませんから」
「いつだって自分の小さな世界に風穴をあけ、
ひろびろと思わぬ方角にひろげてくれるのは『わからないもの』です」
のくだりとか。
サンドイッチの断面の写真も美しいし、スタイリストの大森伃佑子さん(永遠の
オリーブ少女)の、好きなもの道を突っ走る姿はカッコいいし、
隅々までゆっくり読もう。
表紙の吸い込まれるような神秘的な写真。
撮ったのはアンドレイ・タルコフスキー。
ポラロイドで愛妻と愛犬を撮影したものだとか。
まるで彼の映画のワン・シーンから切り取ったような。
Ku:nelにはp12とp13に二枚掲載されているだけですが、見開きページで並んでいる
感じがうつくしいのです。
余白とか文字のバランスまで計算されたレイアウトっていいなぁ。
でも、やっぱり二枚じゃもの足りない。
早速Amazonでタルコフスキーのポラロイド写真集をポチっと。
はっ!!
今気がついたのですが、『Ku:nel 着る?②』今日発売だったのですね。
タルコフスキーの写真に目を奪われてよく確認しなかった…。
買いにいかねば。
パッと目が合って一瞬で惹き付けられた感じ、写真に。
あーku:nelか。
しかも特集が「詩とサンドイッチ。」
<詩のすすめ いんちき篇>なんて書いてある、
このエッセイみたいな文章が頷けることしきり。
特に
「あからさまなものというのは、たいてい美しくはありませんから」
「いつだって自分の小さな世界に風穴をあけ、
ひろびろと思わぬ方角にひろげてくれるのは『わからないもの』です」
のくだりとか。
サンドイッチの断面の写真も美しいし、スタイリストの大森伃佑子さん(永遠の
オリーブ少女)の、好きなもの道を突っ走る姿はカッコいいし、
隅々までゆっくり読もう。
表紙の吸い込まれるような神秘的な写真。
撮ったのはアンドレイ・タルコフスキー。
ポラロイドで愛妻と愛犬を撮影したものだとか。
まるで彼の映画のワン・シーンから切り取ったような。
Ku:nelにはp12とp13に二枚掲載されているだけですが、見開きページで並んでいる
感じがうつくしいのです。
余白とか文字のバランスまで計算されたレイアウトっていいなぁ。
でも、やっぱり二枚じゃもの足りない。
早速Amazonでタルコフスキーのポラロイド写真集をポチっと。
はっ!!
今気がついたのですが、『Ku:nel 着る?②』今日発売だったのですね。
タルコフスキーの写真に目を奪われてよく確認しなかった…。
買いにいかねば。
ku:nel (クウネル) 2013年 03月号
2013年2月10日 読書
表紙が斬新。
書店の棚見てあれ?コレなに?
え?あ、ku:nelかぁ!…って思いました。
今回とても心惹かれたのが「祈りの森へ」と名付けられた
一連の美しい写真。
澤村木綿子さんという作家さんの、衣装ともぬいぐるみとも
分類不可能なオブジェ。
この方の作品は布とかビーズとか鳥の羽根とかを使い、刺繍の技術で作り上げられた
作品を、人が纏うことによって完成するというユニークなもの。
http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120921_11861.html
上のサイトにも掲載されているシロクマのお母さんや、灰色のオオカミ、白い鳥の
羽根を繊細に繋げてつくった、天使の翼のついたドレス。
着ぐるみみたいなものなのですが、細密で何か神秘的な美しさのあるコスチュームは
むしろ呪術的なパワーすら感じます。
これらの<作品>たちは自然の力が形をとって現れたもので、それを纏うことで
人と自然が分ち難く渾然一体となった姿を表現しているのだそう。
着る人と一つになって、冬枯れの森の中にすーっと立つ姿は精霊のよう。
温かく優しくもあるけれど、何か畏怖に似た感覚をも呼び起こします。
これは是非、実物を見てみたいなぁと思いました。
さて。
今回の特集は「よろず相談 うけたまわり〼」ということで。
毎朝のミルクティー、もっとおいしくなりませんか?という比較的フツーのものから
(といっても回答内容は全然フツーじゃなくてマニアックなんだけどw)
網戸でコウモリが冬眠。わたしはどうすればいいのでしょう?なんてユニークなもの
まで(とても真面目な回答&無事コウモリさんは救出されたようです)
楽しめました。が。これにはちょっとビックリ。
『料理の味が決まらないのです』
レシピの<適宜>や<少々>の意味がわからない。美味しい、の加減って?
という質問なんですけど…。
えーーーーーっと。ちょっとビックリ。
料理するとき大抵、こんなもんかな?と勘で塩や醤油や砂糖やコショーを投入してる
自分としては、<美味しい>の加減=自分好みの味の加減、なんですよね…。
なんだろう?この質問の意味が分からん。
と、しばし考えてふと。
もしかして、この質問者は味付けに<正解>と<不正解>があると思っているのかもしれないなぁと。
「おいしい!」って感覚は人それぞれじゃないのかなぁ。
極端にしょっぱいとか甘ったるいってのは問題外だけど、家で作るごはんって、
作り手によって少しずつ味が違って来るのは当たり前なんだから、◯◯さんちのみそ汁は正解で、XXさんちのは不正解、ってのはないと思うし。
体調によって少々塩気が強くなったり薄味になったりって変動があったりするのも、
家庭料理らしくていいんじゃないだろうか?
レストランで出す料理がそれじゃあうまくないだろうけどね(笑)
書店の棚見てあれ?コレなに?
え?あ、ku:nelかぁ!…って思いました。
今回とても心惹かれたのが「祈りの森へ」と名付けられた
一連の美しい写真。
澤村木綿子さんという作家さんの、衣装ともぬいぐるみとも
分類不可能なオブジェ。
この方の作品は布とかビーズとか鳥の羽根とかを使い、刺繍の技術で作り上げられた
作品を、人が纏うことによって完成するというユニークなもの。
http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120921_11861.html
上のサイトにも掲載されているシロクマのお母さんや、灰色のオオカミ、白い鳥の
羽根を繊細に繋げてつくった、天使の翼のついたドレス。
着ぐるみみたいなものなのですが、細密で何か神秘的な美しさのあるコスチュームは
むしろ呪術的なパワーすら感じます。
これらの<作品>たちは自然の力が形をとって現れたもので、それを纏うことで
人と自然が分ち難く渾然一体となった姿を表現しているのだそう。
着る人と一つになって、冬枯れの森の中にすーっと立つ姿は精霊のよう。
温かく優しくもあるけれど、何か畏怖に似た感覚をも呼び起こします。
これは是非、実物を見てみたいなぁと思いました。
さて。
今回の特集は「よろず相談 うけたまわり〼」ということで。
毎朝のミルクティー、もっとおいしくなりませんか?という比較的フツーのものから
(といっても回答内容は全然フツーじゃなくてマニアックなんだけどw)
網戸でコウモリが冬眠。わたしはどうすればいいのでしょう?なんてユニークなもの
まで(とても真面目な回答&無事コウモリさんは救出されたようです)
楽しめました。が。これにはちょっとビックリ。
『料理の味が決まらないのです』
レシピの<適宜>や<少々>の意味がわからない。美味しい、の加減って?
という質問なんですけど…。
えーーーーーっと。ちょっとビックリ。
料理するとき大抵、こんなもんかな?と勘で塩や醤油や砂糖やコショーを投入してる
自分としては、<美味しい>の加減=自分好みの味の加減、なんですよね…。
なんだろう?この質問の意味が分からん。
と、しばし考えてふと。
もしかして、この質問者は味付けに<正解>と<不正解>があると思っているのかもしれないなぁと。
「おいしい!」って感覚は人それぞれじゃないのかなぁ。
極端にしょっぱいとか甘ったるいってのは問題外だけど、家で作るごはんって、
作り手によって少しずつ味が違って来るのは当たり前なんだから、◯◯さんちのみそ汁は正解で、XXさんちのは不正解、ってのはないと思うし。
体調によって少々塩気が強くなったり薄味になったりって変動があったりするのも、
家庭料理らしくていいんじゃないだろうか?
レストランで出す料理がそれじゃあうまくないだろうけどね(笑)
BRUTUS (ブルータス) 2012年 8/15号 [雑誌]
2012年11月17日 読書
発売当時買い損ね、マガジンハウスHPでも品切れ。
某ブックオフでようやく入手(嬉)
表紙はアンディ・ウォーホルのイラスト。
まずBRUTUSがこういう特集したのが意外でありました。
同じマガジンハウスでもku:nelはこの手の特集よくやってるけど。
中身はBRUTUSらしく植物の育て方読本とかじゃなくて、
国内外の植物にまつわる人・場所・モノの話。
初っ端の若き日本人プラント・ハンターの清順さんという方の存在に興奮。
プラント・ハンターとは異国の珍しい植物を探し出し収集し、母国へ持ち帰るプロ。
植民地建設に熱心な時代のイギリス人のイメージが強かったので、意外でした。
清順さんがオーストラリアの珍しい<ボトルツリー>の巨木を現地から掘り出し、
長い航海を経て無事日本へ運び、植樹するまでを追ったレポがエキサイティング。
クレーンでつり下げられたその姿は、まるで珍獣ジュゴンそっくりで、可愛い。
ちなみにこの樹は<代々木VILLAGE>に植樹されたそうです。
清順さんはネット上で人々の心に植物を植える『そら植物園』というプロジェクトで
活動しているそうな。
http://from-sora.com
写真を見てるだけでも楽しいですよ。
さて。
この本で個別に紹介されている植物は、例えば薔薇とかハーブとか、よく知られる
種類のものではありません。
むしろ形として面白かったり少しグロテスクだったり、ビックリするような性質を
持っていたりします。
具体的には多肉植物とか食虫植物とかサボテンの類いとかが中心。
どっちかというと奇を衒った見せ方と言えなくもない。
しかしまぁ、BRUTUSですものね…普通の植物を見たいなら他にいくらでも雑誌が
あるわけですし。
それに、その手の植物のマニアックさ加減、フォトジェニックさは、いかにも
BRUTUS愛読者が好みそうですし。(←勝手にきめつけw)
その編集意図が見事に的中。
植物なんか女と年寄りのもの、なんとなく辛気くさいじゃん、とか思っていた層を
ぐぐっと惹き付けたに違いありません。
(お陰でコッチは古本屋を探し回るはめになったぜ)
でも、なぜ今植物?
BRUTUSのターゲットがそういう年齢wにさしかかったのか?
しかし仮にターゲット層を30〜40代と考えると、いささか若い。
そこには、3.11.以来の世の中の雰囲気が深く関係してるのは間違いない気がする。
植物を手入れする時間って気持ちがリセットされるんです。
綺麗な色や形や匂いに癒されるのももちろんですが、喋らない・動かない彼らを、
毎日眺め、水をやって、虫に喰われてないか、病気っぽくはないかと気にかけてるとその分ちゃんと返ってくる。
少しずつ着実に成長し、茎を伸ばし、葉を広げて、花や実をつけてくれる。
やがて冬が来て葉が落ちても、根か種子が生きていれば、また春には新芽を吹く。
少し前にも書いたけど、世界の目に見えない大きなサイクルを、抽象的でなく具体的に見せてくれる。
規則正しい安定したリズムで。
それは子育てや人と人とのコミュニケーションとはまた別なんです。
もの言わぬ相手なだけに、むしろ自分と向き合ってる感覚に近いかもしれない。
…あ。
大幅に脱線してしまいましたね;
そうそう。
あと面白かったのが『植物を愛した人たち』の章。
<芸術家と庭>の項ではデレク・ジャーマンとジョージア・オキーフ。
どっちも大好きな芸術家ではありますが…庭と言えば『睡蓮』のモネじゃ…?
と、ソッチ方面に行かないのがいかにもBRUTUSだなぁと思いました(笑)
某ブックオフでようやく入手(嬉)
表紙はアンディ・ウォーホルのイラスト。
まずBRUTUSがこういう特集したのが意外でありました。
同じマガジンハウスでもku:nelはこの手の特集よくやってるけど。
中身はBRUTUSらしく植物の育て方読本とかじゃなくて、
国内外の植物にまつわる人・場所・モノの話。
初っ端の若き日本人プラント・ハンターの清順さんという方の存在に興奮。
プラント・ハンターとは異国の珍しい植物を探し出し収集し、母国へ持ち帰るプロ。
植民地建設に熱心な時代のイギリス人のイメージが強かったので、意外でした。
清順さんがオーストラリアの珍しい<ボトルツリー>の巨木を現地から掘り出し、
長い航海を経て無事日本へ運び、植樹するまでを追ったレポがエキサイティング。
クレーンでつり下げられたその姿は、まるで珍獣ジュゴンそっくりで、可愛い。
ちなみにこの樹は<代々木VILLAGE>に植樹されたそうです。
清順さんはネット上で人々の心に植物を植える『そら植物園』というプロジェクトで
活動しているそうな。
http://from-sora.com
写真を見てるだけでも楽しいですよ。
さて。
この本で個別に紹介されている植物は、例えば薔薇とかハーブとか、よく知られる
種類のものではありません。
むしろ形として面白かったり少しグロテスクだったり、ビックリするような性質を
持っていたりします。
具体的には多肉植物とか食虫植物とかサボテンの類いとかが中心。
どっちかというと奇を衒った見せ方と言えなくもない。
しかしまぁ、BRUTUSですものね…普通の植物を見たいなら他にいくらでも雑誌が
あるわけですし。
それに、その手の植物のマニアックさ加減、フォトジェニックさは、いかにも
BRUTUS愛読者が好みそうですし。(←勝手にきめつけw)
その編集意図が見事に的中。
植物なんか女と年寄りのもの、なんとなく辛気くさいじゃん、とか思っていた層を
ぐぐっと惹き付けたに違いありません。
(お陰でコッチは古本屋を探し回るはめになったぜ)
でも、なぜ今植物?
BRUTUSのターゲットがそういう年齢wにさしかかったのか?
しかし仮にターゲット層を30〜40代と考えると、いささか若い。
そこには、3.11.以来の世の中の雰囲気が深く関係してるのは間違いない気がする。
植物を手入れする時間って気持ちがリセットされるんです。
綺麗な色や形や匂いに癒されるのももちろんですが、喋らない・動かない彼らを、
毎日眺め、水をやって、虫に喰われてないか、病気っぽくはないかと気にかけてるとその分ちゃんと返ってくる。
少しずつ着実に成長し、茎を伸ばし、葉を広げて、花や実をつけてくれる。
やがて冬が来て葉が落ちても、根か種子が生きていれば、また春には新芽を吹く。
少し前にも書いたけど、世界の目に見えない大きなサイクルを、抽象的でなく具体的に見せてくれる。
規則正しい安定したリズムで。
それは子育てや人と人とのコミュニケーションとはまた別なんです。
もの言わぬ相手なだけに、むしろ自分と向き合ってる感覚に近いかもしれない。
…あ。
大幅に脱線してしまいましたね;
そうそう。
あと面白かったのが『植物を愛した人たち』の章。
<芸術家と庭>の項ではデレク・ジャーマンとジョージア・オキーフ。
どっちも大好きな芸術家ではありますが…庭と言えば『睡蓮』のモネじゃ…?
と、ソッチ方面に行かないのがいかにもBRUTUSだなぁと思いました(笑)
高橋ヨーコさんの写真を知ったのはKU:NELの創刊号の表紙。
仲睦まじい白人のおじいさんとおばあさん。
幸せそのものの笑顔。
なんかいいなぁ…と思って写真家さんの名前を見たら
『高橋ヨーコ』とあった。
ちなみにこのご夫婦はロシア人で、
郊外の小さな家で仲良く寛いでいるところだそう。
高橋さんの撮る写真は独特の色調である。
少し褪せたようなオレンジとブルーが印象に残る。
アメリカのイラストレーター、
ノーマン・ロックウェルを思い出す。
そこに北ヨーロッパのエッセンスを振りかけたような印象。
(KU:NELのトーベ・ヤンソン特集は何度見ても素晴らしい)
雑誌で、あれ?この写真いいなぁ、と思うと高橋さんのお名前が。
日本とアメリカを拠点とし、世界中で撮り続ける彼女は、旅の写真家でもある。
作品には土地の空気や水や光の具合までがしっかり収まっている。
それでいて、どれにも<彼女らしさ>が詰まっている。
そんな高橋さんが『ONTARIO PAPER』なる本を創刊されたと知り、早速購入。
http://ontariopaper.com/index_jp.html
主にアメリカ中西部を移動しながら撮った写真。
身体中にタトゥーを施したタトゥーマニアの女の子たち。
若干14歳のブルライダーを目指す少年。
(ブルライダー=暴れ牛乗り)
まるでウェスタン映画に出てきそうなカウボーイたち。
どの人もおおらかで、いい顔してる。
確かに今のアメリカなんだけど、どことなく古き良き時代のノスタルジーの香り。
赤茶色の広い大地を、高橋さんは車で移動する。
未知の人々と出会い、話をし、少しの間心を通わせて撮られた写真。
ページをめくるごとに自分が彼女の体験を共有しているような錯覚に陥る。
それはまるで一本のロードムービーを見ているようであります。
10/31まで青山の『BOOK246』という旅をテーマにした書店で写真展を開催中。
期間中に見に行きたいなぁ…。
http://book246.com/news/gallery/2750
この本屋さん自体が魅力的ですよね。
仲睦まじい白人のおじいさんとおばあさん。
幸せそのものの笑顔。
なんかいいなぁ…と思って写真家さんの名前を見たら
『高橋ヨーコ』とあった。
ちなみにこのご夫婦はロシア人で、
郊外の小さな家で仲良く寛いでいるところだそう。
高橋さんの撮る写真は独特の色調である。
少し褪せたようなオレンジとブルーが印象に残る。
アメリカのイラストレーター、
ノーマン・ロックウェルを思い出す。
そこに北ヨーロッパのエッセンスを振りかけたような印象。
(KU:NELのトーベ・ヤンソン特集は何度見ても素晴らしい)
雑誌で、あれ?この写真いいなぁ、と思うと高橋さんのお名前が。
日本とアメリカを拠点とし、世界中で撮り続ける彼女は、旅の写真家でもある。
作品には土地の空気や水や光の具合までがしっかり収まっている。
それでいて、どれにも<彼女らしさ>が詰まっている。
そんな高橋さんが『ONTARIO PAPER』なる本を創刊されたと知り、早速購入。
http://ontariopaper.com/index_jp.html
主にアメリカ中西部を移動しながら撮った写真。
身体中にタトゥーを施したタトゥーマニアの女の子たち。
若干14歳のブルライダーを目指す少年。
(ブルライダー=暴れ牛乗り)
まるでウェスタン映画に出てきそうなカウボーイたち。
どの人もおおらかで、いい顔してる。
確かに今のアメリカなんだけど、どことなく古き良き時代のノスタルジーの香り。
赤茶色の広い大地を、高橋さんは車で移動する。
未知の人々と出会い、話をし、少しの間心を通わせて撮られた写真。
ページをめくるごとに自分が彼女の体験を共有しているような錯覚に陥る。
それはまるで一本のロードムービーを見ているようであります。
10/31まで青山の『BOOK246』という旅をテーマにした書店で写真展を開催中。
期間中に見に行きたいなぁ…。
http://book246.com/news/gallery/2750
この本屋さん自体が魅力的ですよね。
ku:nel (クウネル) 2012年 09月号
2012年8月25日 読書
表紙のピンクとラベンダーの
不思議な花の形に目が留まる。
矢車菊?
にしては色が違うなぁ…。
ぱらぱらとめくって最初に飛び込んできたのは
鮮烈な赤。
『母から娘へ受け継ぐ珊瑚。もも色、ぼけ色、ちあか色。』
スタイリストの山下りかさんの帯留めから始まった珊瑚の物語は、
お母様の田中まきさんの住んでいる高知へ。
珊瑚の仲買人だったまきさんのおうちでの珊瑚の思い出へと
話はつながっていく。
母から娘へ。
優しいコーラルピンクからオレンジ、そして血の赤色。
綿を敷き詰めたブリキ缶に大切にしまわれた珊瑚の玉。
中でも、ちあか珊瑚の美しさは格別にドラマティック。
真綿の白にポトリと滴る真っ赤な一滴。
どこかでそんな物語を読んだ気が…。
そうそう、白雪姫の物語の冒頭シーン。
さて、表紙の花ですが。
RARI YOSHIHOさん作、チャイブのドライフラワーでした。
あのネギ坊主みたいな花が、きれいに乾かすととこんなに繊細な
ニュアンスを醸し出すのだなぁ。
ほかにもチューリップやタンポポ、カモミールの花。
四角い箱に無造作に詰められた様子は作りかけの標本みたい。
珊瑚もドライフラワーもとてもシンプルな見せ方ですが、
ずーっと眺めていても飽きません。
もっと深く知りたくなるエピソードのある物事には、
「これ、なんだろう?」と目をひく引力があるのかも。
…そして今日もUOMO10月号は書店に無。orz
不思議な花の形に目が留まる。
矢車菊?
にしては色が違うなぁ…。
ぱらぱらとめくって最初に飛び込んできたのは
鮮烈な赤。
『母から娘へ受け継ぐ珊瑚。もも色、ぼけ色、ちあか色。』
スタイリストの山下りかさんの帯留めから始まった珊瑚の物語は、
お母様の田中まきさんの住んでいる高知へ。
珊瑚の仲買人だったまきさんのおうちでの珊瑚の思い出へと
話はつながっていく。
母から娘へ。
優しいコーラルピンクからオレンジ、そして血の赤色。
綿を敷き詰めたブリキ缶に大切にしまわれた珊瑚の玉。
中でも、ちあか珊瑚の美しさは格別にドラマティック。
真綿の白にポトリと滴る真っ赤な一滴。
どこかでそんな物語を読んだ気が…。
そうそう、白雪姫の物語の冒頭シーン。
さて、表紙の花ですが。
RARI YOSHIHOさん作、チャイブのドライフラワーでした。
あのネギ坊主みたいな花が、きれいに乾かすととこんなに繊細な
ニュアンスを醸し出すのだなぁ。
ほかにもチューリップやタンポポ、カモミールの花。
四角い箱に無造作に詰められた様子は作りかけの標本みたい。
珊瑚もドライフラワーもとてもシンプルな見せ方ですが、
ずーっと眺めていても飽きません。
もっと深く知りたくなるエピソードのある物事には、
「これ、なんだろう?」と目をひく引力があるのかも。
…そして今日もUOMO10月号は書店に無。orz
ku:nel別冊 大人はおしゃれ 着る? (マガジンハウスムック ku:nel別冊)
2012年3月30日 読書
最近ファッション雑誌を見なくなった。
トレンドというものにだんだん興味が薄れてしまったらしい。
それと、自分の年齢(40代半ば過ぎ)向けに編集&スタイリング
されたであろうと思われる雑誌のコーディネートが、
全くもって自分向きでないのである。
日頃コンバースのスニーカーを愛用しているような人間は
最初から排除されているとしか思えない。
まぁ自分だって似合えば&リッチだったら履いてみたいですけど、
マノロ・ブラニクとか。
キレイですしね。
ということで。
久々に買ったファッション誌。
表紙だけ見ると無印良品がシーズンごとに無料配布してる衣料カタログみたいだ(笑)
基本1Pにワンコーディネイト。
これが見やすくていいですし、それぞれのスタイリングがすごーく計算して、拘って、
慎重に図って撮られたって感じがして好感が持てます。
一応それぞれの服のブランド&店名や価格が掲載されてますが、
写真を邪魔しない程度に、地味に小さく。
一枚一枚に思いいれがこめられてるのがわかるので、じっくり見たくなりますし、
何より服の素材感がわかるのがよい。
「透ける麻のブラウスは、マットな質感のニットを合わせるとキレイだな~。」とか、
「全身黒でも、布地の質感を変えるだけで喪服っぽくならないのだなぁ。」とか。
あと、色彩が多すぎず少なすぎず絶妙できもちいいのも好感度。
ただ、あまりにもシンプルすぎて見ようによってはそっけないかもしれない。
そこから情報を得るためには、少々の想像力が要求されるといえなくもない。
不親切といえば不親切だけど、こういう姿勢ってマガジンハウスらしさだと思うので、
私は好きだな。
何にしろ、受け手に至れり尽くせりの情報提供って親切なようで
実は有難迷惑だと思っているので...。
『白いシャツの似合う人』に、そのイメージから一番遠いところに居ると思われるクレイジー剣こと横山剣さんが登場してるのですが、とってもカッコイイです。
男女問わず<STYLE>のある人はそこに居るだけでサマになりますよね。
トレンドというものにだんだん興味が薄れてしまったらしい。
それと、自分の年齢(40代半ば過ぎ)向けに編集&スタイリング
されたであろうと思われる雑誌のコーディネートが、
全くもって自分向きでないのである。
日頃コンバースのスニーカーを愛用しているような人間は
最初から排除されているとしか思えない。
まぁ自分だって似合えば&リッチだったら履いてみたいですけど、
マノロ・ブラニクとか。
キレイですしね。
ということで。
久々に買ったファッション誌。
表紙だけ見ると無印良品がシーズンごとに無料配布してる衣料カタログみたいだ(笑)
基本1Pにワンコーディネイト。
これが見やすくていいですし、それぞれのスタイリングがすごーく計算して、拘って、
慎重に図って撮られたって感じがして好感が持てます。
一応それぞれの服のブランド&店名や価格が掲載されてますが、
写真を邪魔しない程度に、地味に小さく。
一枚一枚に思いいれがこめられてるのがわかるので、じっくり見たくなりますし、
何より服の素材感がわかるのがよい。
「透ける麻のブラウスは、マットな質感のニットを合わせるとキレイだな~。」とか、
「全身黒でも、布地の質感を変えるだけで喪服っぽくならないのだなぁ。」とか。
あと、色彩が多すぎず少なすぎず絶妙できもちいいのも好感度。
ただ、あまりにもシンプルすぎて見ようによってはそっけないかもしれない。
そこから情報を得るためには、少々の想像力が要求されるといえなくもない。
不親切といえば不親切だけど、こういう姿勢ってマガジンハウスらしさだと思うので、
私は好きだな。
何にしろ、受け手に至れり尽くせりの情報提供って親切なようで
実は有難迷惑だと思っているので...。
『白いシャツの似合う人』に、そのイメージから一番遠いところに居ると思われるクレイジー剣こと横山剣さんが登場してるのですが、とってもカッコイイです。
男女問わず<STYLE>のある人はそこに居るだけでサマになりますよね。
日本人女性が単身海外へ渡ること自体冒険であっただろう’60年代。
アーティストとしてその特異な才能で世界的に有名な草間彌生。
当時の彼女の作品と活動、NYという都市が発していた
剥き出しのエネルギーを、
彼女自身の言葉と写真で再現しようと試みた本。
<たたかう>という言葉が、あらゆる意味でぴったりくる。
戦う、ではなく。
武器も暴力も彼女は持たない。
だから、<たたかう>。
強迫観念的な水玉や反復、自己消滅のイメージ。
ボディペインティングした裸の男女、オージー(乱交)といったスキャンダラスな
パフォーマンスは、
より多くの人の目を惹き付ける仕掛けであっただろうけれど、
その行動の根っこにあるのは、
『表現することでしか生きている実感を得られない』ような、切羽詰った衝動であったことを
伺わせる。
その頃のNYの空気や熱気を感じるだけでも、刺激的な本だと思う。
大好きな彼女の言葉が引用されていました。
初めて読んだのがいつだったのか...もう思い出せません。
しかし読むたびに、そのインパクトの強さ・言葉の強靭さに感動する。
私にとって彼女は、すごくカッコイイ女性、なのです。
「私は私の死に至るまで、あたかも終着なきハイウェイをドライブし続けるかのように感ずる。自働式のカフェテリアで出される数千杯のコーヒーを飲み続けるかのようである。そして、私が望むと望むまいと、私の生涯の終わりまで、ありとあらゆるヴィジョンを欲望し、同時に逃避し続けるつもりだ、私は生存をとめることもできないし、また死から逃げることもできない。」
(『芸術生活』1975年11月号より)
アーティストとしてその特異な才能で世界的に有名な草間彌生。
当時の彼女の作品と活動、NYという都市が発していた
剥き出しのエネルギーを、
彼女自身の言葉と写真で再現しようと試みた本。
<たたかう>という言葉が、あらゆる意味でぴったりくる。
戦う、ではなく。
武器も暴力も彼女は持たない。
だから、<たたかう>。
強迫観念的な水玉や反復、自己消滅のイメージ。
ボディペインティングした裸の男女、オージー(乱交)といったスキャンダラスな
パフォーマンスは、
より多くの人の目を惹き付ける仕掛けであっただろうけれど、
その行動の根っこにあるのは、
『表現することでしか生きている実感を得られない』ような、切羽詰った衝動であったことを
伺わせる。
その頃のNYの空気や熱気を感じるだけでも、刺激的な本だと思う。
大好きな彼女の言葉が引用されていました。
初めて読んだのがいつだったのか...もう思い出せません。
しかし読むたびに、そのインパクトの強さ・言葉の強靭さに感動する。
私にとって彼女は、すごくカッコイイ女性、なのです。
「私は私の死に至るまで、あたかも終着なきハイウェイをドライブし続けるかのように感ずる。自働式のカフェテリアで出される数千杯のコーヒーを飲み続けるかのようである。そして、私が望むと望むまいと、私の生涯の終わりまで、ありとあらゆるヴィジョンを欲望し、同時に逃避し続けるつもりだ、私は生存をとめることもできないし、また死から逃げることもできない。」
(『芸術生活』1975年11月号より)
とても美しい物語だと思った。
著者の岸 真理子・モリアさんはプロの作家ではない。
パリのギャラリーで働くためやってきて、ロベール・クートラスと出会い、
彼自身の語る夢とも現ともつかない半生を語る言葉を丁寧に書きとめた。
その言葉は詩的な映像に満ち、道端に捨てられた古いものたちや、
彼が石工として働いたフランスの田舎にあるカテドラル(教会)の屋根裏や目立たない壁の彫刻たちが不思議な輝きを纏って生きいきと語りだす。
周囲と溶け込めなかった子供時代、奔放な母、戦争。
それらを通り抜け、アートで生きていくためにやってきたパリ。
ちょうど60年代から70年代の、アーティストやそのパトロンたちの、自堕落で
魅力的で節操のないボヘミアン的生活の様子。
ナイーブで頑なで、生きていくにはあまりにも繊細すぎるような彼のまっすぐな目。
芸術の純粋性を信じ、自分の周りを美しいものだけで埋めていくことを念じているような彼は、やがてすこしずつ精神を病んでいく。
彼が「僕の夜」と呼んだ美しく謎めいたカルトの作品集
『僕の夜 Mes Nuits』
(以前感想を書きました→http://holidaze.diarynote.jp/201101151933401464/)
比較すると作品の写真が少ないのが残念ですが、装丁も美しく、
何より岸さんの文章が心地よい。
クートラスの言葉と彼女の見た彼の姿を、誠実に書きとめようとする意志が感じられて。
彼女がプロの作家でないことが帰って幸いしたのかもしれない。
はんぶん夢の世界に住んでいるようなクートラスは、無邪気でいろんな人に優しいけれど、
普通の意味での恋人への誠実さなどはかけらもなく、それだけに実際のところは、
もっと生々しい感情のもつれややりとりがあったかもしれないけれど。
クートラスが「親方の獲り分」と呼び、決して画商に売り渡そうとしなかったカルトたち。
いわば彼の魂の欠片のような作品を今も大切に守り続けている彼女。
ありきたりな表現だけれど、<ソウル・メイト>という言葉が浮かんだ。
著者の岸 真理子・モリアさんはプロの作家ではない。
パリのギャラリーで働くためやってきて、ロベール・クートラスと出会い、
彼自身の語る夢とも現ともつかない半生を語る言葉を丁寧に書きとめた。
その言葉は詩的な映像に満ち、道端に捨てられた古いものたちや、
彼が石工として働いたフランスの田舎にあるカテドラル(教会)の屋根裏や目立たない壁の彫刻たちが不思議な輝きを纏って生きいきと語りだす。
周囲と溶け込めなかった子供時代、奔放な母、戦争。
それらを通り抜け、アートで生きていくためにやってきたパリ。
ちょうど60年代から70年代の、アーティストやそのパトロンたちの、自堕落で
魅力的で節操のないボヘミアン的生活の様子。
ナイーブで頑なで、生きていくにはあまりにも繊細すぎるような彼のまっすぐな目。
芸術の純粋性を信じ、自分の周りを美しいものだけで埋めていくことを念じているような彼は、やがてすこしずつ精神を病んでいく。
彼が「僕の夜」と呼んだ美しく謎めいたカルトの作品集
『僕の夜 Mes Nuits』
(以前感想を書きました→http://holidaze.diarynote.jp/201101151933401464/)
比較すると作品の写真が少ないのが残念ですが、装丁も美しく、
何より岸さんの文章が心地よい。
クートラスの言葉と彼女の見た彼の姿を、誠実に書きとめようとする意志が感じられて。
彼女がプロの作家でないことが帰って幸いしたのかもしれない。
はんぶん夢の世界に住んでいるようなクートラスは、無邪気でいろんな人に優しいけれど、
普通の意味での恋人への誠実さなどはかけらもなく、それだけに実際のところは、
もっと生々しい感情のもつれややりとりがあったかもしれないけれど。
クートラスが「親方の獲り分」と呼び、決して画商に売り渡そうとしなかったカルトたち。
いわば彼の魂の欠片のような作品を今も大切に守り続けている彼女。
ありきたりな表現だけれど、<ソウル・メイト>という言葉が浮かんだ。
開放区2~Bitter
2011年10月6日 読書
昨日書いたことについて。
開放区2で語ってたなぁと思い出し早速探してみた。
『Bitter』というタイトルで、
いかにも彼らしい言葉で綴ってあってニヤリとする。
苦みもえぐみも心地いい。
その変化は豊かなものとして実感できるし満足している。
旨い 上手いなー。
彼はボキャブラリーは多くないけどいつも、その言葉のふくらみに気付かされハッとする。
<渋い(=えぐみ)><苦みばしった>とくれば、当然オトコ←なぜかカタカナなんですw
そこが、キムラの場合具体的な味覚(文中では山菜)に結びつくのも面白い。
というのは置いといて。
まさにその、オトナの味覚ですよねー・・・。ENDLESSのあのモノクロフォト。
そうか。
長年において全幅(かどうかしらんけど)の信頼を置く野口さんと組んで、
メンズ誌ならではのコンセプトで、彼の言う『大人の味覚』に取組んだのがアレなんだ。
うんうん。私は好きだよ。
ワインもフルーティでスウィートより思わず口をすぼめるような
タンニンの渋さたっぷりのが好きだからさ(違)
でも実は、こんな感じに撮られた写真、数年前からあった気がします。
一番最初に「あ!」と思ったのは、女性セブンだったかなー・・・。
映画HEROで、咥え煙草の久利生の表情をUPで捉えた一枚。
それがなんとも渋くてね・・・大人の顔だったな。
「こういう顔ができるんだー。これならキムラは40代になっても大丈夫だな!」
となぜか安堵したのを覚えてる。
それと去年のanan。上田義彦氏とのコラボ。
あれは凄かった。
アイドルの薄皮を引っぺがして生身の37歳(当時w)と対峙するカメラ。
闇の動物のような暗い目の青年と、見る人を不安にする予感を秘めた男の体の皮膚感。
しかしどっちも意外と話題にならずに「あれっ?」となったもんです(笑)
彼の新たな味覚への挑戦は、アイドルの顔とは相容れないのだろうか?
・・・なんだかややこしくなってきました。
さて。
このBitterの章には、「大人として開発途上にある」彼なりの、新たな味覚へのワクワク感と、
「どんな大人になるんだろうなー?」という、まだちょっと未知数の青年っぽい憧れが
錯綜していてとても面白いです。
その無邪気なアンテナに引っかかるエピソードがいちいち面白くて愛しい。
ぜんぶ好きなんだけど、一番よかったのが山崎努さんとの会話部分。
タバコ吸いながら「ふつか」って
この下り読みながら、場面がまんま頭の中で再生されちゃって、
すっかりキムラ目線で山崎さん見てたよ私は。
そうそうそうそう!
山崎さんってこういう言い方しますよね!タバコ吸いながら。
十代のころ、そういう山崎さんを何度映像で目撃したことか・・・・。
キムラがドキドキした気分がめちゃくちゃ分ります。
つづく緒形さんのシーンもまんま緒形さん過ぎて。
チャボのとこもそう。
(素晴しい再生能力。言葉でもその才能を発揮できるヤツ。凄い)
彼が今、人生のセンパイとして憧れている人々。
イキイキと綴られたその文章から、彼が何を吸収しつつあるのか、がちょっとだけ
覗ける気がしました。
登場するのがぜんぶ好きなタイプのオトコの人たちだったのも嬉しかったり(笑)
(もちろん出っ歯のオジキもそうですけどねw)
*この本の表紙もキムラ部分だけシルエットなんだねw
なんか・・・ヘンだよやっぱり。
開放区2で語ってたなぁと思い出し早速探してみた。
『Bitter』というタイトルで、
いかにも彼らしい言葉で綴ってあってニヤリとする。
苦みもえぐみも心地いい。
その変化は豊かなものとして実感できるし満足している。
彼はボキャブラリーは多くないけどいつも、その言葉のふくらみに気付かされハッとする。
<渋い(=えぐみ)><苦みばしった>とくれば、当然オトコ←なぜかカタカナなんですw
そこが、キムラの場合具体的な味覚(文中では山菜)に結びつくのも面白い。
というのは置いといて。
まさにその、オトナの味覚ですよねー・・・。ENDLESSのあのモノクロフォト。
そうか。
長年において全幅(かどうかしらんけど)の信頼を置く野口さんと組んで、
メンズ誌ならではのコンセプトで、彼の言う『大人の味覚』に取組んだのがアレなんだ。
うんうん。私は好きだよ。
ワインもフルーティでスウィートより思わず口をすぼめるような
タンニンの渋さたっぷりのが好きだからさ(違)
でも実は、こんな感じに撮られた写真、数年前からあった気がします。
一番最初に「あ!」と思ったのは、女性セブンだったかなー・・・。
映画HEROで、咥え煙草の久利生の表情をUPで捉えた一枚。
それがなんとも渋くてね・・・大人の顔だったな。
「こういう顔ができるんだー。これならキムラは40代になっても大丈夫だな!」
となぜか安堵したのを覚えてる。
それと去年のanan。上田義彦氏とのコラボ。
あれは凄かった。
アイドルの薄皮を引っぺがして生身の37歳(当時w)と対峙するカメラ。
闇の動物のような暗い目の青年と、見る人を不安にする予感を秘めた男の体の皮膚感。
しかしどっちも意外と話題にならずに「あれっ?」となったもんです(笑)
彼の新たな味覚への挑戦は、アイドルの顔とは相容れないのだろうか?
・・・なんだかややこしくなってきました。
さて。
このBitterの章には、「大人として開発途上にある」彼なりの、新たな味覚へのワクワク感と、
「どんな大人になるんだろうなー?」という、まだちょっと未知数の青年っぽい憧れが
錯綜していてとても面白いです。
その無邪気なアンテナに引っかかるエピソードがいちいち面白くて愛しい。
ぜんぶ好きなんだけど、一番よかったのが山崎努さんとの会話部分。
タバコ吸いながら「ふつか」って
この下り読みながら、場面がまんま頭の中で再生されちゃって、
すっかりキムラ目線で山崎さん見てたよ私は。
そうそうそうそう!
山崎さんってこういう言い方しますよね!タバコ吸いながら。
十代のころ、そういう山崎さんを何度映像で目撃したことか・・・・。
キムラがドキドキした気分がめちゃくちゃ分ります。
つづく緒形さんのシーンもまんま緒形さん過ぎて。
チャボのとこもそう。
(素晴しい再生能力。言葉でもその才能を発揮できるヤツ。凄い)
彼が今、人生のセンパイとして憧れている人々。
イキイキと綴られたその文章から、彼が何を吸収しつつあるのか、がちょっとだけ
覗ける気がしました。
登場するのがぜんぶ好きなタイプのオトコの人たちだったのも嬉しかったり(笑)
(もちろん出っ歯のオジキもそうですけどねw)
*この本の表紙もキムラ部分だけシルエットなんだねw
なんか・・・ヘンだよやっぱり。