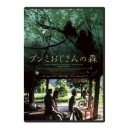ちょっと目を離した隙にふいっとどこかへ消えてしまう恋人。
振り回されて「これが最後だ…!」と自分に言いきかせながら、ふらりと戻ってきた彼の「やり直そう。」の甘い言葉にほだされてしまう<私>。
映画で、小説で、演劇で、何度も何度も目にしてきた物語。
愛し合いながらすれ違う。
相手を必要としているのに一緒に居るとぎくしゃくする。
そんなカップルは世の中にいくらでも居るだろう。
ファイ(トニー・レオン)とウィン(レスリー・チャン)の二人もそんな関係。
少し違うのは、恋人も<私>も男性で、中国人の二人が居るのは地球の反対側、
アルゼンチンのブエノスアイレス。
私はこの作品のDVDを持っていて、その感想は以前書いた。
http://holidaze.diarynote.jp/201010090019447298/
しかしそれから月日が経ったからか、はたまた大スクリーンで見たせいか、見た後の印象が随分違う。
DVDではあまり意識しなかったけれど、ファイが滞在している安アパートの構造…
古くて間口が狭く奥が深く、日の当たらない廊下、共同の汚いキッチン、公衆電話、に強烈な既視感。
これどっかで見た。そうそう、2046のあのアパートとよく似ている。
違うのは住人とファイ&ウィンの生活がほとんど分断されていること。
香港のアパートにあった隣人の気配を感じる瞬間は、ここではほとんどない。
物語自体、ファイとウィン、それに途中から参加する若いチャン(チャン・チェン)の三人の絡み中心で、その他はほぼ背景に過ぎない。
他に親しい者もいない異国、狭く薄暗い部屋に男と男。
冒頭、二人の濃厚なセックスシーンが挿入されるけれど、モノクロで撮られたそれは愛撫というより裸体のぶつかり合いで、終始乾いた感じがつきまとう。
心と身体の行き止まり感を払拭すべく、新たな刺激を求めて二人はレンタカーで
イグアスの滝を目指す。
しかし車はポンコツ。道を間違え、資金も尽きて、二人はけんか別れしてしまう。
ブエノスアイレスに舞い戻りキャバレーの客引きで細々と暮らすファイの元に、怪我をした野良猫のような姿で戻ってくるウィン。
「やり直そう。」
どうせ怪我が治ってしまえばまたどこかへ消えてしまうと知りながら、献身的に看護するファイ。
せめての抵抗とちょっとした復讐心でウィンのパスポートを隠してしまう。
二人が夜、誰もいないキッチンでぴったりと寄り添い踊るアルゼンチンタンゴ。
バンドネオンの物悲しい音色は黒いベルベットの手触りを連想させ、キッチンは
濃密な息づかいと体温の絡み合う官能的なダンスホールへと姿を変える。
…二人の身体と心が完全に一つになったと感じる、魔法のような瞬間。
しかしやがて音楽は終わり、溶け合ったと見えた肉体はまた二つに引き裂かれる。
気まぐれな恋人は姿を消し、ファイは地球の反対側でまた一人。
そこへ若いチャンが現れる。
彼は普通より何倍も耳が鋭く、声でその人の心を読み取る不思議な青年。
彼はファイの声を愛し、たぶんファイ自身を好きだけれど、それはウィンとファイの関係とは違う。
チャンにとって声は発する人そのものであり、彼の愛は肉体の接触を必要としない。
ファイはそんなチャンの無垢な人となりに惹かれ、実は肉体的にも彼を求めていたのではないかと思う。
感受性が強く繊細なファイはついに、それを打ち明けることは無かったけれども。
台湾のチャンの両親が経営する屋台で、密かにチャンの写真を失敬したファイ。
(もしかすると肉体の代用品を手に入れるために)
「会いたいと思えばいつでも会える。例え地球の反対側に居ても。」
肉体は別々の場所にあっても心は一瞬で相手の元へ飛んで一つになれる。
もし、相手も同じように自分のことを考えていると信じられるなら。
一方、<イグアスの滝を一緒に見る>という目的で一つになろうとした
ファイとウィン。
しかし二人が一緒にそこへ辿り着くことは決してない。
身体が、いつも心を追い抜いてしまうから。
ファイが去った部屋で一人泣き崩れるウィン。
ファイがウィンにパスポートを返したかどうか、最後まで描かれることはない。
だってウィンは永久にブエノスアイレスから旅立つことはないのだから。
「やり直そう。」
何度も何度も同じ言葉を口にし、ファイを置き去りにしてまた舞い戻る。
テープの巻き戻し・再生のような人生を選んだウィンは、同じ時間を永久に生き続けるしかない、無限のトラップに落ち込んだのかもしれない。
DVDでは希望に満ちた音に聞こえたラストのHappy Together。
大画面で聞いたそれは、もっと複雑な…正反対の二つの人生を
象徴しているような気がした。
振り回されて「これが最後だ…!」と自分に言いきかせながら、ふらりと戻ってきた彼の「やり直そう。」の甘い言葉にほだされてしまう<私>。
映画で、小説で、演劇で、何度も何度も目にしてきた物語。
愛し合いながらすれ違う。
相手を必要としているのに一緒に居るとぎくしゃくする。
そんなカップルは世の中にいくらでも居るだろう。
ファイ(トニー・レオン)とウィン(レスリー・チャン)の二人もそんな関係。
少し違うのは、恋人も<私>も男性で、中国人の二人が居るのは地球の反対側、
アルゼンチンのブエノスアイレス。
私はこの作品のDVDを持っていて、その感想は以前書いた。
http://holidaze.diarynote.jp/201010090019447298/
しかしそれから月日が経ったからか、はたまた大スクリーンで見たせいか、見た後の印象が随分違う。
DVDではあまり意識しなかったけれど、ファイが滞在している安アパートの構造…
古くて間口が狭く奥が深く、日の当たらない廊下、共同の汚いキッチン、公衆電話、に強烈な既視感。
これどっかで見た。そうそう、2046のあのアパートとよく似ている。
違うのは住人とファイ&ウィンの生活がほとんど分断されていること。
香港のアパートにあった隣人の気配を感じる瞬間は、ここではほとんどない。
物語自体、ファイとウィン、それに途中から参加する若いチャン(チャン・チェン)の三人の絡み中心で、その他はほぼ背景に過ぎない。
他に親しい者もいない異国、狭く薄暗い部屋に男と男。
冒頭、二人の濃厚なセックスシーンが挿入されるけれど、モノクロで撮られたそれは愛撫というより裸体のぶつかり合いで、終始乾いた感じがつきまとう。
心と身体の行き止まり感を払拭すべく、新たな刺激を求めて二人はレンタカーで
イグアスの滝を目指す。
しかし車はポンコツ。道を間違え、資金も尽きて、二人はけんか別れしてしまう。
ブエノスアイレスに舞い戻りキャバレーの客引きで細々と暮らすファイの元に、怪我をした野良猫のような姿で戻ってくるウィン。
「やり直そう。」
どうせ怪我が治ってしまえばまたどこかへ消えてしまうと知りながら、献身的に看護するファイ。
せめての抵抗とちょっとした復讐心でウィンのパスポートを隠してしまう。
二人が夜、誰もいないキッチンでぴったりと寄り添い踊るアルゼンチンタンゴ。
バンドネオンの物悲しい音色は黒いベルベットの手触りを連想させ、キッチンは
濃密な息づかいと体温の絡み合う官能的なダンスホールへと姿を変える。
…二人の身体と心が完全に一つになったと感じる、魔法のような瞬間。
しかしやがて音楽は終わり、溶け合ったと見えた肉体はまた二つに引き裂かれる。
気まぐれな恋人は姿を消し、ファイは地球の反対側でまた一人。
そこへ若いチャンが現れる。
彼は普通より何倍も耳が鋭く、声でその人の心を読み取る不思議な青年。
彼はファイの声を愛し、たぶんファイ自身を好きだけれど、それはウィンとファイの関係とは違う。
チャンにとって声は発する人そのものであり、彼の愛は肉体の接触を必要としない。
ファイはそんなチャンの無垢な人となりに惹かれ、実は肉体的にも彼を求めていたのではないかと思う。
感受性が強く繊細なファイはついに、それを打ち明けることは無かったけれども。
台湾のチャンの両親が経営する屋台で、密かにチャンの写真を失敬したファイ。
(もしかすると肉体の代用品を手に入れるために)
「会いたいと思えばいつでも会える。例え地球の反対側に居ても。」
肉体は別々の場所にあっても心は一瞬で相手の元へ飛んで一つになれる。
もし、相手も同じように自分のことを考えていると信じられるなら。
一方、<イグアスの滝を一緒に見る>という目的で一つになろうとした
ファイとウィン。
しかし二人が一緒にそこへ辿り着くことは決してない。
身体が、いつも心を追い抜いてしまうから。
ファイが去った部屋で一人泣き崩れるウィン。
ファイがウィンにパスポートを返したかどうか、最後まで描かれることはない。
だってウィンは永久にブエノスアイレスから旅立つことはないのだから。
「やり直そう。」
何度も何度も同じ言葉を口にし、ファイを置き去りにしてまた舞い戻る。
テープの巻き戻し・再生のような人生を選んだウィンは、同じ時間を永久に生き続けるしかない、無限のトラップに落ち込んだのかもしれない。
DVDでは希望に満ちた音に聞こえたラストのHappy Together。
大画面で聞いたそれは、もっと複雑な…正反対の二つの人生を
象徴しているような気がした。
HOLY MOTORS
2013年4月25日 映画トレイラー
http://www.holymotors.jp
映画紹介
http://eiga.com/extra/kuriko/9/
冒頭薄暗い狭い部屋のベッドで眠る男と犬。
どうやら船室らしい。というのも、波と船体が軋む音、カモメの声が聞こえるから。
灰色の髪にサングラスの男は起き上がり、不思議な鍵で壁の隠し扉を開く。
暗い通路を通って男が現れたのは映画館の映写室の前のバルコニー。
そこで私は、そこが船室でなく映画館の隠し部屋(そんなものがあるなら)と知る。
観客席にカメラが向き、皆真剣にスクリーンを見ている、そして波とカモメの声。
このサングラスの男こそ、この作品の監督レオス・カラックスで、一見意味不明な
冒頭のシーンが、映画を見るうちにひとつのキーワードなんだと気づく。
突然画面は切り替わって、パリ郊外の豪華客船を思わせるモダンな邸宅と家族、
そこから出勤する初老の男・オスカーを映す。
馬鹿でかい白いリムジンに映画スターのように乗り込む男。
その顔はどちらかというとチンパンジーみたいでお世辞にも男前でなく、しかし
彼の持つ独特の空気感に不思議な深みを感じる。
この俳優=ドニ・ラヴァンはカラックス作品の常連というか、監督の分身のような
存在で、ボーイ・ミーツ・ガールから私の見た作品全てに登場していた。
(ポーラXとオムニバス短編は見てないのですが)
家族から送り出されたときは大企業の社長といった出で立ちの彼は、車内で手早く
カツラを外しメイクを取り服を着替え、禿の異形の男になる。
つまり、豪邸も家族も何もかもが<セット>に過ぎなかったのだ。
彼の仕事はファイルで依頼された人物になりきり、指定された場所でその役柄を演じきること。
リムジンの中はちょうど俳優のメイクルームのようにカツラ、小道具、特殊メイク用の素材、衣装、がぎっしりで、彼はそこで指示通りの人物になり切る。
年老いた物乞いの女、CG映像の人物モデル、墓から出てきた怪物のような男(BGMがゴジラw)、思春期の娘の悩みを真摯に受け止める父親、殺人犯、暗殺者、ストリートミュージシャン、死を目前に、美しい姪に心情を吐露する金持ちの老人。
パートタイムで姿も人格もどんどん変わって行く彼の、ある一日。
リムジンを運転するのは元ダンサーだという50代の美しい女、セリーヌ。
リムジンの中でメイクを落とし衣装を脱いだ時だけが、オスカーの本来の姿。
誰が何のためにオスカーに<役を演じる>ことを依頼しているのか?
全く説明もなく、刻々と姿を、人格を変化させるオスカーを、カメラはドラマチックに映し出す。
異形の怪人の姿で雑誌のグラビア撮影中のスーパーモデルを誘拐し、カメラマン助手の女の指を喰いちぎり、殺人者になって倉庫係の男をナイフで殺害し、(しかも
殺された男の顔もオスカー自身)、普通の父親の姿でパーティに参加した内気な娘を迎えに行く。
私は考える。
オスカーはパートタイムの映画俳優の設定なのかもしれない。
画面には映らないけれど、どこかで極小サイズのカメラが回ってるに違いない。
その、オスカーを主人公にした様々な映画のメイキングを見ているんだ。
(ミシェル・ピコリ演じる顔に痣のある男との会話にこんな下りがあった。
「昔カメラは人の頭より重たかった。今ではそれは、目に見えないほど小さい」)
だから喰いちぎられた指も、娘(どことなく面影が似てなくもない)も、殺されて・死んでゆく男も<演技>に違いない。
(「我々は死ぬことはできない」)
死んでゆく者が<役柄を演じているオスカー>ならば、それは役柄の死であり、
オスカーの死ではない。
でも…それにしても…や、もしかしたらこれはオスカーの脳内で繰り広げられた
幻想?そういうオチ?
(早速オチを予測しはじめる悪い癖w)
しかしその後登場するカイリー・ミノーグ演じる女の顛末によって、私の楽観的予測
は根底から揺さぶられる。
オスカーが演じているのは、本当に<役柄>なんだろうか?
それにしては彼の24時間にはあまりに自分自身に戻る瞬間が無さ過ぎる。
朝起きてから夜眠るまで。
これはまるで…オスカーの人生そのものが<役を演じること>じゃないか?
たぶん冒頭の映画館のシーンが暗示するように、カラックスという人は映画に
取り憑かれているんだろう。
自分自身の生活の全ての、根っこの部分が映画というシロモノに繋がっていて。
例えば恋人と一緒でもつい、「ここはこの角度から…こんな光の感じで」なんて。
その魔力に取り憑かれ、歩いていても、食事していても、眠っているときでさえも、目はカメラになり、自分と周りで起きる事全てが誰かのシナリオだと感じてしまう。
演じること=映画を撮ること→生きること
オスカーを演じるドニ・ラヴァンが監督の分身だってこともあり、今のところ
私はそうなんじゃないかなと思っている。
見方によっては、場面ごとに違う自分を演じわけ、調子良く生きてるつもりが
自分を見失い、生死の実感をも失いつつある現代人への皮肉とも解釈できるかも。
しかしそんな解釈はありきたり過ぎるし少々乱暴だと感じてしまう位、デリケートで物悲しくて、真摯で綺麗な映像だった。
こういう映画を好んで見る人はどっちかというと少数派だと思うし、
正直ラストシーンはいかがなものか?と思うし、
やたら謎かけが多いけど一つとして回収されないので、スッキリしないし。
でもそれでもみた後に「あ、これ好きだなぁ…。」と思って、翌日もその次も、
暫くの間はあれこれ考えてみたくなる作品です。
http://www.holymotors.jp
映画紹介
http://eiga.com/extra/kuriko/9/
冒頭薄暗い狭い部屋のベッドで眠る男と犬。
どうやら船室らしい。というのも、波と船体が軋む音、カモメの声が聞こえるから。
灰色の髪にサングラスの男は起き上がり、不思議な鍵で壁の隠し扉を開く。
暗い通路を通って男が現れたのは映画館の映写室の前のバルコニー。
そこで私は、そこが船室でなく映画館の隠し部屋(そんなものがあるなら)と知る。
観客席にカメラが向き、皆真剣にスクリーンを見ている、そして波とカモメの声。
このサングラスの男こそ、この作品の監督レオス・カラックスで、一見意味不明な
冒頭のシーンが、映画を見るうちにひとつのキーワードなんだと気づく。
突然画面は切り替わって、パリ郊外の豪華客船を思わせるモダンな邸宅と家族、
そこから出勤する初老の男・オスカーを映す。
馬鹿でかい白いリムジンに映画スターのように乗り込む男。
その顔はどちらかというとチンパンジーみたいでお世辞にも男前でなく、しかし
彼の持つ独特の空気感に不思議な深みを感じる。
この俳優=ドニ・ラヴァンはカラックス作品の常連というか、監督の分身のような
存在で、ボーイ・ミーツ・ガールから私の見た作品全てに登場していた。
(ポーラXとオムニバス短編は見てないのですが)
家族から送り出されたときは大企業の社長といった出で立ちの彼は、車内で手早く
カツラを外しメイクを取り服を着替え、禿の異形の男になる。
つまり、豪邸も家族も何もかもが<セット>に過ぎなかったのだ。
彼の仕事はファイルで依頼された人物になりきり、指定された場所でその役柄を演じきること。
リムジンの中はちょうど俳優のメイクルームのようにカツラ、小道具、特殊メイク用の素材、衣装、がぎっしりで、彼はそこで指示通りの人物になり切る。
年老いた物乞いの女、CG映像の人物モデル、墓から出てきた怪物のような男(BGMがゴジラw)、思春期の娘の悩みを真摯に受け止める父親、殺人犯、暗殺者、ストリートミュージシャン、死を目前に、美しい姪に心情を吐露する金持ちの老人。
パートタイムで姿も人格もどんどん変わって行く彼の、ある一日。
リムジンを運転するのは元ダンサーだという50代の美しい女、セリーヌ。
リムジンの中でメイクを落とし衣装を脱いだ時だけが、オスカーの本来の姿。
誰が何のためにオスカーに<役を演じる>ことを依頼しているのか?
全く説明もなく、刻々と姿を、人格を変化させるオスカーを、カメラはドラマチックに映し出す。
異形の怪人の姿で雑誌のグラビア撮影中のスーパーモデルを誘拐し、カメラマン助手の女の指を喰いちぎり、殺人者になって倉庫係の男をナイフで殺害し、(しかも
殺された男の顔もオスカー自身)、普通の父親の姿でパーティに参加した内気な娘を迎えに行く。
私は考える。
オスカーはパートタイムの映画俳優の設定なのかもしれない。
画面には映らないけれど、どこかで極小サイズのカメラが回ってるに違いない。
その、オスカーを主人公にした様々な映画のメイキングを見ているんだ。
(ミシェル・ピコリ演じる顔に痣のある男との会話にこんな下りがあった。
「昔カメラは人の頭より重たかった。今ではそれは、目に見えないほど小さい」)
だから喰いちぎられた指も、娘(どことなく面影が似てなくもない)も、殺されて・死んでゆく男も<演技>に違いない。
(「我々は死ぬことはできない」)
死んでゆく者が<役柄を演じているオスカー>ならば、それは役柄の死であり、
オスカーの死ではない。
でも…それにしても…や、もしかしたらこれはオスカーの脳内で繰り広げられた
幻想?そういうオチ?
(早速オチを予測しはじめる悪い癖w)
しかしその後登場するカイリー・ミノーグ演じる女の顛末によって、私の楽観的予測
は根底から揺さぶられる。
オスカーが演じているのは、本当に<役柄>なんだろうか?
それにしては彼の24時間にはあまりに自分自身に戻る瞬間が無さ過ぎる。
朝起きてから夜眠るまで。
これはまるで…オスカーの人生そのものが<役を演じること>じゃないか?
たぶん冒頭の映画館のシーンが暗示するように、カラックスという人は映画に
取り憑かれているんだろう。
自分自身の生活の全ての、根っこの部分が映画というシロモノに繋がっていて。
例えば恋人と一緒でもつい、「ここはこの角度から…こんな光の感じで」なんて。
その魔力に取り憑かれ、歩いていても、食事していても、眠っているときでさえも、目はカメラになり、自分と周りで起きる事全てが誰かのシナリオだと感じてしまう。
演じること=映画を撮ること→生きること
オスカーを演じるドニ・ラヴァンが監督の分身だってこともあり、今のところ
私はそうなんじゃないかなと思っている。
見方によっては、場面ごとに違う自分を演じわけ、調子良く生きてるつもりが
自分を見失い、生死の実感をも失いつつある現代人への皮肉とも解釈できるかも。
しかしそんな解釈はありきたり過ぎるし少々乱暴だと感じてしまう位、デリケートで物悲しくて、真摯で綺麗な映像だった。
こういう映画を好んで見る人はどっちかというと少数派だと思うし、
正直ラストシーンはいかがなものか?と思うし、
やたら謎かけが多いけど一つとして回収されないので、スッキリしないし。
でもそれでもみた後に「あ、これ好きだなぁ…。」と思って、翌日もその次も、
暫くの間はあれこれ考えてみたくなる作品です。
アルゴ(編集しました)
2013年4月1日 映画 コメント (2)
すっごく面白かった。
1979年。
革命で反米感情最高潮のイラク国内から、
厳重な監視の目をかいくぐり、
アメリカ大使館員を奪還した
CIA工作員による救出劇の真相。
亡命したパーレビー国王を匿っているアメリカへの
イラン国民の憎悪は凄まじく、
アメリカ人だとわかったらリンチされかねない状況の中、
どうやって6名を国外へ脱出させるのか?
架空のSF映画製作をでっち上げ、カナダ人のロケハンスタッフに偽装して
連れ出すという奇想天外な計画で見事に成功するんですけど、
イラン国内の映像パートでは手持ちカメラで撮影したみたいに粒子が粗く、
色調が少しブルーグレイに調整してあるのがいかにもドキュメンタリーっぽい。
(注:一部実際の映像を使用しているそうです)
一方、CIA本部やでっち上げ映画製作中のハリウッドのスタジオのパートでは
ちょっと昔のアメリカのTVドラマ風。
イランとアメリカで映像の色調や質感を微妙に変えて、交互に切り替えながら
見せてるのが本当に上手い。
コントラストつけてるから、変化に富んで飽きないんだよね。
アメリカ政府の政治的建前に翻弄される現場のCIA工作員。
その彼が仕掛ける計画がハリウッド映画のロケハン。
それは、自由民主主義の番人を自認し、他国への介入をも辞さないアメリカと、
世界のエンターテイメント工場としての二つの顔を象徴しているようにも見える。
また、作品自体もシビアなドキュメンタリー作品の側面を持ちながら、
エンターテイメントとしても成功していて、これも二面性がある。
仮に日本で同様の作品を制作する場合、どうだろう?
ドキュメンタリーとエンターテイメントをバランス良く両立させるのってかなり
ハードル高いんじゃないかなぁ…。
こういう作品を見ると底力の違いを痛感させられます。
ベン・アフレック監督作品を見るのは初めてだけど、魅せるなぁ。
特典映像で実際の関係者インタビューを見たんだけど、映画として面白くするため
どの辺りを脚色したのかよくわかる。
もちろん実際はそこまでドラマチックだったわけじゃないんだなと(笑)
これ、ジョージ・クルーニーも制作に関わってるんだよね。
面白い作品をありがとう!
ベンとジョージに感謝☆
いや〜…映画館で見ればよかった!(今更w)
1979年。
革命で反米感情最高潮のイラク国内から、
厳重な監視の目をかいくぐり、
アメリカ大使館員を奪還した
CIA工作員による救出劇の真相。
亡命したパーレビー国王を匿っているアメリカへの
イラン国民の憎悪は凄まじく、
アメリカ人だとわかったらリンチされかねない状況の中、
どうやって6名を国外へ脱出させるのか?
架空のSF映画製作をでっち上げ、カナダ人のロケハンスタッフに偽装して
連れ出すという奇想天外な計画で見事に成功するんですけど、
イラン国内の映像パートでは手持ちカメラで撮影したみたいに粒子が粗く、
色調が少しブルーグレイに調整してあるのがいかにもドキュメンタリーっぽい。
(注:一部実際の映像を使用しているそうです)
一方、CIA本部やでっち上げ映画製作中のハリウッドのスタジオのパートでは
ちょっと昔のアメリカのTVドラマ風。
イランとアメリカで映像の色調や質感を微妙に変えて、交互に切り替えながら
見せてるのが本当に上手い。
コントラストつけてるから、変化に富んで飽きないんだよね。
アメリカ政府の政治的建前に翻弄される現場のCIA工作員。
その彼が仕掛ける計画がハリウッド映画のロケハン。
それは、自由民主主義の番人を自認し、他国への介入をも辞さないアメリカと、
世界のエンターテイメント工場としての二つの顔を象徴しているようにも見える。
また、作品自体もシビアなドキュメンタリー作品の側面を持ちながら、
エンターテイメントとしても成功していて、これも二面性がある。
仮に日本で同様の作品を制作する場合、どうだろう?
ドキュメンタリーとエンターテイメントをバランス良く両立させるのってかなり
ハードル高いんじゃないかなぁ…。
こういう作品を見ると底力の違いを痛感させられます。
ベン・アフレック監督作品を見るのは初めてだけど、魅せるなぁ。
特典映像で実際の関係者インタビューを見たんだけど、映画として面白くするため
どの辺りを脚色したのかよくわかる。
もちろん実際はそこまでドラマチックだったわけじゃないんだなと(笑)
これ、ジョージ・クルーニーも制作に関わってるんだよね。
面白い作品をありがとう!
ベンとジョージに感謝☆
いや〜…映画館で見ればよかった!(今更w)
http://www.lesmiserables-movie.jp
TVで予告も見たし、インタビューでのヒュー・ジャックマンのキュートさ(笑)に
素敵な男性だなぁ…と思いつつ、実は見に行くつもりじゃなかったのですが…。
気がついたら涙が溢れてる、という体験をしてしまった。
ジャン・バルジャンが、ファンテーヌが、画面いっぱいの超クローズアップで歌う。
奥底からわき上がる感情の昂りのまま、全てを<声>に注ぎ込み爆発させる。
天上世界から人々のちっぽけな営みを見下ろしているであろう、神という存在に
向かって、愛と怒りと悲しみと喜びと希望と絶望を訴えかける。
歌より祈りに近いもの。
ドラマティックで壮大な音楽と相まって、考えるより先に感情の渦に引き込まれ、
翻弄される感覚。
台詞(ここでは歌詞ですが)や役者の演技に心が動いて感動する、というのとは
また別次元で…
むしろ思考を飛び越え、見る者を演じる者の感覚の磁場に一瞬で引き込んでしまう
力技、とでもいいますか。
もちろんそういう作品ですから<声>のよい役者さんばかりです。
ジャン・バルジャンとファンテーヌのソロシーンの歌声は素晴らしかったですし、
ジャベールの深みのある声質はとってもセクシーですし。
個人的に一番「凄い!」と思ったのは、エポニーヌ役のサマンサ・バークスかな。
囁も、朗々と力強く歌い上げる声も自由自在で、しかも色気がある。
片思いの相手を陰から見守りつつ、雨に打たれながら切々と歌い上げる胸の内。
そして、革命の歌やラスト大団円の壮大な合唱のシーンは、声のパワーで体が
ぐぐっと押されるような錯覚すらありました。
映像も個性的でした。
初っ端の、嵐の中でガレー船を人力で引き上げるシーン。
CGでしかあり得ないカメラワークなんですが、空の高い位置から一気に下降し、
傾いた舟のマストから舳先を掠めて地上すれすれに舞い降りて、悲惨な囚人たち
ひとりひとりの絶望に満ちた表情を見せる。
そこから一気にジャン・バルジャンの仮釈放、フランスの険しい山岳地帯の彷徨、
キャンドルで効果的に彩られた、美しく厳かな教会の内部のシーンへ。
手前から奥へ、奥から手前へ、ヒュー・ジャックマンが歌いながら移動するのを、
正面から目の高さのカメラでずーっと撮っている。
すると丁度、3Dで登場人物がこっちへ飛び出してくるような感覚なんです。
更に役者さんの見せ場、ソロで歌い上げるシーンは、ほぼバストアップでカメラを固定してるので、一人の役者さんにスポットライトが当たっている感じ。
舞台でのお芝居をかぶりつきで見ている感覚を狙ったんじゃないでしょうか。
ミュージカル映画なのでしょうけれど、今まで見てきたものとはまた違う。
音といい映像といい、素材は極オーソドックスですが、見せ方はかなり計算して
面白いものを作っているなぁという印象です。
音も映像も、一般家庭のTVだとあの迫力を十分に発揮できないんじゃないかな。
大スクリーンで、出来るだけ音響のよい映画館で見るべき作品かと思います。
TVで予告も見たし、インタビューでのヒュー・ジャックマンのキュートさ(笑)に
素敵な男性だなぁ…と思いつつ、実は見に行くつもりじゃなかったのですが…。
気がついたら涙が溢れてる、という体験をしてしまった。
ジャン・バルジャンが、ファンテーヌが、画面いっぱいの超クローズアップで歌う。
奥底からわき上がる感情の昂りのまま、全てを<声>に注ぎ込み爆発させる。
天上世界から人々のちっぽけな営みを見下ろしているであろう、神という存在に
向かって、愛と怒りと悲しみと喜びと希望と絶望を訴えかける。
歌より祈りに近いもの。
ドラマティックで壮大な音楽と相まって、考えるより先に感情の渦に引き込まれ、
翻弄される感覚。
台詞(ここでは歌詞ですが)や役者の演技に心が動いて感動する、というのとは
また別次元で…
むしろ思考を飛び越え、見る者を演じる者の感覚の磁場に一瞬で引き込んでしまう
力技、とでもいいますか。
もちろんそういう作品ですから<声>のよい役者さんばかりです。
ジャン・バルジャンとファンテーヌのソロシーンの歌声は素晴らしかったですし、
ジャベールの深みのある声質はとってもセクシーですし。
個人的に一番「凄い!」と思ったのは、エポニーヌ役のサマンサ・バークスかな。
囁も、朗々と力強く歌い上げる声も自由自在で、しかも色気がある。
片思いの相手を陰から見守りつつ、雨に打たれながら切々と歌い上げる胸の内。
そして、革命の歌やラスト大団円の壮大な合唱のシーンは、声のパワーで体が
ぐぐっと押されるような錯覚すらありました。
映像も個性的でした。
初っ端の、嵐の中でガレー船を人力で引き上げるシーン。
CGでしかあり得ないカメラワークなんですが、空の高い位置から一気に下降し、
傾いた舟のマストから舳先を掠めて地上すれすれに舞い降りて、悲惨な囚人たち
ひとりひとりの絶望に満ちた表情を見せる。
そこから一気にジャン・バルジャンの仮釈放、フランスの険しい山岳地帯の彷徨、
キャンドルで効果的に彩られた、美しく厳かな教会の内部のシーンへ。
手前から奥へ、奥から手前へ、ヒュー・ジャックマンが歌いながら移動するのを、
正面から目の高さのカメラでずーっと撮っている。
すると丁度、3Dで登場人物がこっちへ飛び出してくるような感覚なんです。
更に役者さんの見せ場、ソロで歌い上げるシーンは、ほぼバストアップでカメラを固定してるので、一人の役者さんにスポットライトが当たっている感じ。
舞台でのお芝居をかぶりつきで見ている感覚を狙ったんじゃないでしょうか。
ミュージカル映画なのでしょうけれど、今まで見てきたものとはまた違う。
音といい映像といい、素材は極オーソドックスですが、見せ方はかなり計算して
面白いものを作っているなぁという印象です。
音も映像も、一般家庭のTVだとあの迫力を十分に発揮できないんじゃないかな。
大スクリーンで、出来るだけ音響のよい映画館で見るべき作品かと思います。
KOTOKO 【DVD】
2013年1月19日 映画
他の大多数の人と同じようには生きていけない人がいる。
歌やダンスや美しいものへの素晴らしい才能を持ちながら、
外から入って来る情報を上手くコントロールできなかったり、
特に他の<人間>が発する敵意の無いコミュニケーションすら
突然の暴力に感じてしまうような女性=kotoko。
そんな彼女が授かった赤ちゃんをたった一人で育てようとして
直面する苦痛と恐怖。
kotokoの暮らす小さな部屋はきれいなライトやテキスタイル、
赤ちゃん向けの玩具や手作りのインテリアで飾り付けられ、二人っきりで
そこに止まる限り危険は無い。
しかし生きていくために彼女は否応なく<他者>との関わりを強制され、少しずつ
精神のバランスを崩していく。
とても痛々しい映画でした。
神経症を抱え日常的にリストカットを行い、下心を持って近づく男の手にフォークを
突き立てるkotokoが、彼女を演じたcoccoそのものとしか思えないこともあり、
もちろん虚構の世界なんですが、演者と役柄が近過ぎて、見てる私もフィクションなのかノンフィクションなのか、分からなくなる瞬間が何度もありました。
天使のように可愛らしい健康的な男の赤ちゃんを、骨と皮にやせ衰えた腕に抱え、
たった一人で<外界>と格闘する彼女の姿は、常に不安定に揺れ動くカメラと雑音でさらに強調され、ある種の狂気を感じさせるのですが…。
自分の生んだ子供への執拗な愛着と、不慮の事故で子供を失うのではないか?
という根拠の無い不安。
その一方で、自分が産んだ子であるけれど彼は絶対的な他者である、という認識からくる漠然とした違和感。
あまりにもリアルで、その感覚はkotokoの逸脱のせいで決して一般的なものではない…とは、わたしには思えなかった。
幼児虐待の理由はそれぞれあるでしょうけれど、ある方向からギリギリのところまで
その心理に近づいたのかもしれません。
見る人を選ぶ映画ですけれど、見る価値のある作品です。
kotoko=coccoがアカペラで歌い・踊るシーンがあるのですが、素晴らしいの一言。
伸びやかで透明感のある歌声を、全身から発する彼女はとても魅力的。
痛々しくグロテスクではあるものの、その存在感が全てを浄化していた気がします。
彼女の故郷である南国のシーンは、まるで時の止まったパラダイスのようでした。
ただ、個人的に「これは入れて欲しくなかった・・・。」と思う部分があります。
塚本監督自身が演じる田中の、血まみれシーン。
kotokoと田中の歪んだ愛情関係を暗示する為とは思うのですが、やりすぎ。
人体破壊や変形は塚本監督<らしさ>でしょうし、ある種のファンサービスなのかもしれませんけど…どうしてもあざとい感じが残ってしまって後味が悪いです。
もしかして海外の映画賞を意識した?なぁんて意地悪かつ下世話な想像が(苦笑)
ああいう露悪趣味って作品の邪魔をしてるほうが多いような気がしますが…。
DVDのジャケットにもなっているラスト近くのシーンはとても美しい。
雨に打たれ、この世の者とは思えないほどでした。
歌やダンスや美しいものへの素晴らしい才能を持ちながら、
外から入って来る情報を上手くコントロールできなかったり、
特に他の<人間>が発する敵意の無いコミュニケーションすら
突然の暴力に感じてしまうような女性=kotoko。
そんな彼女が授かった赤ちゃんをたった一人で育てようとして
直面する苦痛と恐怖。
kotokoの暮らす小さな部屋はきれいなライトやテキスタイル、
赤ちゃん向けの玩具や手作りのインテリアで飾り付けられ、二人っきりで
そこに止まる限り危険は無い。
しかし生きていくために彼女は否応なく<他者>との関わりを強制され、少しずつ
精神のバランスを崩していく。
とても痛々しい映画でした。
神経症を抱え日常的にリストカットを行い、下心を持って近づく男の手にフォークを
突き立てるkotokoが、彼女を演じたcoccoそのものとしか思えないこともあり、
もちろん虚構の世界なんですが、演者と役柄が近過ぎて、見てる私もフィクションなのかノンフィクションなのか、分からなくなる瞬間が何度もありました。
天使のように可愛らしい健康的な男の赤ちゃんを、骨と皮にやせ衰えた腕に抱え、
たった一人で<外界>と格闘する彼女の姿は、常に不安定に揺れ動くカメラと雑音でさらに強調され、ある種の狂気を感じさせるのですが…。
自分の生んだ子供への執拗な愛着と、不慮の事故で子供を失うのではないか?
という根拠の無い不安。
その一方で、自分が産んだ子であるけれど彼は絶対的な他者である、という認識からくる漠然とした違和感。
あまりにもリアルで、その感覚はkotokoの逸脱のせいで決して一般的なものではない…とは、わたしには思えなかった。
幼児虐待の理由はそれぞれあるでしょうけれど、ある方向からギリギリのところまで
その心理に近づいたのかもしれません。
見る人を選ぶ映画ですけれど、見る価値のある作品です。
kotoko=coccoがアカペラで歌い・踊るシーンがあるのですが、素晴らしいの一言。
伸びやかで透明感のある歌声を、全身から発する彼女はとても魅力的。
痛々しくグロテスクではあるものの、その存在感が全てを浄化していた気がします。
彼女の故郷である南国のシーンは、まるで時の止まったパラダイスのようでした。
ただ、個人的に「これは入れて欲しくなかった・・・。」と思う部分があります。
塚本監督自身が演じる田中の、血まみれシーン。
kotokoと田中の歪んだ愛情関係を暗示する為とは思うのですが、やりすぎ。
人体破壊や変形は塚本監督<らしさ>でしょうし、ある種のファンサービスなのかもしれませんけど…どうしてもあざとい感じが残ってしまって後味が悪いです。
もしかして海外の映画賞を意識した?なぁんて意地悪かつ下世話な想像が(苦笑)
ああいう露悪趣味って作品の邪魔をしてるほうが多いような気がしますが…。
DVDのジャケットにもなっているラスト近くのシーンはとても美しい。
雨に打たれ、この世の者とは思えないほどでした。
インファナル・アフェア [DVD]
2012年10月31日 映画
ダブルフェイス、面白そうだったんですが見逃しちゃったんですよねー…。
年末か年始に再放送されるそうなので、絶対見なければ。
と、ふと。
この元ネタとなった作品をまだ見てないことに気づく。
早速TSUTAYAへ行ったら案の定貸し出し中…一週間待って
ようやく借りられました。
潜入捜査官として香港マフィアの組織で密かに活動するヤン。
警察の人間でありながら、マフィアに情報を漏らすラウ。
組織の中で敵側のイヌとして生きる二人の男の運命の交錯。
ちょっとレザボアドッグスを思い出しましたが、レザボアドッグスは個性豊かな
犯罪者個人の心理描写に主眼を置いた作品。
こちらは組織の中の異物である人間を描いた作品でどちらかというと刑事物っぽい
印象。
流血描写や暴力描写もレザボアドッグスより大人しめで見やすかったです。
B級映画の香りが漂ってるんですが、設定がいいですし、ストーリーが面白い。
そして。
何と言ってもトニー・レオンですよ!
この映画のなんとも言えないやるせない哀愁はトニー・レオンが居たからこそ。
あの独特の湿り気のある視線や寂しげで子犬のような目と笑顔がたまりません。
彼と密かに心を通わせるカウンセラーの美女。
ヤンが彼女に残すメモの言葉…
「俺の秘密を覚えておいて、さようなら。」
格好良すぎるだろう!!!!!
マフィアの麻薬取引の情報を刻一刻と警察側に連絡する手段が、なんと古風にも
モールス信号ってのもいい。
ケータイ、パソコンを駆使しながら、肝心なところはモールス信号。
犯罪を犯すのも人なら検挙し裁くのも人。
ラスト近く、寂れたビルの屋上でラウの頭に拳銃を突きつけるヤン。
「俺は警官に戻りたい。」
しかし彼が戻りたい警察組織も既に内側から喰い荒らされ、腐敗しつつある。
行くも地獄、戻るも地獄。
それが分かっていても人は「居るべき場所」を求めるのだろうか。
中国語のタイトルは「無間道」
死ぬ事もできず永遠に苦しみから逃れられない地獄の呼称だそう。
一度犯罪に手を染めた者は二度と元の世界へは戻れない。
ヤンとラウ。
フィルムのポジとネガのような二人が堕ちた世界…。
年末か年始に再放送されるそうなので、絶対見なければ。
と、ふと。
この元ネタとなった作品をまだ見てないことに気づく。
早速TSUTAYAへ行ったら案の定貸し出し中…一週間待って
ようやく借りられました。
潜入捜査官として香港マフィアの組織で密かに活動するヤン。
警察の人間でありながら、マフィアに情報を漏らすラウ。
組織の中で敵側のイヌとして生きる二人の男の運命の交錯。
ちょっとレザボアドッグスを思い出しましたが、レザボアドッグスは個性豊かな
犯罪者個人の心理描写に主眼を置いた作品。
こちらは組織の中の異物である人間を描いた作品でどちらかというと刑事物っぽい
印象。
流血描写や暴力描写もレザボアドッグスより大人しめで見やすかったです。
B級映画の香りが漂ってるんですが、設定がいいですし、ストーリーが面白い。
そして。
何と言ってもトニー・レオンですよ!
この映画のなんとも言えないやるせない哀愁はトニー・レオンが居たからこそ。
あの独特の湿り気のある視線や寂しげで子犬のような目と笑顔がたまりません。
彼と密かに心を通わせるカウンセラーの美女。
ヤンが彼女に残すメモの言葉…
「俺の秘密を覚えておいて、さようなら。」
格好良すぎるだろう!!!!!
マフィアの麻薬取引の情報を刻一刻と警察側に連絡する手段が、なんと古風にも
モールス信号ってのもいい。
ケータイ、パソコンを駆使しながら、肝心なところはモールス信号。
犯罪を犯すのも人なら検挙し裁くのも人。
ラスト近く、寂れたビルの屋上でラウの頭に拳銃を突きつけるヤン。
「俺は警官に戻りたい。」
しかし彼が戻りたい警察組織も既に内側から喰い荒らされ、腐敗しつつある。
行くも地獄、戻るも地獄。
それが分かっていても人は「居るべき場所」を求めるのだろうか。
中国語のタイトルは「無間道」
死ぬ事もできず永遠に苦しみから逃れられない地獄の呼称だそう。
一度犯罪に手を染めた者は二度と元の世界へは戻れない。
ヤンとラウ。
フィルムのポジとネガのような二人が堕ちた世界…。
キナタイ マニラ・アンダーグラウンド [DVD]
2012年9月15日 映画
カンヌで監督賞を穫ったフィリピンの新進気鋭監督の作品。
マニラの夜。
暴力が支配する暗黒の世界にはからずも足を踏み入れてしまった
新婚青年の悪夢。
壮絶なリンチシーン&スプラッター有。
注:血と暴力が苦手な方は絶対見ちゃいけません。
アジア、フィリピン、マニラ。
犯罪と暴力とごく親しい場所で生きる日常の暗黒面の描写という点では、『Cyclo』
にも通じるかな…ただ、トラン・アン・ユンのような映像美や詩的イメージまで
高められたエロティシズムの描写はここには無い。
『ICWR』の詩的で美しい側面を全て切り捨てた感じ…で当たらずとも遠からず。
18歳の妻。6ヶ月の息子。結婚式を挙げたばかりの20歳の警察学校に通う青年。
その青年が小銭稼ぎに麻薬売買に手を染めてるってのがまず驚き。
さらにギャングと一晩行動を共にし、陰惨な殺害現場に居合せながらも右往左往し、
直接手は下さないまでも結局は何もできないまま、犯罪を幇助してしまう。
ギャングのボスの言葉…
「お前、警官になるのか?それだけじゃ喰えねえよ。」
頷く青年。
日本でも警察関係者の汚職や犯罪が度々問題になっていますが、
そんなの比じゃありません。
出口なし。少し気を緩めれば小さな綻びからあっという間に滑り落ち、底なし沼に
堕ちていく闇の世界。
けばけばしい風俗関係の店が並ぶマニラ市内のネオン街から、ギャングと拉致された
ジャンキーの娼婦(犠牲者)とワゴン車に密閉されたまま、ほとんど街灯もない
郊外の深い闇の世界へ。
何度もすれ違うパトカー。しかし車内で何が起きてるか誰も気づかない。
タイトルの<キナタイ>はタガログ語で<屠殺>だそうですが、夜の食肉加工所前を通過するシーンがあり、血も凍る展開を想像してゾッとしました。
この辺りのなんとも言えない恐怖。目に見えない、脳内に投影される恐怖。
見たくないのに先が気になってみてしまう、どうしようもないあの感じ。
ただ、それに続く惨殺シーンは、うーん。
汚らしいだけでそんなに衝撃的でもなかったです。
自分の想像力の方が強烈だったのかもしれません(苦笑)
興味深くはありますし、時々手ブレするカメラで撮られた映像はリアリティ満点。
でも正直いって新鮮な驚き=恐怖感ではないです。
人間の堕落していく姿の描写にしても、言ってしまえばありきたりかもしれない。
悪くはないけど、監督賞穫るほどかというと、どうだろう?
カンヌで評価されたアジア映画で最近見たのは『ブンミおじさんの森』ですが、
こちらは映像やテーマの選び方に新鮮味がありましたし…。
でもある時代のある都市の、闇の部分を赤裸裸に描いたのは凄いですし、問題提起の
手段としてはインパクト十分といったところでしょうか。
ちょっと検索してみたのですが、2009年のカンヌ映画祭ってあのラース・フォン・
トリアー監督の『アンチクライスト』やロウ・イエ監督の『スプリングフィーバー』が各賞を受賞してるんですね。
暴力とセックスを扱った作品が目立った年であったのでしょう。
また、『スプリングフィーバー』同様、政府の検閲が入って国内での一般上映禁止処分になったといういわくつき作品でもあります。
その年の審査員のセンスや好みに左右されるカンヌらしいチョイスですね。
ただし、上映会では『アンチクライスト』同様、ブーイングの嵐だったらしいです。
マニラの夜。
暴力が支配する暗黒の世界にはからずも足を踏み入れてしまった
新婚青年の悪夢。
壮絶なリンチシーン&スプラッター有。
注:血と暴力が苦手な方は絶対見ちゃいけません。
アジア、フィリピン、マニラ。
犯罪と暴力とごく親しい場所で生きる日常の暗黒面の描写という点では、『Cyclo』
にも通じるかな…ただ、トラン・アン・ユンのような映像美や詩的イメージまで
高められたエロティシズムの描写はここには無い。
『ICWR』の詩的で美しい側面を全て切り捨てた感じ…で当たらずとも遠からず。
18歳の妻。6ヶ月の息子。結婚式を挙げたばかりの20歳の警察学校に通う青年。
その青年が小銭稼ぎに麻薬売買に手を染めてるってのがまず驚き。
さらにギャングと一晩行動を共にし、陰惨な殺害現場に居合せながらも右往左往し、
直接手は下さないまでも結局は何もできないまま、犯罪を幇助してしまう。
ギャングのボスの言葉…
「お前、警官になるのか?それだけじゃ喰えねえよ。」
頷く青年。
日本でも警察関係者の汚職や犯罪が度々問題になっていますが、
そんなの比じゃありません。
出口なし。少し気を緩めれば小さな綻びからあっという間に滑り落ち、底なし沼に
堕ちていく闇の世界。
けばけばしい風俗関係の店が並ぶマニラ市内のネオン街から、ギャングと拉致された
ジャンキーの娼婦(犠牲者)とワゴン車に密閉されたまま、ほとんど街灯もない
郊外の深い闇の世界へ。
何度もすれ違うパトカー。しかし車内で何が起きてるか誰も気づかない。
タイトルの<キナタイ>はタガログ語で<屠殺>だそうですが、夜の食肉加工所前を通過するシーンがあり、血も凍る展開を想像してゾッとしました。
この辺りのなんとも言えない恐怖。目に見えない、脳内に投影される恐怖。
見たくないのに先が気になってみてしまう、どうしようもないあの感じ。
ただ、それに続く惨殺シーンは、うーん。
汚らしいだけでそんなに衝撃的でもなかったです。
自分の想像力の方が強烈だったのかもしれません(苦笑)
興味深くはありますし、時々手ブレするカメラで撮られた映像はリアリティ満点。
でも正直いって新鮮な驚き=恐怖感ではないです。
人間の堕落していく姿の描写にしても、言ってしまえばありきたりかもしれない。
悪くはないけど、監督賞穫るほどかというと、どうだろう?
カンヌで評価されたアジア映画で最近見たのは『ブンミおじさんの森』ですが、
こちらは映像やテーマの選び方に新鮮味がありましたし…。
でもある時代のある都市の、闇の部分を赤裸裸に描いたのは凄いですし、問題提起の
手段としてはインパクト十分といったところでしょうか。
ちょっと検索してみたのですが、2009年のカンヌ映画祭ってあのラース・フォン・
トリアー監督の『アンチクライスト』やロウ・イエ監督の『スプリングフィーバー』が各賞を受賞してるんですね。
暴力とセックスを扱った作品が目立った年であったのでしょう。
また、『スプリングフィーバー』同様、政府の検閲が入って国内での一般上映禁止処分になったといういわくつき作品でもあります。
その年の審査員のセンスや好みに左右されるカンヌらしいチョイスですね。
ただし、上映会では『アンチクライスト』同様、ブーイングの嵐だったらしいです。
http://saikyo-2.gaga.ne.jp/
強盗の罪で服役を終えたばかりのドリスは、失業手当を貰う為に大富豪の障害者
フィリップの介護の仕事に応募する。
(フランスでは就職面接の不採用通知が3カ所分あると手当が貰えるらしい)
不採用のつもりが何故か採用。
お金も知性も教養もありながら、頸椎損傷で首から下が全く動かせないフィリップと元気とユーモアと健康だけは人一倍だが貧困層で育った元チンピラのドリス。
周囲の誰もが眉をひそめる正反対の2人が、数々のギャップを克服し固い絆で
結ばれていく、というストーリー。
冒頭、スーパーカーみたいな黒塗りの車で警察とカーチェイスを繰り広げる
ドリスとフィリップのシーンから始まる。
ヒゲ面のダニエル・デイ・ルイスをちょっと丸顔にしたような上品なフィリップと
スキンヘッドに黒檀のような肌、白目と歯が美しいドリスの組み合わせ。
危険運転の罪で警察に逮捕されかけるドリス。が、重い身体障害のあるフィリップが
発作で今にも死にそうなお芝居で警察官の目を誤摩化し、パトカーで救急病院へ
先導までさせて、まんまと逃げてしまう。
とても象徴的なシーン。
もしフィリップが障害者でなかったら、警察官はもっとよく状況を調べて
2人を逮捕したはず。
フィリップは自家用ジェットを所有し、芸術的造詣が深く、素晴らしい邸宅に
大勢の使用人のいる暮らしぶり。
しかしパラグライダーの事故による全身麻痺で自分では何一つできない現状が
彼をいら立たせ、気難しく扱い辛くしている。
彼の元へやって来る介護士は皆、介護のエキスパートであるがゆえに患者として
<腫れ物に触るように>彼に接する。
ドリスははなっから介護士になろうなんて思ってもないし、介護の知識も技術もなくましてやお金も教養もない。
フィリップの全身麻痺なんておかまいなしで極ふつうに接し、時には障害をジョークにして笑い飛ばす。
陽気で無邪気でノリがよくて屈託のない態度は、フィリップと周囲の人々の気持ちを徐々に解していく。
重い障害者であるフィリップは、<健常者>と区別して扱われ、ある意味社会から
隔てられた存在。
そして貧困層出身のドリスもまた底辺の存在であり、まっとうな社会生活から
落ちこぼれた存在。
フィリップとドリスのあり方は、見えているようで見えてない(または、見ないようにしている)社会の中のギャップを意識させてくれる。
同時に、そのギャップを<存在しないもの>であるかのように振る舞うことと
<過剰に意識すること>とは、同じくらい誰かの生き方を邪魔しているかもしれないと気づく。
あなたとわたしは全然別の人間である。
どう違うかは実際のところ接してみないと分からない。
違う者同士がコミュニケーションすれば、そこに共感と違和感が生じる。
その両方を楽しんでしまうのが一番大事なのかも。
…と、そんなことを考えた。
音楽がとてもいい。
バッハやヴィヴァルディのクラシックが効果的に使われていたけど、
Earth ,Wind&Fireの曲が使われた2つのシーンがどちらも最高にカッコよくて、
ハッピーになる。
冒頭のカーチェイス。
ドリスがこれを大音響で響かせながら大声で歌う。
『September』
http://www.youtube.com/watch?v=2S8ZrQG0y6g&feature=related
フィリップの誕生パーティでこれに合わせて粋なスーツで踊るドリスに惚れ惚れ。
まるで自分もダンスしているかのようなフィリップの表情も最高にいい。
『 Boogie Wonderland』
http://www.youtube.com/watch?v=_jLGa4X5H2c
ドリスのジョークってかなり辛辣なんですよ。
彼が旨そうに食べるマーブルチョコを「わたしにもくれ。」と言うフィリップに
「これは<健常者用>チョコだからあんたにはあげないよw」とドリス。
苦笑いのフィリップ。
にやっとわらってドリスがようやくチョコをフィリップの口に入れる、とか。
フィリップのヒゲを剃るシーンでは、わざと鼻の下にチョビヒゲを残し前髪を水で
濡らしてヒトラー風に作り上げ、「ハイル!」とポーズを取らせる、とか。
(フランスは第二次大戦時ナチス・ドイツに苦しめられた)
…これ、日本映画に置き換えたらどんな感じになるだろうな〜。
フランスでは大ヒットで国民の3人に1人(のべ人数)が見た映画らしいですが、
日本で同様の作品を上映したらどんな反応が返ってくるのかな。
そうそう。
ハリウッドが早速リメイクするそうですよ(苦笑)
強盗の罪で服役を終えたばかりのドリスは、失業手当を貰う為に大富豪の障害者
フィリップの介護の仕事に応募する。
(フランスでは就職面接の不採用通知が3カ所分あると手当が貰えるらしい)
不採用のつもりが何故か採用。
お金も知性も教養もありながら、頸椎損傷で首から下が全く動かせないフィリップと元気とユーモアと健康だけは人一倍だが貧困層で育った元チンピラのドリス。
周囲の誰もが眉をひそめる正反対の2人が、数々のギャップを克服し固い絆で
結ばれていく、というストーリー。
冒頭、スーパーカーみたいな黒塗りの車で警察とカーチェイスを繰り広げる
ドリスとフィリップのシーンから始まる。
ヒゲ面のダニエル・デイ・ルイスをちょっと丸顔にしたような上品なフィリップと
スキンヘッドに黒檀のような肌、白目と歯が美しいドリスの組み合わせ。
危険運転の罪で警察に逮捕されかけるドリス。が、重い身体障害のあるフィリップが
発作で今にも死にそうなお芝居で警察官の目を誤摩化し、パトカーで救急病院へ
先導までさせて、まんまと逃げてしまう。
とても象徴的なシーン。
もしフィリップが障害者でなかったら、警察官はもっとよく状況を調べて
2人を逮捕したはず。
フィリップは自家用ジェットを所有し、芸術的造詣が深く、素晴らしい邸宅に
大勢の使用人のいる暮らしぶり。
しかしパラグライダーの事故による全身麻痺で自分では何一つできない現状が
彼をいら立たせ、気難しく扱い辛くしている。
彼の元へやって来る介護士は皆、介護のエキスパートであるがゆえに患者として
<腫れ物に触るように>彼に接する。
ドリスははなっから介護士になろうなんて思ってもないし、介護の知識も技術もなくましてやお金も教養もない。
フィリップの全身麻痺なんておかまいなしで極ふつうに接し、時には障害をジョークにして笑い飛ばす。
陽気で無邪気でノリがよくて屈託のない態度は、フィリップと周囲の人々の気持ちを徐々に解していく。
重い障害者であるフィリップは、<健常者>と区別して扱われ、ある意味社会から
隔てられた存在。
そして貧困層出身のドリスもまた底辺の存在であり、まっとうな社会生活から
落ちこぼれた存在。
フィリップとドリスのあり方は、見えているようで見えてない(または、見ないようにしている)社会の中のギャップを意識させてくれる。
同時に、そのギャップを<存在しないもの>であるかのように振る舞うことと
<過剰に意識すること>とは、同じくらい誰かの生き方を邪魔しているかもしれないと気づく。
あなたとわたしは全然別の人間である。
どう違うかは実際のところ接してみないと分からない。
違う者同士がコミュニケーションすれば、そこに共感と違和感が生じる。
その両方を楽しんでしまうのが一番大事なのかも。
…と、そんなことを考えた。
音楽がとてもいい。
バッハやヴィヴァルディのクラシックが効果的に使われていたけど、
Earth ,Wind&Fireの曲が使われた2つのシーンがどちらも最高にカッコよくて、
ハッピーになる。
冒頭のカーチェイス。
ドリスがこれを大音響で響かせながら大声で歌う。
『September』
http://www.youtube.com/watch?v=2S8ZrQG0y6g&feature=related
フィリップの誕生パーティでこれに合わせて粋なスーツで踊るドリスに惚れ惚れ。
まるで自分もダンスしているかのようなフィリップの表情も最高にいい。
『 Boogie Wonderland』
http://www.youtube.com/watch?v=_jLGa4X5H2c
ドリスのジョークってかなり辛辣なんですよ。
彼が旨そうに食べるマーブルチョコを「わたしにもくれ。」と言うフィリップに
「これは<健常者用>チョコだからあんたにはあげないよw」とドリス。
苦笑いのフィリップ。
にやっとわらってドリスがようやくチョコをフィリップの口に入れる、とか。
フィリップのヒゲを剃るシーンでは、わざと鼻の下にチョビヒゲを残し前髪を水で
濡らしてヒトラー風に作り上げ、「ハイル!」とポーズを取らせる、とか。
(フランスは第二次大戦時ナチス・ドイツに苦しめられた)
…これ、日本映画に置き換えたらどんな感じになるだろうな〜。
フランスでは大ヒットで国民の3人に1人(のべ人数)が見た映画らしいですが、
日本で同様の作品を上映したらどんな反応が返ってくるのかな。
そうそう。
ハリウッドが早速リメイクするそうですよ(苦笑)
ミレニアム2 火と戯れる女 [DVD]
2012年9月10日 映画
ハリウッド版『ドラゴンタトゥーの女』が面白くて、
急いで2をレンタル。
見終わったら待ちきれずに3をレンタルしてしまいました。
全三部作を見終わって…やっぱり面白い!!!
細かく張られた伏線をきっちり回収して、
更に個々のキャラクターの過去含め
それぞれの人物像がよりくっきりと印象つけられる展開。
練りに練られた物語であることがよくわかります。
ただ『ミレニアム ドラゴンタトゥーの女』と比較すると、
話がより社会的といいますか、政府の陰謀とか策略とかスキャンダルの隠蔽とか、
ちょっとスケールがデカくなった分、当初の淫靡さや禁忌…いわばデカダンスの香りが抑え込まれてしまったのが残念といえば残念。
テイストが違って来てるというか…面白いんですけど、本来作者が描きたかったのは
2&3の世界だったのかも、と。
リスベットとミカエルの2人がタッグを組んで真実を解き明かしていく過程で、
一見まともに見える人間たち(=男)の、パラノイアックで罪深い側面が
浮き彫りにされ、白日の元に晒されて行くというテーマは同じなのですけどね。
圧巻は法廷シーン。
ミカエルの実の妹がリスベットの弁護士、という設定はまぁご愛嬌として、
一見人権派ぶった精神科医と検事の、仮面の下の顔が明らかにされていく過程は
あざといほどのカタストロフでありました(笑)
映画を見て興味をもたれた方、是非こっちのシリーズもチェックをお勧めします。
ハリウッド版のほうのミカエル=ダニエル・クレイグ。
すでに『ドラゴンタトゥーの女3』まで契約書にサインを済ませたってことは、
2も3も制作決定、ってことですよね?
ハリウッドがどんな風に料理するのか…そのアレンジっぷりが今から楽しみです。
正直、個人的にリスベットはハリウッド版のが好みなんですけど@ビジュアルw
その後。
ツレが小説の方を購入。まだ読んでないんですが…。
原作者:スティーグ・ラーソンは既に第5部までの構想を練っていたとか。
彼の突然の死(心筋梗塞らしいです)により、ある意味永遠に未完になった本作。
もし続いていればどんな展開が待ち受けていたのか。
見たいような、見たくないような。
急いで2をレンタル。
見終わったら待ちきれずに3をレンタルしてしまいました。
全三部作を見終わって…やっぱり面白い!!!
細かく張られた伏線をきっちり回収して、
更に個々のキャラクターの過去含め
それぞれの人物像がよりくっきりと印象つけられる展開。
練りに練られた物語であることがよくわかります。
ただ『ミレニアム ドラゴンタトゥーの女』と比較すると、
話がより社会的といいますか、政府の陰謀とか策略とかスキャンダルの隠蔽とか、
ちょっとスケールがデカくなった分、当初の淫靡さや禁忌…いわばデカダンスの香りが抑え込まれてしまったのが残念といえば残念。
テイストが違って来てるというか…面白いんですけど、本来作者が描きたかったのは
2&3の世界だったのかも、と。
リスベットとミカエルの2人がタッグを組んで真実を解き明かしていく過程で、
一見まともに見える人間たち(=男)の、パラノイアックで罪深い側面が
浮き彫りにされ、白日の元に晒されて行くというテーマは同じなのですけどね。
圧巻は法廷シーン。
ミカエルの実の妹がリスベットの弁護士、という設定はまぁご愛嬌として、
一見人権派ぶった精神科医と検事の、仮面の下の顔が明らかにされていく過程は
あざといほどのカタストロフでありました(笑)
映画を見て興味をもたれた方、是非こっちのシリーズもチェックをお勧めします。
ハリウッド版のほうのミカエル=ダニエル・クレイグ。
すでに『ドラゴンタトゥーの女3』まで契約書にサインを済ませたってことは、
2も3も制作決定、ってことですよね?
ハリウッドがどんな風に料理するのか…そのアレンジっぷりが今から楽しみです。
正直、個人的にリスベットはハリウッド版のが好みなんですけど@ビジュアルw
その後。
ツレが小説の方を購入。まだ読んでないんですが…。
原作者:スティーグ・ラーソンは既に第5部までの構想を練っていたとか。
彼の突然の死(心筋梗塞らしいです)により、ある意味永遠に未完になった本作。
もし続いていればどんな展開が待ち受けていたのか。
見たいような、見たくないような。
昨日オンエアされたのを録画で見ました。
かなりご都合主義&楽天的な展開でしたが(笑)最後まで面白く見れてしまったのは
やっぱり役者さんの力でしょう。
原田芳雄さんはじめ個性派&大御所の方々を適材適所に配し、気負い一切なしの
とても<自然な>お芝居。
それぞれの役者さんがいかにも演じそうな役を普通に演じているからこその
安心感の毛布みたいな感触がこの映画の持ち味なんだろうなー。
エンドロールでキヨシローの歌が流れるっつーのもあまりにも<それらしい>けど
やっぱりぴったりの選曲だなぁと思いました。
自分の撮りたいものを、一番ぴったりくる役者さんに演じてもらいながら、撮る。
映画が主に人間を描くものであるとするならば、一番大事なことかもしれない。
そして意外と難しいことだったりするのかもしれない。
原田さん…もう一回キムラと共演して頂きたかったなぁ。
父と息子とかの<優しい>関係じゃない配役で。
今朝はバスも電車も結構混んでました。
世間的にはお盆休みも終わり、夏も終盤というところでしょうけど、
私の夏休みは今週末からです。
かなりご都合主義&楽天的な展開でしたが(笑)最後まで面白く見れてしまったのは
やっぱり役者さんの力でしょう。
原田芳雄さんはじめ個性派&大御所の方々を適材適所に配し、気負い一切なしの
とても<自然な>お芝居。
それぞれの役者さんがいかにも演じそうな役を普通に演じているからこその
安心感の毛布みたいな感触がこの映画の持ち味なんだろうなー。
エンドロールでキヨシローの歌が流れるっつーのもあまりにも<それらしい>けど
やっぱりぴったりの選曲だなぁと思いました。
自分の撮りたいものを、一番ぴったりくる役者さんに演じてもらいながら、撮る。
映画が主に人間を描くものであるとするならば、一番大事なことかもしれない。
そして意外と難しいことだったりするのかもしれない。
原田さん…もう一回キムラと共演して頂きたかったなぁ。
父と息子とかの<優しい>関係じゃない配役で。
今朝はバスも電車も結構混んでました。
世間的にはお盆休みも終わり、夏も終盤というところでしょうけど、
私の夏休みは今週末からです。
ドラゴン・タトゥーの女 [DVD]
2012年8月19日 映画 コメント (2)
映画館で見よう!と決意してたのに結局DVD
… 出不精な自分orz
ちなみにオリジナル版ドラゴンタトゥーの感想。
↓
http://holidaze.diarynote.jp/201008181943283843/
てか、オリジナル版感想日記の日付は2010年8月18日。
ハリウッド版DVD見たのは昨日。ちょうど2年前!!すげぇ偶然!!(聞いてない)
オリジナルが面白かった&監督がD.フィンチャーってことでまずハズレはないだろうと思ってたんですが。
ハリウッド版はオリジナルにほぼ忠実。
で、結論から言いますと、ハリウッド版のがとっつき易いです。(当然です)
トレイラー
http://www.youtube.com/watch?v=BGFNTbw_eLA
オリジナル同様、ナチス・儀式殺人・近親相姦・主人公のトラウマ・過激エチシーン
(モザイク有w)…等々さすがR-15指定だわぁ♪な内容ですが、
主役のリスベットがオリジナルに比べると断然華奢でスタイリッシュで、
どことなくピュアな雰囲気を醸し出しているので、彼女に感情移入しやすい。
一方、雑誌記者ミカエル役がオリンピック開会式で女王陛下をエスコートした
007ことダニエル・クレイグ。素敵系。
これでラブ絡まなかったら嘘だろう!
…ってことで、ちょいと捻った(歪んだ)恋愛絡みのサスペンスとも読める仕掛け。
実際、見てるうちにリスベットの健気さにキュンキュンしちゃいました。
ガリガリに痩せて顔はピアスだらけ、眉もそり落とし、タトゥーだらけのパンク少年みたいな外見なんですけどね。
あと、やっぱり映像が素敵。
フィンチャー監督の作品は照明暗めでモノトーンに近い配色、シンプルで細部まで
計算されつくした映像が独特の雰囲気を醸し出すのですが、
余計なものは映さない・目に入らせない手法は、見てる側の視線と意識を監督が
<見せたいもの>へと誘導するのに最適ではないかと。
また、入る情報が限られるので、細かいディテールに意識が向きやすい。
つまり伏線を理解しないと展開が掴みにくいサスペンスにピッタリ。
更に旧約聖書に基づいた猟奇殺人という発想はまさに『セブン』を彷彿とさせます。
『ドラゴンタトゥー』のリメイクが決まった時点で、プロデューサーの脳裏には
監督=フィンチャーしか浮かばなかったのではないかとすら思いました。
まぁ…『セブン』よりかは百倍あと味のいい映画ですけど(笑)
個人的にはフィンチャー作品の映像って、外科手術の器具を連想するんですよ。
研ぎすまされてムダがなく、一点の曇りもなく清潔でひんやりと冷たく、奇妙な形をしたステンレス製のオブジェ。
どこかフェティッシュな匂いが…たぶん消毒液だな(笑)
音楽はトレント・レズナー。
『ソーシャルネットワーク』でも彼でしたね。
重低音の無機質で冷たいビートが、CG使いまくりのおどろおどろしくもエロチックなオープニングクレジットにピッタリ過ぎでカッコいい。
http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&feature=related
… 出不精な自分orz
ちなみにオリジナル版ドラゴンタトゥーの感想。
↓
http://holidaze.diarynote.jp/201008181943283843/
てか、オリジナル版感想日記の日付は2010年8月18日。
ハリウッド版DVD見たのは昨日。ちょうど2年前!!すげぇ偶然!!(聞いてない)
オリジナルが面白かった&監督がD.フィンチャーってことでまずハズレはないだろうと思ってたんですが。
ハリウッド版はオリジナルにほぼ忠実。
で、結論から言いますと、ハリウッド版のがとっつき易いです。(当然です)
トレイラー
http://www.youtube.com/watch?v=BGFNTbw_eLA
オリジナル同様、ナチス・儀式殺人・近親相姦・主人公のトラウマ・過激エチシーン
(モザイク有w)…等々さすがR-15指定だわぁ♪な内容ですが、
主役のリスベットがオリジナルに比べると断然華奢でスタイリッシュで、
どことなくピュアな雰囲気を醸し出しているので、彼女に感情移入しやすい。
一方、雑誌記者ミカエル役がオリンピック開会式で女王陛下をエスコートした
007ことダニエル・クレイグ。素敵系。
これでラブ絡まなかったら嘘だろう!
…ってことで、ちょいと捻った(歪んだ)恋愛絡みのサスペンスとも読める仕掛け。
実際、見てるうちにリスベットの健気さにキュンキュンしちゃいました。
ガリガリに痩せて顔はピアスだらけ、眉もそり落とし、タトゥーだらけのパンク少年みたいな外見なんですけどね。
あと、やっぱり映像が素敵。
フィンチャー監督の作品は照明暗めでモノトーンに近い配色、シンプルで細部まで
計算されつくした映像が独特の雰囲気を醸し出すのですが、
余計なものは映さない・目に入らせない手法は、見てる側の視線と意識を監督が
<見せたいもの>へと誘導するのに最適ではないかと。
また、入る情報が限られるので、細かいディテールに意識が向きやすい。
つまり伏線を理解しないと展開が掴みにくいサスペンスにピッタリ。
更に旧約聖書に基づいた猟奇殺人という発想はまさに『セブン』を彷彿とさせます。
『ドラゴンタトゥー』のリメイクが決まった時点で、プロデューサーの脳裏には
監督=フィンチャーしか浮かばなかったのではないかとすら思いました。
まぁ…『セブン』よりかは百倍あと味のいい映画ですけど(笑)
個人的にはフィンチャー作品の映像って、外科手術の器具を連想するんですよ。
研ぎすまされてムダがなく、一点の曇りもなく清潔でひんやりと冷たく、奇妙な形をしたステンレス製のオブジェ。
どこかフェティッシュな匂いが…たぶん消毒液だな(笑)
音楽はトレント・レズナー。
『ソーシャルネットワーク』でも彼でしたね。
重低音の無機質で冷たいビートが、CG使いまくりのおどろおどろしくもエロチックなオープニングクレジットにピッタリ過ぎでカッコいい。
http://www.youtube.com/watch?v=mVLJkIZvFlo&feature=related
郵便局員のハーブと図書館司書のドロシー。
慎ましい生活の中で30年かけて2人が集めた
現代アートのコレクション。
選ぶ基準は二つ。
1.自分たちの給料で買える値段であること
2.1LDKのアパートに収まる大きさであること
公式サイト
http://www.herbanddorothy.com/jp/story.html
トレイラー
http://www.herbanddorothy.com/jp/index.html
すっごく可愛いおじいちゃんとおばあちゃんのご夫婦。
2人は若い頃アーティストを志していたのですが、ある日ミニマルアートの作品を
購入したのをきっかけにアートのコレクションにのめり込み、
やがて有名なコレクターとなります。
その2人の軌跡を、当時のフィルムやアーティスト、キュレーター、ディーラーの
証言を交えながら追った作品です。
アートを買う。
正直、お金持ちの道楽って気がしてしまいますが…。
冒頭に紹介したとおり、2人は決して豊かな生活ではありません。
でもアートが大好きで、ギャラリー巡りは当然のこと、アーティスト本人を直接訪ね気に入ったら交渉してどんどん購入していくのです。
そして代わる代わる部屋に飾って楽しむ。
アートが生活の一部となってるのが素敵でした。
しかしアパートの部屋は作品で埋め尽くされ、生活に支障をきたすようになり、
ついに国立現代美術館に寄贈することになります。
売れば結構な値段がつくのに、2人は決して売ろうとしません。
アートはお金儲けの手段ではなく、生活=人生とともにあるものだから、と。
2人はどこに出かけるのも一緒。
相手が誰であろうと自然に振る舞い、率直な意見を述べます。
豊かな経験に裏打ちされた言葉は説得力があり、また時にはアーティストへの
助言にもなる。
「2人はコレクターというよりはキュレーターです。」
と語るアーティストもいましたが、まさにその通りでした。
評価の定まった人の作品を一種のステイタスとして購入するのではなく、
自分の目で見て感じて「これは!」と思ったものを買う。
その姿勢は、わくわくするような純粋な<楽しさ>に満ちていて、素敵でした。
見終わったあとギャラリーに出かけたくなる作品です。
私も実はクートラスのカルトや上田義彦氏の写真を部屋に飾りたいなぁ…
と迷った経験があるので、その意味でちょっと勇気づけられました(笑)
ご主人=ハーブ氏は7/22に89歳でご逝去されたそうです。
ご冥福をお祈りいたします。
映画は続編を制作中だそうで、公開を楽しみにしております。
慎ましい生活の中で30年かけて2人が集めた
現代アートのコレクション。
選ぶ基準は二つ。
1.自分たちの給料で買える値段であること
2.1LDKのアパートに収まる大きさであること
公式サイト
http://www.herbanddorothy.com/jp/story.html
トレイラー
http://www.herbanddorothy.com/jp/index.html
すっごく可愛いおじいちゃんとおばあちゃんのご夫婦。
2人は若い頃アーティストを志していたのですが、ある日ミニマルアートの作品を
購入したのをきっかけにアートのコレクションにのめり込み、
やがて有名なコレクターとなります。
その2人の軌跡を、当時のフィルムやアーティスト、キュレーター、ディーラーの
証言を交えながら追った作品です。
アートを買う。
正直、お金持ちの道楽って気がしてしまいますが…。
冒頭に紹介したとおり、2人は決して豊かな生活ではありません。
でもアートが大好きで、ギャラリー巡りは当然のこと、アーティスト本人を直接訪ね気に入ったら交渉してどんどん購入していくのです。
そして代わる代わる部屋に飾って楽しむ。
アートが生活の一部となってるのが素敵でした。
しかしアパートの部屋は作品で埋め尽くされ、生活に支障をきたすようになり、
ついに国立現代美術館に寄贈することになります。
売れば結構な値段がつくのに、2人は決して売ろうとしません。
アートはお金儲けの手段ではなく、生活=人生とともにあるものだから、と。
2人はどこに出かけるのも一緒。
相手が誰であろうと自然に振る舞い、率直な意見を述べます。
豊かな経験に裏打ちされた言葉は説得力があり、また時にはアーティストへの
助言にもなる。
「2人はコレクターというよりはキュレーターです。」
と語るアーティストもいましたが、まさにその通りでした。
評価の定まった人の作品を一種のステイタスとして購入するのではなく、
自分の目で見て感じて「これは!」と思ったものを買う。
その姿勢は、わくわくするような純粋な<楽しさ>に満ちていて、素敵でした。
見終わったあとギャラリーに出かけたくなる作品です。
私も実はクートラスのカルトや上田義彦氏の写真を部屋に飾りたいなぁ…
と迷った経験があるので、その意味でちょっと勇気づけられました(笑)
ご主人=ハーブ氏は7/22に89歳でご逝去されたそうです。
ご冥福をお祈りいたします。
映画は続編を制作中だそうで、公開を楽しみにしております。
DVDで見ました。
http://eiga.com/movie/56359/
実在のエルサレム出身の女性ジャーナリストの
自伝的作品の映画化。
パレスチナ側の人々の目線から描く、
イスラエル占領下の東エルサレム。
私財を投げ打って戦災孤児のための学校を設立したヒンドゥ。
奉公先でレイプされ、家を飛び出してキャバレーのダンサーとなり、優しい男と
結婚したものの、心の傷から自ら死を選ぶナディア。
そのナディアの娘で、ヒンドゥの学校で学ぶミラル。
三人の女の半生を通して、占領下に生きる人々の姿を繊細に描き出しています。
パレスチナ人の土地に強引に入植したイスラエル人。
武力で土地を奪われ、人権を制限されたパレスチナの人々の怒り、屈辱、絶望感が
そこで暮らす人の目線で描かれる。
同時に、好奇心旺盛で美しい娘に育ったミラルの心の目を通して、世界中どんな場所でも普遍的に存在する心の働き…愛や慈しみ、挫折感や失望、憧れ、未来への希望が
ごく当たり前の感覚として描かれてもいる。
占領下のエルサレムの実情は日本人にはなじみの薄いものですが、女性目線で描いたことで、物語に感情移入しやすい。
そのさじ加減がいい。
また、母の自殺、占領下のエルサレムという過酷な環境の中で、ヒンドゥの導きと確かな教育、母の不在を埋めるような深く温かな父の愛情によって、ジャーナリストにまでのぼりつめるミラルの姿は、物語の最後、未来への希望と繋がる。
自ら命を絶った母ナディアと自分で道を切り拓くミラルとの決定的な違いは、
きちんとした教育を受けていたかどうか、なんです。
例えば「愛情と教育の大切さ」って口で言うとどこか白々しく感じますが(私はw)、作品の流れの中で無理なくそれに気づかされました。
それから、ミラルのお父さんが素敵なんですよー。
背が高く、手足もすっと長い彼が温かい腕の中に幼いミラルを抱きしめ、
成長してからも包み込むような目線で娘を見つめ、そっと救いの手を差し伸べる。
特にラスト近く、実の娘ではないミラルを精一杯愛した彼の言葉に涙が…。
ちなみにミラルとは、野に咲く真っ赤な花の名前。
路傍の花と同じ名前の女性。
ミラルはエルサレムの街で普通に見かけるような女の子だ、という意味が
こめられているんでしょうね。
監督は『潜水服は蝶の夢を見る』のジュリアン・シュナーベル。
ユダヤ系の彼がパレスチナ側の目線から描いたことに意義がある。
ただし映像はひたすら美しく、うっとりするような色彩に満ち、陰惨な印象は薄い。
作品が政治的になりすぎることを回避したのかも。
主演は『スラムドッグ$ミリオネア』の女優さん。つまり、インド人。
魅力的だし、自然なお芝居で個人的には好きですが、現地の方が見たら違和感あるんじゃないかなぁ…。
そこがちょっと気になったり(笑)
この作品はアメリカ人の監督さんが撮っていますが、最近アジアや中近東、
中南米が舞台の映画が面白い。
DVDで見た『ペルシャ猫を誰も知らない』というイラン映画も良かったですし。
http://eiga.com/movie/55032/
『ミラル』もですが、テーマを選びやすいのかもしれないな。
その点からいくと、日本やアメリカが舞台の映画が、私小説風かエンタメに偏りがち
なのは仕方ないのかもしれません。
http://eiga.com/movie/56359/
実在のエルサレム出身の女性ジャーナリストの
自伝的作品の映画化。
パレスチナ側の人々の目線から描く、
イスラエル占領下の東エルサレム。
私財を投げ打って戦災孤児のための学校を設立したヒンドゥ。
奉公先でレイプされ、家を飛び出してキャバレーのダンサーとなり、優しい男と
結婚したものの、心の傷から自ら死を選ぶナディア。
そのナディアの娘で、ヒンドゥの学校で学ぶミラル。
三人の女の半生を通して、占領下に生きる人々の姿を繊細に描き出しています。
パレスチナ人の土地に強引に入植したイスラエル人。
武力で土地を奪われ、人権を制限されたパレスチナの人々の怒り、屈辱、絶望感が
そこで暮らす人の目線で描かれる。
同時に、好奇心旺盛で美しい娘に育ったミラルの心の目を通して、世界中どんな場所でも普遍的に存在する心の働き…愛や慈しみ、挫折感や失望、憧れ、未来への希望が
ごく当たり前の感覚として描かれてもいる。
占領下のエルサレムの実情は日本人にはなじみの薄いものですが、女性目線で描いたことで、物語に感情移入しやすい。
そのさじ加減がいい。
また、母の自殺、占領下のエルサレムという過酷な環境の中で、ヒンドゥの導きと確かな教育、母の不在を埋めるような深く温かな父の愛情によって、ジャーナリストにまでのぼりつめるミラルの姿は、物語の最後、未来への希望と繋がる。
自ら命を絶った母ナディアと自分で道を切り拓くミラルとの決定的な違いは、
きちんとした教育を受けていたかどうか、なんです。
例えば「愛情と教育の大切さ」って口で言うとどこか白々しく感じますが(私はw)、作品の流れの中で無理なくそれに気づかされました。
それから、ミラルのお父さんが素敵なんですよー。
背が高く、手足もすっと長い彼が温かい腕の中に幼いミラルを抱きしめ、
成長してからも包み込むような目線で娘を見つめ、そっと救いの手を差し伸べる。
特にラスト近く、実の娘ではないミラルを精一杯愛した彼の言葉に涙が…。
ちなみにミラルとは、野に咲く真っ赤な花の名前。
路傍の花と同じ名前の女性。
ミラルはエルサレムの街で普通に見かけるような女の子だ、という意味が
こめられているんでしょうね。
監督は『潜水服は蝶の夢を見る』のジュリアン・シュナーベル。
ユダヤ系の彼がパレスチナ側の目線から描いたことに意義がある。
ただし映像はひたすら美しく、うっとりするような色彩に満ち、陰惨な印象は薄い。
作品が政治的になりすぎることを回避したのかも。
主演は『スラムドッグ$ミリオネア』の女優さん。つまり、インド人。
魅力的だし、自然なお芝居で個人的には好きですが、現地の方が見たら違和感あるんじゃないかなぁ…。
そこがちょっと気になったり(笑)
この作品はアメリカ人の監督さんが撮っていますが、最近アジアや中近東、
中南米が舞台の映画が面白い。
DVDで見た『ペルシャ猫を誰も知らない』というイラン映画も良かったですし。
http://eiga.com/movie/55032/
『ミラル』もですが、テーマを選びやすいのかもしれないな。
その点からいくと、日本やアメリカが舞台の映画が、私小説風かエンタメに偏りがち
なのは仕方ないのかもしれません。
イヴ・サンローラン [DVD]
2012年7月20日 映画
美しいものが好きな人、美しいものに浸りたい人に。
ドキュメンタリーです。
イヴ・サンローランの名前をご存知の方は多いと思います。
が、その人となりとなると知らない人のほうが多いはず。
私もその一人です。
物心ついた頃から『YSL』のロゴデザインはハンカチやスカーフで目にしました。
原色を大胆に使ったグラフィカルなデザインがなんとなくマダァムな雰囲気で、
正直素敵だと思ったことはありませんでした。
…それらはおそらくあまりセンスのよろしくないライセンス契約品によって
刷り込まれたイメージだったのでしょう。
イヴの死後、公私ともに親密なパートナーであったピエール・ベルジェ(♂)は
20年の歳月を費やして2人で買い集めた美術品や家具を、クリスティーズで
競売にかけました。
世紀の競売といわれ、個人の出品としては過去最高額だったそうです。
冒頭、2人の愛の巣の様子を克明に捉えた映像が映し出されます。
パリのバビロン通りのアパルトマン。
くすんだ金と漆黒を基調に胡蝶蘭やユリ、カラーの花の白と葉の緑、膨大な数の本、絵や彫刻、インテリアで埋め尽くされた豪奢な空間。
大変な数のモノが、あるべき場所にぴたっと収まっている心地よさ。
どこからも美しく見えるよう、細心の注意と絶妙なバランスで配置されたそこは、
一つの宇宙、秘密の美術館のようです。
…この映像のためだけでも、見る価値があります。
一転、モロッコのマラケシュにある別荘(先日の「世界行ってみたらホントはこんなとこだった」にも登場した庭園)は、
タイルのブルーと紺、金色とオアシスの緑、豊かに流れる泉の水に象徴される
エキゾティックの極み。アラビアの王様の別荘のようです←イメージw
さらに2人の一番プライベートな場所であったろうノルマンディの田舎家(といっても日本人にとっては大邸宅ですが)は、プルーストの小説をイメージした隠れ家的空間で、大きなソファのある温かい雰囲気。
全てがパーフェクト。
うっとりと見とれながら、ふと考える。
こんな完璧な空間を作り出す精神の働きとはどんなふうなんだろう?
そして、なぜベルジェは愛の結晶ともいうべき品々を売り払う決意をしたのだろう?
サンローランは若くしてクリスチャン・ディオールのメゾンで働き、
ディオールの死後大抜擢されて、その後を引き継ぎます。
当時のインタビューで見る限り、内気で繊細そうな…だ、大丈夫!?って
心配になってしまうような青年でした…。
新生ディオールのショウの初回は大成功に終わり、そこで彼は運命の人・ベルジェと出会います。
その後ベルジェは、ディオールを辞めて自身の名前を冠したメゾンを立ち上げた
サンローランを、献身的な愛と凄腕ディレクターぶりで陰から支え続けるのです。
サンローランって根っからの芸術家気質です。
美しいものへの執念、信念はすごいのに、自分のプロデュースやコントロールは
まるっきりできません。
ドラッグやアルコールに溺れ、何度も精神的危機に直面しながら、なんとか
デザイナー人生を全うできたのは、ベルジェがいたからこそのようです
(といってもベルジェが語る物語ですから、実際のところはわかりませんが)
所謂、割れ鍋に綴じ蓋?(違)
ベルジェが見守る中、クリスティーズでの競売のために、思い出の品が部屋から
運び出されていきます。
一つ、また一つ。
壁から、棚から、テーブルの上から、美術品を扱う運送人たちの手で木箱に納められ
しっかり封をされ、旅だっていくモノたち。
最後にがらんとした空間が残ります。
それはまるで2人の思い出が一つずつ忘却の彼方に消えていくようにも見えます。
ベルジェにとってイヴの居ないこの部屋はそれほどまでに重荷なのでしょうか?
インタビュアーがベルジェに尋ねます。
「あなたはなぜ、2人の思い出の品を競売にかけようと思ったのですか?」
彼の答えはこうです。
もし、生き残ったのがイヴならたぶん競売にかけなかったろう。
それではしかし、ものたちはちりぢりばらばらになってしまう。
彼は生きているうちに、モノたちの行く末をしっかり見届けたかったのでしょう。
それは、遠からずイヴと同じように自分が旅立った後も、愛の結晶であるモノたちが
あるべきところで幸せに生き続けていくことを、自分自身に納得させたいという、
切なる願いだったのかもしれません。
ドキュメンタリーです。
イヴ・サンローランの名前をご存知の方は多いと思います。
が、その人となりとなると知らない人のほうが多いはず。
私もその一人です。
物心ついた頃から『YSL』のロゴデザインはハンカチやスカーフで目にしました。
原色を大胆に使ったグラフィカルなデザインがなんとなくマダァムな雰囲気で、
正直素敵だと思ったことはありませんでした。
…それらはおそらくあまりセンスのよろしくないライセンス契約品によって
刷り込まれたイメージだったのでしょう。
イヴの死後、公私ともに親密なパートナーであったピエール・ベルジェ(♂)は
20年の歳月を費やして2人で買い集めた美術品や家具を、クリスティーズで
競売にかけました。
世紀の競売といわれ、個人の出品としては過去最高額だったそうです。
冒頭、2人の愛の巣の様子を克明に捉えた映像が映し出されます。
パリのバビロン通りのアパルトマン。
くすんだ金と漆黒を基調に胡蝶蘭やユリ、カラーの花の白と葉の緑、膨大な数の本、絵や彫刻、インテリアで埋め尽くされた豪奢な空間。
大変な数のモノが、あるべき場所にぴたっと収まっている心地よさ。
どこからも美しく見えるよう、細心の注意と絶妙なバランスで配置されたそこは、
一つの宇宙、秘密の美術館のようです。
…この映像のためだけでも、見る価値があります。
一転、モロッコのマラケシュにある別荘(先日の「世界行ってみたらホントはこんなとこだった」にも登場した庭園)は、
タイルのブルーと紺、金色とオアシスの緑、豊かに流れる泉の水に象徴される
エキゾティックの極み。アラビアの王様の別荘のようです←イメージw
さらに2人の一番プライベートな場所であったろうノルマンディの田舎家(といっても日本人にとっては大邸宅ですが)は、プルーストの小説をイメージした隠れ家的空間で、大きなソファのある温かい雰囲気。
全てがパーフェクト。
うっとりと見とれながら、ふと考える。
こんな完璧な空間を作り出す精神の働きとはどんなふうなんだろう?
そして、なぜベルジェは愛の結晶ともいうべき品々を売り払う決意をしたのだろう?
サンローランは若くしてクリスチャン・ディオールのメゾンで働き、
ディオールの死後大抜擢されて、その後を引き継ぎます。
当時のインタビューで見る限り、内気で繊細そうな…だ、大丈夫!?って
心配になってしまうような青年でした…。
新生ディオールのショウの初回は大成功に終わり、そこで彼は運命の人・ベルジェと出会います。
その後ベルジェは、ディオールを辞めて自身の名前を冠したメゾンを立ち上げた
サンローランを、献身的な愛と凄腕ディレクターぶりで陰から支え続けるのです。
サンローランって根っからの芸術家気質です。
美しいものへの執念、信念はすごいのに、自分のプロデュースやコントロールは
まるっきりできません。
ドラッグやアルコールに溺れ、何度も精神的危機に直面しながら、なんとか
デザイナー人生を全うできたのは、ベルジェがいたからこそのようです
(といってもベルジェが語る物語ですから、実際のところはわかりませんが)
所謂、割れ鍋に綴じ蓋?(違)
ベルジェが見守る中、クリスティーズでの競売のために、思い出の品が部屋から
運び出されていきます。
一つ、また一つ。
壁から、棚から、テーブルの上から、美術品を扱う運送人たちの手で木箱に納められ
しっかり封をされ、旅だっていくモノたち。
最後にがらんとした空間が残ります。
それはまるで2人の思い出が一つずつ忘却の彼方に消えていくようにも見えます。
ベルジェにとってイヴの居ないこの部屋はそれほどまでに重荷なのでしょうか?
インタビュアーがベルジェに尋ねます。
「あなたはなぜ、2人の思い出の品を競売にかけようと思ったのですか?」
彼の答えはこうです。
もし、生き残ったのがイヴならたぶん競売にかけなかったろう。
それではしかし、ものたちはちりぢりばらばらになってしまう。
彼は生きているうちに、モノたちの行く末をしっかり見届けたかったのでしょう。
それは、遠からずイヴと同じように自分が旅立った後も、愛の結晶であるモノたちが
あるべきところで幸せに生き続けていくことを、自分自身に納得させたいという、
切なる願いだったのかもしれません。
ムスコのテストが終わったら一緒に見に行こうと約束していた『テルマエロマエ』。
本日ようやく観覧しました。
原作の漫画がとっても面白くて絵も好みだったので、期待/不安が五分五分。
かなり面白かったです。
(どうしても原作と比較しちゃうので100%とはいきませんが;)
原作者のヤマザキ マリさんが映画化にあたって譲れない条件としたのが
『主要キャストは全て日本人であること』だったそうな。
えええええ!?と思うけど、実はこれが成功への鍵だったんですねー。
テルマエの面白さは、古代ローマ人のルシウスが、ローマ風呂から現代日本の風呂へとタイムスリップして味わう強烈なカルチャー・ショックの数々。
彫の深いローマ人の彼からすると日本人の顔は平べったく、それ故風呂で出会った
オッサンや爺さんを『平たい顔の種族』と少々侮蔑的表現で形容する。
しかし、プラスティック成形された洗面器、鏡、風呂上がりに飲むフルーツ牛乳、
果てはトイレのウォッシュレットに至るまで、『平たい顔の種族』が生み出した
ハイテク(笑)バス・トイレタリーグッズの数々は、世界一進んだ文明を自負する
ローマ帝国国民であるルシウスに、衝撃とインスピレーションを与え続ける。
…ここのとこの、ルシウスの驚きの描写に、映画の面白さのキモがある。
それを阿部ちゃんは実に的確に・かつ巧みに演じているのです。
ほんっとに絶妙なんですよー…完璧。
これ、もしキャスティングにイタリア人俳優を持ってきても絶対ムリ。
日本の漫画を日本語で読み、物語の人物の間合いをきちっと
表現できるかどうかに全てがかかっているんですから。
一方、阿部ちゃんの絶妙なお芝居を受けて立つ市村正親さんも上手い。
ローマ皇帝ハドリアヌスという仰天な設定を、絶妙なさじ加減で演じきってます。
適度に芝居がかった台詞まわしと仕草が、阿部ちゃんのルシウスとうまーく
噛み合ってるんですよ。
ラストのやり取りなんか、ちょっとうるっと来てしまいました。
上戸彩さんのお父さん役、笹野さんがすごくいい味出してたなぁ〜…。
オッサン・爺さんがまた、個性的で味わいのある顔の方々ばかりでした
映画ってもちろん脚本やセット、衣装やライティングの出来不出来も仕上がりを
大きく左右しますが、やはり役者さんのセンスに負うところが大きいよなぁと、
改めて実感。
あ、でも撮影も本格的です。
チネチッタの、古代ローマを再現したセットを使用したそうです。
で、所々わざとチープにキッチュに撮ったシーンが差し込まれていて、
そのハズした感じも上手い。
作り手のセンスと計算の勝利ですね。
(*チネチッタ=ローマ郊外に位置する由緒ある映画撮影所)
そうそう。
ルシウス役の阿部ちゃん。
全裸(笑)シーンがたくさんあるのですが、素晴らしい肉体美を披露してますw
ウホッ!いいオトコ。←w
本日ようやく観覧しました。
原作の漫画がとっても面白くて絵も好みだったので、期待/不安が五分五分。
かなり面白かったです。
(どうしても原作と比較しちゃうので100%とはいきませんが;)
原作者のヤマザキ マリさんが映画化にあたって譲れない条件としたのが
『主要キャストは全て日本人であること』だったそうな。
えええええ!?と思うけど、実はこれが成功への鍵だったんですねー。
テルマエの面白さは、古代ローマ人のルシウスが、ローマ風呂から現代日本の風呂へとタイムスリップして味わう強烈なカルチャー・ショックの数々。
彫の深いローマ人の彼からすると日本人の顔は平べったく、それ故風呂で出会った
オッサンや爺さんを『平たい顔の種族』と少々侮蔑的表現で形容する。
しかし、プラスティック成形された洗面器、鏡、風呂上がりに飲むフルーツ牛乳、
果てはトイレのウォッシュレットに至るまで、『平たい顔の種族』が生み出した
ハイテク(笑)バス・トイレタリーグッズの数々は、世界一進んだ文明を自負する
ローマ帝国国民であるルシウスに、衝撃とインスピレーションを与え続ける。
…ここのとこの、ルシウスの驚きの描写に、映画の面白さのキモがある。
それを阿部ちゃんは実に的確に・かつ巧みに演じているのです。
ほんっとに絶妙なんですよー…完璧。
これ、もしキャスティングにイタリア人俳優を持ってきても絶対ムリ。
日本の漫画を日本語で読み、物語の人物の間合いをきちっと
表現できるかどうかに全てがかかっているんですから。
一方、阿部ちゃんの絶妙なお芝居を受けて立つ市村正親さんも上手い。
ローマ皇帝ハドリアヌスという仰天な設定を、絶妙なさじ加減で演じきってます。
適度に芝居がかった台詞まわしと仕草が、阿部ちゃんのルシウスとうまーく
噛み合ってるんですよ。
ラストのやり取りなんか、ちょっとうるっと来てしまいました。
上戸彩さんのお父さん役、笹野さんがすごくいい味出してたなぁ〜…。
オッサン・爺さんがまた、個性的で味わいのある顔の方々ばかりでした
映画ってもちろん脚本やセット、衣装やライティングの出来不出来も仕上がりを
大きく左右しますが、やはり役者さんのセンスに負うところが大きいよなぁと、
改めて実感。
あ、でも撮影も本格的です。
チネチッタの、古代ローマを再現したセットを使用したそうです。
で、所々わざとチープにキッチュに撮ったシーンが差し込まれていて、
そのハズした感じも上手い。
作り手のセンスと計算の勝利ですね。
(*チネチッタ=ローマ郊外に位置する由緒ある映画撮影所)
そうそう。
ルシウス役の阿部ちゃん。
全裸(笑)シーンがたくさんあるのですが、素晴らしい肉体美を披露してますw
ウホッ!いいオトコ。←w
アビチャッポン・ウィーラセタクン監督作品。
横浜トリエンナーレでショートフィルムと写真で構成された作品を見て
ちょっと好きな感じだったのと、
2010年カンヌでパルムドールを獲ったというので見てみました。
ブンミおじさんはタイの田舎で農場を営んでいて、そのすぐ先には
深い森が広がっている。
腎臓を患い余命いくばくもない彼が、19年前に亡くなった妻の妹とその息子を呼び寄せ、
3人で夕食を摂っている。
そこにいきなり亡くなった妻の亡霊が現れ、驚いているうちに今度は
13年前に行方不明になった息子が異形の生き物となって現れる、というお話。
ファンタジーなんです、一応。
でもキラキラの夢の世界の扉が開くわけでも、CGを多用した冒険があるわけでもない。
妻の亡霊といっても普通に女優さんが淡々と喋ってるだけですし、異形の元息子は
猿の惑星の猿みたいな姿で堂々と出てきます...なんせ猿の精霊になってしまったので(笑)
面白いのが、妻の亡霊や猿の精霊の息子の登場に、ブンミおじさん含め一同が
一応びっくりするんだけど、すぐに受け入れ、
まるで葬式で久々に会った親戚同士のごとく淡々と語りあうところ。
まぁ考えてみれば、日本や中国の昔話には死んだ人が帰ってきて思い出話をする、
というような展開は結構あるので、不思議じゃないのかも。
タイトル通り、この作品の主人公は<森>です。
ブンミおじさんの農園や家の中にはいつも森の気配が入り込んでくる。
それは絶えずバックに流れている様々な虫の声や、木や草がこすれあったり、
目に見えない生き物が歩き回るときの<音>で表現されていて、
見ている私もその場に居て、同じ空気を感じているような不思議な感覚でした。
田舎育ちのせいか、不気味なんだけど妙に気分が安らぐ(笑)
いよいよ死期を悟ったブンミおじさんは亡霊の妻に導かれるまま、
妻の妹とその息子を伴って、真夜中の森に分け入っていく。
その様子を赤く光る目をした猿の精霊達が見守っている。
(この辺り、ちょっと「もののけ姫」を連想させるのだった)
やがて森の最奥にある洞窟へと辿りつく。
鍾乳石や土ボタルの光る神秘的な洞窟の中。
『生きてるときには忘れていたが、私はここで生まれたのだった』
その夜、ブンミおじさんは洞窟の奥で静かに息を引き取った。
人間はどこからやってきてどこに行くのか。
ブンミおじさんは森の奥からやってきて、再び森へ戻っていった。
ある意味、森の中の巨大な子宮へ回帰したとも見える最期。
死と再生を司る森に抱かれている限り、命は永遠のサイクルで繋がっていく。
しかし、森=巨大な子宮からとうの昔に切り離された世界に住む人間にとって、
戻るべき場所は一体何処にあるんだろう。
余談ですが、この森の空気感といい、その奥底に人知れずぽっかりと開いた洞窟が
墓場でありかつ子宮である、というイメージはShitaoの再生シーンを思い出します。
アーティスティックな映画を撮るタイの映像作家。
フランス在住ながらアジアの原風景に拘る映画監督。
作風の違う二人の個性的映画監督が、同じ目線で『森』を描きだしたところが
非常に興味深い。
横浜トリエンナーレでショートフィルムと写真で構成された作品を見て
ちょっと好きな感じだったのと、
2010年カンヌでパルムドールを獲ったというので見てみました。
ブンミおじさんはタイの田舎で農場を営んでいて、そのすぐ先には
深い森が広がっている。
腎臓を患い余命いくばくもない彼が、19年前に亡くなった妻の妹とその息子を呼び寄せ、
3人で夕食を摂っている。
そこにいきなり亡くなった妻の亡霊が現れ、驚いているうちに今度は
13年前に行方不明になった息子が異形の生き物となって現れる、というお話。
ファンタジーなんです、一応。
でもキラキラの夢の世界の扉が開くわけでも、CGを多用した冒険があるわけでもない。
妻の亡霊といっても普通に女優さんが淡々と喋ってるだけですし、異形の元息子は
猿の惑星の猿みたいな姿で堂々と出てきます...なんせ猿の精霊になってしまったので(笑)
面白いのが、妻の亡霊や猿の精霊の息子の登場に、ブンミおじさん含め一同が
一応びっくりするんだけど、すぐに受け入れ、
まるで葬式で久々に会った親戚同士のごとく淡々と語りあうところ。
まぁ考えてみれば、日本や中国の昔話には死んだ人が帰ってきて思い出話をする、
というような展開は結構あるので、不思議じゃないのかも。
タイトル通り、この作品の主人公は<森>です。
ブンミおじさんの農園や家の中にはいつも森の気配が入り込んでくる。
それは絶えずバックに流れている様々な虫の声や、木や草がこすれあったり、
目に見えない生き物が歩き回るときの<音>で表現されていて、
見ている私もその場に居て、同じ空気を感じているような不思議な感覚でした。
田舎育ちのせいか、不気味なんだけど妙に気分が安らぐ(笑)
いよいよ死期を悟ったブンミおじさんは亡霊の妻に導かれるまま、
妻の妹とその息子を伴って、真夜中の森に分け入っていく。
その様子を赤く光る目をした猿の精霊達が見守っている。
(この辺り、ちょっと「もののけ姫」を連想させるのだった)
やがて森の最奥にある洞窟へと辿りつく。
鍾乳石や土ボタルの光る神秘的な洞窟の中。
『生きてるときには忘れていたが、私はここで生まれたのだった』
その夜、ブンミおじさんは洞窟の奥で静かに息を引き取った。
人間はどこからやってきてどこに行くのか。
ブンミおじさんは森の奥からやってきて、再び森へ戻っていった。
ある意味、森の中の巨大な子宮へ回帰したとも見える最期。
死と再生を司る森に抱かれている限り、命は永遠のサイクルで繋がっていく。
しかし、森=巨大な子宮からとうの昔に切り離された世界に住む人間にとって、
戻るべき場所は一体何処にあるんだろう。
余談ですが、この森の空気感といい、その奥底に人知れずぽっかりと開いた洞窟が
墓場でありかつ子宮である、というイメージはShitaoの再生シーンを思い出します。
アーティスティックな映画を撮るタイの映像作家。
フランス在住ながらアジアの原風景に拘る映画監督。
作風の違う二人の個性的映画監督が、同じ目線で『森』を描きだしたところが
非常に興味深い。
シャーロック・『ロバダニ』・ホームズにモエ。
2012年3月27日 映画映画館に行く時は自転車なので天気のいい日がほとんどです。
今日は風は強くて花粉飛びまくりですが、温かくて自転車日和でした。
自転車の何がいいって、空気の匂いを感じるところです。
甘美でふくよかな梅の香りだけでなく、スパイシーで微かに漢方を連想させる沈丁花も。
白い辛夷も咲きかけてました。
春だ!!!!!
ということで。
今日は春休み中のムスコと『シャーロック・ホームズ シャドウゲーム』へ。
http://wwws.warnerbros.co.jp/sherlockholmes2/
↑のトレイラーで大体わかっちゃう感じなんですけど(笑)
面白いです。
かなり笑えます。
アクションてんこ盛りです。
長い映画ですが、ほとんど飽きさせません。
そして何より、ロバダニ萌えの映画です。
頭良すぎのせいで他人と上手くいかない、孤独で捻くれた中年wのおっさん子供が、
自分とは正反対の、生まじめで優しい大人の男に全力で懐いて、振り回すお話です。
ロバダニのホームズがもう、なんというか...可愛いすぐる(´∀`)
他のキャラクターも舞台設定も、全ては二人の怪しいw関係性を、より魅力的に
見せる装置にすぎません。
モリアーティ教授の地味さが象徴的。
天才VS天才の対決が見せ場のはずなんだけどなー...。
ロバダニのホームズにハマれるか否かで、楽しめる度合いが全然違うかも。
ホームズったら毒薬マニアかつ写真記憶の持ち主なんだよね。
彼の脳内にまんま侵入するかのような凝った映像は、少し前なら実現困難だったはず。
SF的未来でなく、敢て過去を...19世紀末~20世紀初頭の雰囲気を、
最新のテクノロジーを駆使して表現する、というちょっと捻った発想も魅力の一つ。
エンディングのバックに流れる映像が象徴的です。
昨夜のすますまといい、二日続けて萌えを堪能(笑)
WORLD ORDER×SM@P何回もリピしました。
青イナの出だしの声がもーエロくてエロくて。
最初どっから声がしてんのかわかんなくて。
あれ?どこに居るんだよキムラ~~~~!?
...と探してたら左下から、
寝そべった状態→どっこらしょと二人がかりで起こす
→スイッチの入ったロボットのようにスーッと動き出す
の一連の流れがたまらなくエエです。
全体のパフォーマンスの雰囲気にすっかり馴染みながらもしっかり目立つ。
流石ですね。
いや~...一気に春がきた感じですわ(人´∀`).☆.。.:*・゚
今日は風は強くて花粉飛びまくりですが、温かくて自転車日和でした。
自転車の何がいいって、空気の匂いを感じるところです。
甘美でふくよかな梅の香りだけでなく、スパイシーで微かに漢方を連想させる沈丁花も。
白い辛夷も咲きかけてました。
春だ!!!!!
ということで。
今日は春休み中のムスコと『シャーロック・ホームズ シャドウゲーム』へ。
http://wwws.warnerbros.co.jp/sherlockholmes2/
↑のトレイラーで大体わかっちゃう感じなんですけど(笑)
面白いです。
かなり笑えます。
アクションてんこ盛りです。
長い映画ですが、ほとんど飽きさせません。
そして何より、ロバダニ萌えの映画です。
頭良すぎのせいで他人と上手くいかない、孤独で捻くれた中年wのおっさん子供が、
自分とは正反対の、生まじめで優しい大人の男に全力で懐いて、振り回すお話です。
ロバダニのホームズがもう、なんというか...可愛いすぐる(´∀`)
他のキャラクターも舞台設定も、全ては二人の怪しいw関係性を、より魅力的に
見せる装置にすぎません。
モリアーティ教授の地味さが象徴的。
天才VS天才の対決が見せ場のはずなんだけどなー...。
ロバダニのホームズにハマれるか否かで、楽しめる度合いが全然違うかも。
ホームズったら毒薬マニアかつ写真記憶の持ち主なんだよね。
彼の脳内にまんま侵入するかのような凝った映像は、少し前なら実現困難だったはず。
SF的未来でなく、敢て過去を...19世紀末~20世紀初頭の雰囲気を、
最新のテクノロジーを駆使して表現する、というちょっと捻った発想も魅力の一つ。
エンディングのバックに流れる映像が象徴的です。
昨夜のすますまといい、二日続けて萌えを堪能(笑)
WORLD ORDER×SM@P何回もリピしました。
青イナの出だしの声がもーエロくてエロくて。
最初どっから声がしてんのかわかんなくて。
あれ?どこに居るんだよキムラ~~~~!?
...と探してたら左下から、
寝そべった状態→どっこらしょと二人がかりで起こす
→スイッチの入ったロボットのようにスーッと動き出す
の一連の流れがたまらなくエエです。
全体のパフォーマンスの雰囲気にすっかり馴染みながらもしっかり目立つ。
流石ですね。
いや~...一気に春がきた感じですわ(人´∀`).☆.。.:*・゚
1992年公開。
IRAの下部組織を名乗るテロ集団が
英国軍の黒人兵士・ジョディを人質にする。
ファーガスはジョディを見張るうち
図らずも心を通わせ、彼の遺言を託される。
「ロンドンのメトロってクラブで恋人にマルガリータを奢ってやってくれ。
そして俺が愛してたって伝えて欲しい。」
渡された写真一枚。褐色の肌に長い髪のセクシーな女。
人質処刑の朝、アジトは政府軍に奇襲され、混乱の中ジョディは事故死。
ファーガスは辛くも生き延びて、名前を変え、ロンドンで暮らし始める。
やがて彼は遺言にしたがって「メトロ」でジョディの恋人と出会う。
ディルという名の彼女はスリムで色っぽく、不思議な雰囲気を漂わせていた。
ぴったりしたドレスと幻想的な身振りで【Crying Game】を歌う彼女に
ファーガスは強く惹かれる。
派手な外見とは裏腹に、一度好きになった男に全てを捧げてしまう一途な女、ディル。
しかし初めての夜、ファーガスの前でバスローブを脱ぎ一糸纏わぬ姿になった彼女は
実は男だった。
衝撃のあまりディルを拒絶するファーガス。
一方、かつてのテロリスト仲間の生き残りがファーガスを探し出し、彼にテロ行為を強要する。
自分が逃げればディルの命はない。
ファーガスは、身を捨ててディルを守ろうとするが...。
過去のある男と、実は男性の美女とのラブ・ロマンス。
テロリスト絡みのサスペンス。
二つの側面を絶妙に絡み合わせ、意外な方向へと展開していく脚本がお見事。
20年も前の作品だし、見るからに低予算なんだけど、
とにかく面白くて最後まで一気に見てしまいます。
ファーガス役の俳優さん、特にかっこよくもハンサムでもない、
どっちかというと地味でごく普通の男性。
男であると分った途端、キスも甘い言葉も全てなかったことにして
自分を拒絶するファーガスに
「私のこと嫌いじゃないでしょ?」
「優しくしてよ」
と何度も問いかけ、尽くし、愛されようとするディル。
ことあるごとに『それが女ってものよ』『女はそれに耐えられないの』と口にし、
その度にファーガスに「君は女じゃないだろ。」と否定されるけれど、全然めげない(笑)
男の体を持つディルをどうしても受け入れられないけれど、優しく真摯に接するファーガスに
心底惚れこんで仔猫のように纏わりつくディルがひたすらいじらしく可愛い。
最初はただ義務感と罪悪感からディルの身を案じていたファーガスが、少しずつ
ディルのひたむきさに心を開き、人として惹かれていくさまがスリリングでロマンティック。
面白いなぁと思ったのが、ファーガスを追ってくる元仲間のテロリストの女が、
ディルとは対照的に計算ずくの色仕掛けで彼を操ろうとするところ。
女の体に生まれ、当然のようにそれを武器として利用しようとする女。
男の体に生まれ、心と体のギャップに何度も傷つきながら、
女としてひたすら男を愛し尽くそうとする女。
二人の女に惑わされ翻弄される男。
その生い立ちや体がどうあれ、女の心はしなやかで逞しい。
ラストの意外などんでん返しも気持ちのいい終わり方。
タイトルであり、ディルが妖しく歌う【Crying Game】の歌詞。
♪ふと気づくと去っていくあなたの後ろ姿
涙のゲームはもういやだわ
涙のゲームはいらないの・・・♪
うたかたの恋のゲームで何度も涙を流した彼女。
ただ一人、ありのままの自分を愛してくれたジョディを失った嘆きと諦めとが
象徴的に歌われています。
http://www.youtube.com/watch?v=xF59nPVCUsw
IRAの下部組織を名乗るテロ集団が
英国軍の黒人兵士・ジョディを人質にする。
ファーガスはジョディを見張るうち
図らずも心を通わせ、彼の遺言を託される。
「ロンドンのメトロってクラブで恋人にマルガリータを奢ってやってくれ。
そして俺が愛してたって伝えて欲しい。」
渡された写真一枚。褐色の肌に長い髪のセクシーな女。
人質処刑の朝、アジトは政府軍に奇襲され、混乱の中ジョディは事故死。
ファーガスは辛くも生き延びて、名前を変え、ロンドンで暮らし始める。
やがて彼は遺言にしたがって「メトロ」でジョディの恋人と出会う。
ディルという名の彼女はスリムで色っぽく、不思議な雰囲気を漂わせていた。
ぴったりしたドレスと幻想的な身振りで【Crying Game】を歌う彼女に
ファーガスは強く惹かれる。
派手な外見とは裏腹に、一度好きになった男に全てを捧げてしまう一途な女、ディル。
しかし初めての夜、ファーガスの前でバスローブを脱ぎ一糸纏わぬ姿になった彼女は
実は男だった。
衝撃のあまりディルを拒絶するファーガス。
一方、かつてのテロリスト仲間の生き残りがファーガスを探し出し、彼にテロ行為を強要する。
自分が逃げればディルの命はない。
ファーガスは、身を捨ててディルを守ろうとするが...。
過去のある男と、実は男性の美女とのラブ・ロマンス。
テロリスト絡みのサスペンス。
二つの側面を絶妙に絡み合わせ、意外な方向へと展開していく脚本がお見事。
20年も前の作品だし、見るからに低予算なんだけど、
とにかく面白くて最後まで一気に見てしまいます。
ファーガス役の俳優さん、特にかっこよくもハンサムでもない、
どっちかというと地味でごく普通の男性。
男であると分った途端、キスも甘い言葉も全てなかったことにして
自分を拒絶するファーガスに
「私のこと嫌いじゃないでしょ?」
「優しくしてよ」
と何度も問いかけ、尽くし、愛されようとするディル。
ことあるごとに『それが女ってものよ』『女はそれに耐えられないの』と口にし、
その度にファーガスに「君は女じゃないだろ。」と否定されるけれど、全然めげない(笑)
男の体を持つディルをどうしても受け入れられないけれど、優しく真摯に接するファーガスに
心底惚れこんで仔猫のように纏わりつくディルがひたすらいじらしく可愛い。
最初はただ義務感と罪悪感からディルの身を案じていたファーガスが、少しずつ
ディルのひたむきさに心を開き、人として惹かれていくさまがスリリングでロマンティック。
面白いなぁと思ったのが、ファーガスを追ってくる元仲間のテロリストの女が、
ディルとは対照的に計算ずくの色仕掛けで彼を操ろうとするところ。
女の体に生まれ、当然のようにそれを武器として利用しようとする女。
男の体に生まれ、心と体のギャップに何度も傷つきながら、
女としてひたすら男を愛し尽くそうとする女。
二人の女に惑わされ翻弄される男。
その生い立ちや体がどうあれ、女の心はしなやかで逞しい。
ラストの意外などんでん返しも気持ちのいい終わり方。
タイトルであり、ディルが妖しく歌う【Crying Game】の歌詞。
♪ふと気づくと去っていくあなたの後ろ姿
涙のゲームはもういやだわ
涙のゲームはいらないの・・・♪
うたかたの恋のゲームで何度も涙を流した彼女。
ただ一人、ありのままの自分を愛してくれたジョディを失った嘆きと諦めとが
象徴的に歌われています。
http://www.youtube.com/watch?v=xF59nPVCUsw
Exit Through the Gift Shop [DVD]
2012年3月3日 映画
現代アート、特にストリート・カルチャーから派生してきた種類のアートの
<価値>って何?
というギモンをユーモアたっぷりに、ギミックに、
しかも面白く見せてしまうドキュメンタリー。
...や、ほんとにドキュメンタリーなの?
全部やらせちゃう?
見終わった後、思わずMBW(ミスター・ブレイン・ウォッシュ)をググってしまいました。
監督:バンクシー。
↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC
芸術テロリストって呼ばれているらしい(笑)
この映画の問いかけってある意味重いです。
アートがビジネスとして成立すること。
一見落書きみたいな作品が高値で取引されること。
メディアやインターネットを巧く利用すれば、無名のアーティストの作品でも
数万ドルの値がつくこと。
アートに崇高さを求め、アーティストの仕事にある種の神秘性を見出そうとする人には、
とても挑戦的な作品だと感じられるかもしれません。
個人的にはMBWの作品には全く独創性も美しさカッコよさも感じないのだけれど、
皆は彼の<仕掛け>を楽しみ、楽しませてくれたことに価値を見出している。
ように見えました。
ん~...しかしやっぱりMBW=バンクシーじゃないかなぁ...。
あ、そうだ。
ほんの一瞬ですけど、BECK、ノエル・ギャラガー、ブラッド・ピット、ジュード・ロウ
といった方々が映りこんでいたりします♪
さすがLA。
<価値>って何?
というギモンをユーモアたっぷりに、ギミックに、
しかも面白く見せてしまうドキュメンタリー。
...や、ほんとにドキュメンタリーなの?
全部やらせちゃう?
見終わった後、思わずMBW(ミスター・ブレイン・ウォッシュ)をググってしまいました。
監督:バンクシー。
↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC
芸術テロリストって呼ばれているらしい(笑)
この映画の問いかけってある意味重いです。
アートがビジネスとして成立すること。
一見落書きみたいな作品が高値で取引されること。
メディアやインターネットを巧く利用すれば、無名のアーティストの作品でも
数万ドルの値がつくこと。
アートに崇高さを求め、アーティストの仕事にある種の神秘性を見出そうとする人には、
とても挑戦的な作品だと感じられるかもしれません。
個人的にはMBWの作品には全く独創性も
皆は彼の<仕掛け>を楽しみ、楽しませてくれたことに価値を見出している。
ように見えました。
ん~...しかしやっぱりMBW=バンクシーじゃないかなぁ...。
あ、そうだ。
ほんの一瞬ですけど、BECK、ノエル・ギャラガー、ブラッド・ピット、ジュード・ロウ
といった方々が映りこんでいたりします♪
さすがLA。
スプリング・フィーバー [DVD]
2012年1月27日 映画
魔性のゲイ(=ジャン)を巡る男女入り乱れての愛憎劇@中国。
...と書くとなんか凄そうですが、
全編を通して印象的なのはタイトル通りの、
春風に浮されたように一瞬燃え上がる熱情と
それが通りすぎた後の虚しさ。
冒頭、まだ春先の冷たい雨に打たれる車内の、ただならぬ雰囲気の
男二人のシーンからはじまるのですが、
その雨が晴れの日であってもどこか日陰で降り続いているような、
ひんやりして灰色の空気と湿気を、
見ている間中ずーっと感じていました。
郊外の貸し別荘で男二人が全裸で愛し合うシーンに結構びっくりしますが、
ブエノスアイレスもそうだったよな~...とついつい比較(笑)
でもカーウァイ監督の作品ほどスタイリッシュでも難解でもなく、
先の読めない展開に一気に最後まで見てしまいました。
一人目の男は既婚者。
妻は学校の教師で本人は古本屋の店主。
勘の鋭い妻は夫の不倫を疑い、フリーター(中国語ではなんていうのだろう?)の青年に
尾行を依頼、浮気相手が実は男であると知り逆上。
浮気相手(=ジャン)が働く旅行代理店に乗り込んで修羅場に...。
既婚者の男を慮って会わないことにした彼に、今度は尾行していたフリーターが堕ちてしまう。
そのフリーターの彼には工場で働く彼女(菊池凛子似w)がいる。
成り行きで一緒に旅に出ることになった男と男と女。
裸で絡むシーンがたくさん出てきますが、ポルノっぽくはないです。
浮かびあがってくるのはむしろ、性別やパートナーの有る無しに関係なく、
突然湧き上がってくる理性ではコントロールできない熱情。
しかしジャンの恋愛対象が同性である限り、その熱情が結実することは決してない。
なので、彼の愛情は常にどこかうわの空。
そんなジャンに捨てられたと知り、自ら命を絶つ一人目の男。
死と引替えに、男との熱情の日々はジャンの心と身体に永遠に消えない傷跡となって残る。
センチメンタリズムに陥りそうな展開ですが、適度な距離を保ちつつ
心の襞を丹念に拾う演出と、
なんとなく他人のプライバシーを覗き見してるような後ろめたさとリアルさのある映像の力で、強度のある美しさへと昇華されている。
後半、ジャンと二人目の愛人とその恋人(女性)が遊覧船に乗るシーンがあって、
構図といい人物の表情といい、昔見たフランス映画を思い出した。
(*↑DVDジャケットの写真参考)
なんだか懐かしい感じがしたのはそのせいかもしれません。
ところどころに挿入される漢詩の字面がエキゾティックで美しく、
また朗読する声も響きが心地よい。
原題は「春風沈酔的晩上」。
この詩の意味が作品の中で出てくる。
「スプリング・フィーバー」の邦題も意味深でいいけどね。
ゲイ+ロードムービー。
中国がすでに<共産主義国家>のイメージからはかけ離れていることは知ってましたが、
こんな映画撮れるんだ!
...とびっくりしてたら、ロウ・イエ監督はこれの一つ前の作品で政府から
「5年間、映画を撮るべからず。」
とお達しを受けたにもかかわらず、ゲリラ撮影で完成させたのだとか。
ううむ。
キモのすわりかたが違うね...。
そういうの映像から自然と伝わってくるもんなんだよなぁ、やっぱり。
...と書くとなんか凄そうですが、
全編を通して印象的なのはタイトル通りの、
春風に浮されたように一瞬燃え上がる熱情と
それが通りすぎた後の虚しさ。
冒頭、まだ春先の冷たい雨に打たれる車内の、ただならぬ雰囲気の
男二人のシーンからはじまるのですが、
その雨が晴れの日であってもどこか日陰で降り続いているような、
ひんやりして灰色の空気と湿気を、
見ている間中ずーっと感じていました。
郊外の貸し別荘で男二人が全裸で愛し合うシーンに結構びっくりしますが、
ブエノスアイレスもそうだったよな~...とついつい比較(笑)
でもカーウァイ監督の作品ほどスタイリッシュでも難解でもなく、
先の読めない展開に一気に最後まで見てしまいました。
一人目の男は既婚者。
妻は学校の教師で本人は古本屋の店主。
勘の鋭い妻は夫の不倫を疑い、フリーター(中国語ではなんていうのだろう?)の青年に
尾行を依頼、浮気相手が実は男であると知り逆上。
浮気相手(=ジャン)が働く旅行代理店に乗り込んで修羅場に...。
既婚者の男を慮って会わないことにした彼に、今度は尾行していたフリーターが堕ちてしまう。
そのフリーターの彼には工場で働く彼女(菊池凛子似w)がいる。
成り行きで一緒に旅に出ることになった男と男と女。
裸で絡むシーンがたくさん出てきますが、ポルノっぽくはないです。
浮かびあがってくるのはむしろ、性別やパートナーの有る無しに関係なく、
突然湧き上がってくる理性ではコントロールできない熱情。
しかしジャンの恋愛対象が同性である限り、その熱情が結実することは決してない。
なので、彼の愛情は常にどこかうわの空。
そんなジャンに捨てられたと知り、自ら命を絶つ一人目の男。
死と引替えに、男との熱情の日々はジャンの心と身体に永遠に消えない傷跡となって残る。
センチメンタリズムに陥りそうな展開ですが、適度な距離を保ちつつ
心の襞を丹念に拾う演出と、
なんとなく他人のプライバシーを覗き見してるような後ろめたさとリアルさのある映像の力で、強度のある美しさへと昇華されている。
後半、ジャンと二人目の愛人とその恋人(女性)が遊覧船に乗るシーンがあって、
構図といい人物の表情といい、昔見たフランス映画を思い出した。
(*↑DVDジャケットの写真参考)
なんだか懐かしい感じがしたのはそのせいかもしれません。
ところどころに挿入される漢詩の字面がエキゾティックで美しく、
また朗読する声も響きが心地よい。
原題は「春風沈酔的晩上」。
この詩の意味が作品の中で出てくる。
「スプリング・フィーバー」の邦題も意味深でいいけどね。
ゲイ+ロードムービー。
中国がすでに<共産主義国家>のイメージからはかけ離れていることは知ってましたが、
こんな映画撮れるんだ!
...とびっくりしてたら、ロウ・イエ監督はこれの一つ前の作品で政府から
「5年間、映画を撮るべからず。」
とお達しを受けたにもかかわらず、ゲリラ撮影で完成させたのだとか。
ううむ。
キモのすわりかたが違うね...。
そういうの映像から自然と伝わってくるもんなんだよなぁ、やっぱり。